映像化されたものの感想などを追っかけて行くと、この小説版をベースにいろいろ批評されている部分もあるようにみえたので読んでみた。
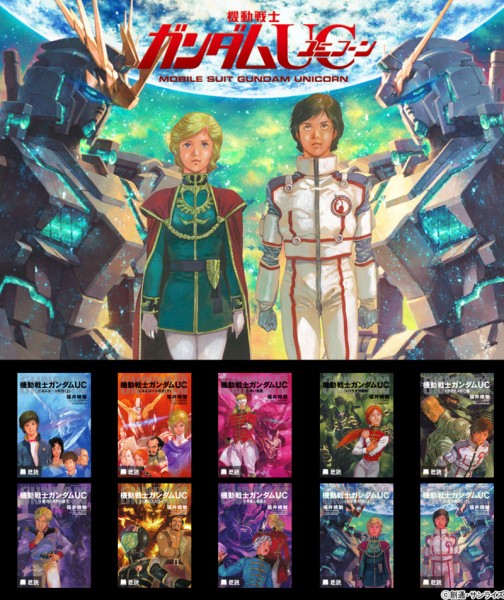
例の角川dowangoの合併セールにてBOOKWLAKERの電子版を。
続きを読む

映像化されたものの感想などを追っかけて行くと、この小説版をベースにいろいろ批評されている部分もあるようにみえたので読んでみた。
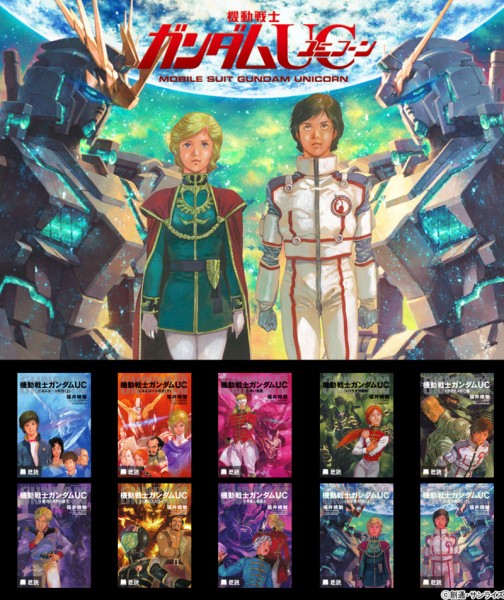
例の角川dowangoの合併セールにてBOOKWLAKERの電子版を。
続きを読む
最初は史料を元にした新説の一冊かな、と思って購入したが小説。その時点で「あ、こりゃはずしたかも」と思ったらさにあらず。
たぶん信長や秀吉、光秀を追っかけるなら必ず出てくるいわゆる”金ヶ崎の退き口”を新規な切り口で描いた非常に面白い一冊だった。
京に入り足利将軍を擁したとはいえ、いまだ天下布武の道半ばにある信長は、京の目の上のたんこぶとも言える越前・朝倉勢を攻めようとする。しかしその攻略の必須条件は北近江・浅井勢の同調―それがないと北上する軍勢の横っぱらを浅井が突くことになるからだ。いまだ武勲はないがその交渉力で対浅井の調略を行っていた秀吉、味方でありつつも信長を疎ましく思い暗躍する足利将軍の名代・光秀、そして織田の最大の同盟の盟主とも言える家康―信長の「浅井は敵対せぬ」との観に背き、彼らの側面を浅井勢が襲う。その報を受けて信長は全ての兵を捨て、単騎京へと脱出する。結果、後に天下を順に治めることになる三者は残された寡兵をもって襲い掛かる浅井・朝倉勢相手の壮絶な撤退戦を開始した―。
今年は国内のデング熱騒ぎといい、いまだ油断できないエボラ出血熱といい、けっこう深刻な事態につながりかねない感染症の流行が相次いでいるので、ふと数年前のこの作品のことを思い出して改めて読んでみた。
bookwalkerにて。今回のセールじゃなくて以前なにかのキャンペーン時に購入して積ん読になってたものを。
日本海沿岸で大規模演習を展開していた自衛隊だが、その最中、新潟と富山の県境の境川にある臨時の補給物資の集積所に待機していた数十名の隊員たちはその装備とともにタイムスリップに巻き込まれる。彼らはいつの間にか戦国時代へタイムスリップしていた。伊庭義明・三等陸尉たちはそこで出会った長尾景虎に協力し、とりあえずの部隊の安定を図るが、彼らとともに持ち込まれた近代兵器、その威力故に、彼らも否応なしにその戦乱の中に巻き込まれてゆく・・・。
bookwalkerの角川セールにて電子版を。
山田風太郎によるいわゆる”柳生十兵衛三部作”の一作。江戸・徳川時代の初期、会津藩・加藤明成のもとを退転した堀主水の一族だったが、男たちは捉われ鎌倉の女人寺に身を寄せていた女衆も、加藤配下の”会津七本槍”の手によって虐殺されてしまう。しかしその事を起こした女人寺・東慶寺の住持・天秀尼は神君家康の孫・千姫の庇護下にある人物だった。その残虐な手口と男子不入の女人寺にまで立ち入っての狼藉に千姫は加藤との対決を決意し、生き残りの女衆七人に加藤を討たせようとする。その七人のもとへ老僧・沢庵を介して隻眼の剣士が現われた。