映像化されたものの感想などを追っかけて行くと、この小説版をベースにいろいろ批評されている部分もあるようにみえたので読んでみた。
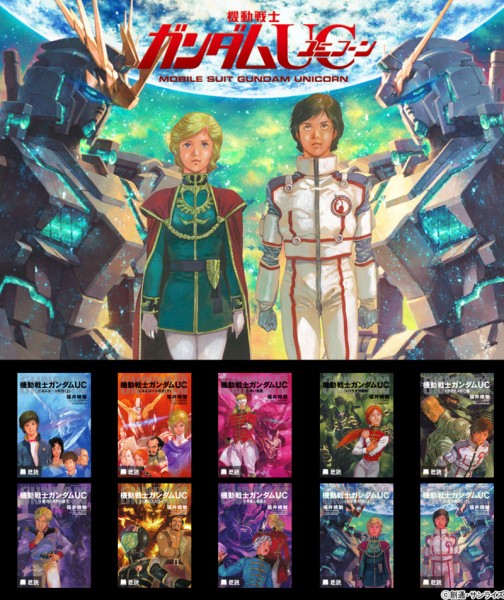
例の角川dowangoの合併セールにてBOOKWLAKERの電子版を。
今年完結したEP7みた直後から、原作にあたるこの小説版は読んでみたいな、とは思っていた。
しかしまとまって買うとけっこうなお値段することと、実は下記のバージョンの装丁がいいなあと思っていたので、どうしたもんかと悩んでいたんだが前述のようにセールがあったことと、作中の”宇宙軍再編計画”ならぬ”本棚再編計画”(笑)で物理版はなるべく減らそうとしてた真っ最中だったので、今回素直に電書版を購入。
角川書店(角川グループパブリッシング)
売り上げランキング: 441,209
(安彦氏の表紙もいいんだが、やっぱり軽くSFオタ入ってる身としてはこちらもいいよねえ―おまけに今回の電書版挿絵は別の人でけっこうひどいレベルだったし・・・)
で、内容である。
まず意外だったのが映像版のEP3までにあたる5巻目ぐらいまでは、びっくりするほどこの小説版に忠実に映像化されているということ。
各まとめサイト等では散々『原作からいろいろ端折りすぎ!』と叩かれる原因になっていたようだが、すくなくともこの5巻目まではそういった印象は薄く、むしろ良くこの分量をあの尺で正確に落としこめたな、というのが強く印象に残った。
ある意味これは、1,2巻が『ユニコーンの日』の題で上下巻である、という構成を見てもらえば分かるように、ここで主人公とヒロインの二人の出会いを描きつつ、「スペースコロニーのある世界」の描写―そのディティールを、これでもか、と徹底的に描くことにけっこうな量を割いていたからだろうか。
そしてこの丁寧さの部分に”プロの”小説家ならではの部分を強く感じた。そしてだからこそ映像というメディアのもつ説得力の凄さも改めて実感した。
(なにせこれだけの量で説明されることを場合によっては1カットでズバッと視聴者に伝えているわけだ・・・)
そして描写が省略されている、といわれる根拠となるような部分が存在するのは確かなのだが、映像版から入った自分としては「え、結局この程度の省略?」という感じで、事前情報から想像するような深い深い描写がされていたわけでもない。もちろんタクヤやミコットたちとの関係性など大きく違う部分もあるんだが、そういったところに関しての省略・改変も、作品の根幹テーマはなにか?ということを考えた上でばっさり・すっぱり変えてあるので、むしろ過剰だったかもしれないディティールを刈りこんで簡潔にしている印象すらある。
つまりは、映像版の監督である古橋氏がインタビューで仰られていたように、映像の間にあるものを読み取ることで十分補える範疇のものだった。
しかしここからが面白いのだが、映像版でもかなり混乱がみられるEP4以降(小説版6巻以降)の内容は、明らかに両者の展開の仕方が異なっている。
よく批判されるように、シャンブロを駆るロニとのエピソードがだいぶ削られていたんだな、というのはよく分かったし、くわえてその舞台を西アフリカ・ダカールからオーストラリア・トリントン基地のほうに寄せたことで、ダカールにある連邦政府議会でのラプラスの箱への伏線がひとつ省略されてしまっている。また、そうまでして1巻に詰め込んだもう一つのエピソード―ジオン残党の決起―というエピソードは実は端折ってもよかったんじゃないか、という印象すらある。
なので技術・ストーリー的によくまとめたなと思う反面、EP4はロニのエピソードで1巻使ってもよかったんじゃないか、というのは強く感じた。
ただ、このロニのエピソードは非常にデリケートな宗教問題に絡む描写があるので、ある意味そこに予防線を張る+販促の意味でジオン残党のエピソードはずせなかった、ということから意図的にこういう混乱した構成にしたということかもしれない。
そして実はこの6巻目以降、というのはたしかに端折られていたり、時系列がかなり違ったりするのだが―個人的には映像版のほうが出来がいいように思う。
もちろんこれは自分が映像版のほうを先にみているから、ということもあるかと思うのだが、なによりそのスピード感が違う。逆にいうと、それぐらいこの小説版は丁寧にエピソードを展開しているともいえるし、そういった先に存在していた膨大なリソースを使って、そのいいとこどりをしたのが映像版と言えなくもないので、このあたりを比べることはフェアでないのだが。
そういったことを前提の上でいうと、この小説版の終盤―特に宇宙に上がって以降は、ちょっとその規模を広げ過ぎた結果、冗長に感じる部分が出てしまった印象。ここでいう規模というのは、エピソード的にというわけでなくて話中での作戦規模についてだ。
どれぐらい違うかというと、映像版でいくなら「ラプラス”紛争”」で収まるがこの小説版だと「ラプラス”戦争”」―それぐらい違いがあると思う。
これは福井氏の得意分野である国防論的なトピックを、作中ジオン共和国の”風の会”という三島由紀夫の盾の会を彷彿とさせる組織に仮託して入れてみたり、フルアーマー化したユニコーンが敵艦隊とがっつり戦ったり、という描写の結果かと思うのだが、この部分、描写としてだけ見るなら面白いが、作品のテーマを描く上でほんとうに必要なエピソードだったのか?という感は否めない。
ただ、宇宙世紀という仮想の世界を舞台を使って現状の日本の置かれている状況やアメリカとの関係を仮託してみせたのは、流石だし思わずニヤッとしたのも確か。
こういった描写は、実は上記”風の会”のエピソードに限らず、全体を通してところどころに見てとれるのだが、要はこういったある種デリケートな要素をそういう断片的な見せ方に留めておくことを辛抱できず、それを押し出して1エピソードやっちゃったのが冗長さを招いたといえるか。
またこれも意外だったんだけれども、作中アルベルトのウェイトが非常に重く、実はそのせいで映像版ほどリディに存在感がない。
原作との比較でよく指摘されることの一つが「リディの描写が映像版はカットされまくり」ということだったんだが、むしろリディはそれによって大きく得をしたキャラクターのような気がする。なにしろ映像版の終盤では彼は間違いなく”白い一角獣”と対をなす”黒い獅子”としての存在感をもってもう一人の主人公とすらなっていた。それに対しこの小説版は、彼に関する描写が丁寧な分、むしろ”群衆の中の一人”的な印象があり、映像版のような強烈な印象が薄い。
むしろ「カットされまくり」ということでいえば、アルベルトのほうだろう。
そのへたれぶりと言い、それ故のその終盤の行動力と言い、この小説版のアルベルトのいい意味での情けなさ・けなげな努力は、映像版ではリディに全部統合されている感がある。
しかし―この小説版での彼の魅力を認めた上で―アルベルトばっさりカット、というのは、実はかしこい選択だったのかもしれない。ここをあまり頑張らなかったおかげで、主人公・バナージの背景がニュートラルに近づいたというか、ありがちな血統主義や骨肉の争いという小さな物語へ落とし込まれることを結果的に予防した。このあたりは怪我の功名のように思う。
そしてへたれと言えば、実はこの小説版最大のへたれはジンネマンである。
これは本来の彼の境遇を考えると非常に納得のいく話であるし、実際彼のようなキャラクターがいたとすれば納得の描写なのだが、そのぶん映像版のようなカタルシスは薄い。そのキャラクターに託された本質の部分は変わらないとはいえ、彼も映像化によって大きく得をしたキャラクターの一人だろう。
最後は作中最大の敵―フルフロンタル。
実はここがいちばん大きく違っているところかもしれない。
これは気になる方はこの小説版を読んでみてほしいが、小説、という媒体を考えると、こういったキャラクター造形になったというのは、ある意味納得だ。映像版と表面的に似てはいても本質的にまったく異なる。
では、なぜここがこうまで変わったのか?
それはもう、このキャラクターが池田秀一という声を得た―その一点に尽きるだろう。
作中でのその無機質な―ある種昆虫のような―マイナスの感情をチップに焼き付けたようなキャラクターが、その声を得たことによってマイナスからプラスへその存在感を大きく変えた―相転移したといってもいい。
これが本作品の本来持っていたテーマ性の部分に非常にうまくマッチした―ここもやはりこの作品のもつ”運の良さ”のようなものを感じる。
一節によると、著者の福井氏に対して池田氏が「これじゃあ終われないな」とラストに対してのリクエストを出したこと、そして映像版の古橋監督がフロンタルに対して単なる敵役ではなく、彼にも父性の一面を持たせたこと―これによって物語のクライマックスとしての深みが大きく異なった。
これもある意味小説版で繰り返し描かれた”人々の善意”―それを信じて前に進むこと―が作品自体でも発現していたようでなんとなく感慨深い。
―これ以降の部分はある意味深く触れなくてもよいだろう。
映像版でのクライマックスでもあったあのシーンは、(この小説版に準拠した)一部作画の準備にまで入っていた別案もあったそうだが、結局いまのモノに落ち着いたという話だし、よく指摘されるように『イデオン』からの影響を感じさせる”虹の彼方”の描写といい、このあたりは映像版と同じくぼかしておくのが華かと思う―なぜなら、ここは本作の話の根幹のようでいて実はそうではないような気がするから。
そう―実は本作のキモは、ニュータイプやサイコフレーム、はてはモビルスーツといったガジェットにあるのではなく―人と人の間で生きていくということ、社会の中でどう生きていくかという、当たり前の、しかし根源的なことを読者に問いかけようとしている作品のように思う。
もちろんこういった表現媒体故の甘さや、絵空事的なところもあるにはあるが、その部分部分で伝わってくる作者の気持ちというのは、自分は嫌いではないし、大切なことを伝えようとしていると思う。
(その内容自体は議論の余地はあるとしても)
こういうエンターテイメント小説の皮をかぶっていても、時折ずばっとそういった本質で切り込んでくる部分がある、というのは作品の送り手としての真摯さの現れではないだろうか。
そしてそういう”熱”を込められた作品は、決して悪い作品ではない。
少なくともそういうこめられた真摯さに目をつぶり、自分の言いたいことだけをピーチクパーチクさえずっているよりははるかに上等ではないか、と自分は思う。
映像版を先に見ておいたおかげで、画づらも浮かびやすく、最後まで非常に楽しく読めた作品だった。
角川書店(角川グループパブリッシング)





![機動戦士ガンダムUC FILM&LIVE the FINAL“A mon seul desir” [Blu-ray]](https://www.thx-design.net/blog/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/21.jpg)
