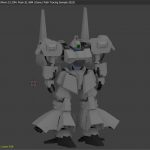最初は史料を元にした新説の一冊かな、と思って購入したが小説。その時点で「あ、こりゃはずしたかも」と思ったらさにあらず。
たぶん信長や秀吉、光秀を追っかけるなら必ず出てくるいわゆる”金ヶ崎の退き口”を新規な切り口で描いた非常に面白い一冊だった。
毎日新聞社
売り上げランキング: 70,234
京に入り足利将軍を擁したとはいえ、いまだ天下布武の道半ばにある信長は、京の目の上のたんこぶとも言える越前・朝倉勢を攻めようとする。しかしその攻略の必須条件は北近江・浅井勢の同調―それがないと北上する軍勢の横っぱらを浅井が突くことになるからだ。いまだ武勲はないがその交渉力で対浅井の調略を行っていた秀吉、味方でありつつも信長を疎ましく思い暗躍する足利将軍の名代・光秀、そして織田の最大の同盟の盟主とも言える家康―信長の「浅井は敵対せぬ」との観に背き、彼らの側面を浅井勢が襲う。その報を受けて信長は全ての兵を捨て、単騎京へと脱出する。結果、後に天下を順に治めることになる三者は残された寡兵をもって襲い掛かる浅井・朝倉勢相手の壮絶な撤退戦を開始した―。
この有名な「金ヶ崎の退き口」は秀吉、家康の話は良く出てくるんだが、光秀を絡めてくれるかどうかはけっこうまちまち。なので本作のように4名の名が表題にまででているというのは待ってました!という感じだったので読んでみた。
最初、冒頭にも書いたように著者の自説を開陳した一冊かと思ったら小説だった、というのはあったが、読んでみるとすこぶる自分の好みに近い雰囲気があって凄く楽しめた。
本作はその最初から最後まで、ある種織田軍団の傍観者でもある家康の視点から書かれている。
その家康も後年のイメージから受ける人の出来た柔らかい印象ではなく、当時の年齢らしい青年将校ぽさが残り、ここはすごくいい人選だと思った。この家康がいわば読者への視点の提供者となるので、その場の状況を非常に俯瞰できる感じがある。
そしてその家康視点から語られる秀吉は、交渉力は抜群だが、侍というものがどういうもかわかっていない惰弱な、けれどどこか憎めないキャラクターとして描かれ、もう一方の光秀は、たたき上げの軍人的な側面はもちつつも、やはり素性の知れない胡散臭さとアクの強さをもった老齢を迎えた実力派武将として描かれている。
このあたり、多くの作品で描かれる二人の人物像とやや色合いが変わっていてすごく新鮮だった。
とくに光秀のそれというのは―物語の必然性からかなり高齢気味に描かれている点を除き―案外実像に近いところもあるんじゃないか、とすら思える。彼に対するこういう造形はきわめてまれだろう。
そして信長である。
ここはある種予想通りの面もありつつも、物語のクライマックスのほうであっ!?という感じのキャラクター描写があったりする。
人によってはこのあたりの描写を嫌う人はいるかもしれないが、自分的にはそこまでに描かれている信長像から、なんか妙にマッチした感じがあって、すごく楽しく読めた。
総じてこの「金ヶ崎の退き口」は絵になるシーンのはずなんだが、意外とみっちり描写されている作品は少なかったりする。
そこをけっこうアクションシーンなども交え、読者を飽きさせずに最後まで読ませるなど、かなりいい意味でのエンターテイメント色も兼ね備えた一作である。
また上記のように四名それぞれのキャラクターが、全員が全員既存のキャラクターイメージをいい意味でくつがえす人物造形がされていて、かつ、それまでのオーソドックスな人物像の中にも収まるという絶妙のさじ加減―ここがすごく新鮮で楽しめた。
作品の雰囲気としては、『のぼうの城』よりはもう少しシリアス度と描写の密度がある、といった感じか。
この著者の方は知らなかったんだが、ちょっと他の作品も読んでみたい、そう思わせる佳作だった。
この4名のうちいずれかに興味のある方は読んでみても損はないと思う。
ちょっとしためっけもんでした!