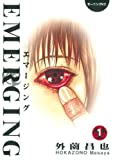今年は国内のデング熱騒ぎといい、いまだ油断できないエボラ出血熱といい、けっこう深刻な事態につながりかねない感染症の流行が相次いでいるので、ふと数年前のこの作品のことを思い出して改めて読んでみた。
『エマージング(1)』
『エマージング(2)』
読む人によってはかなり恐怖を感じる描写が多数あると思う作品なので、読んでみようと思う方はご留意のほどを。
本作品は掲載誌だった週刊モーニングをずっと購読していた関係で、連載時にリアルタイムで読んでいた。改めて発表年を調べてみると2004~5年ごろの作品らしく、ほぼ十年ほど前の作品となる。
しかし作品の基本的なところは全く古くなっておらず、むしろこういった感染症の流行のあったいまだからこそ、その恐怖はさらに倍増する感じだ。
おそらく当時の企画の原点は、そのさらに十年ほど前に発表されている映画『アウトブレイク』、引いてはある意味その原作とも言える『ホット・ゾーン』あたりにあるのは間違いないだろう。
それらで描かれているような状況がもし日本国内で発生したとしたら―本作品は、その際に起き得るであろうことの骨子をはずさないように留意しながら、表現媒体であるコミック故のキャラクター造形などの強みを生かして、読み手にいろいろと考えさせる一作である。
作中でも触れられているが、もしこのレベルの感染症のパンデミックが発生した場合、どこでどうやって防ぐのか(防ぎようがあるのか)、発祥した人たちをどう扱うのか、また決め手となる臨床的な研究設備が住民の反対で稼働できない可能性があるのでは、というかなりハードなシナリオで展開する。
(※いまざっと調べてみた感じでも国内のP4=BSL-4施設はあるにはあるが、やはり住民の反対でBSL-3相当での稼働しかしていないような記載が出るなあ・・・まあ当然ではあるんだが)
ただ当時はあまりそういったシリアスさが受け入れられなかったせいか、はたまたある意味”真面目”にシミュレーションしようとし過ぎたのか、印象としてはこの1、2巻の内容だけでほぼ打ち切りに近いような印象で終わったように記憶している。正直これが良かったのか悪かったのか微妙なところだ。
もっと連載が続いていれば、読者にはある程度こういった事象の際に発生するであろう多様なシチュエーションに対するシミュレートはできたかと思うし、なにより作中の状況を現実の我が事として置き換えてある程度の基本的な知識の蓄積もできただろう。
反面、作中の描写はかなりキツイ描写があったりするので、そこだけに目が行って恐怖感だけを印象として残してしまった場合、今回のような状況の報道があった場合、嫌な形の短絡的なパニックの下地を作ることになっていたかもしれない。
そういうことを考えると、一応のハッピーエンドに近い形でこの分量で終えておいたというのは、案外最良の選択だったのかもしれない。
まあ逆に言うと、それだけの取材をして描かれた力作だったと言えるだろう。
で、自分も今回ちょっとその根幹となる「ウィルス」という概念をすこしだけwikiとかで読み直してみたんだけど、わけわからんよねえ、ウィルスっちゅう存在は(笑)。
単独では自己複製能力がなく、限りなく無機物に近く(一節によると有機物との境目だとか)しかし宿主に入り込んで自己増殖する機能を備えている。
本作中でも出てきた描写だが、だから”殺す”っていう概念が細菌と違って成り立たないのよね。
なんかほんと設定だけ見ればSF小説に出てきそうなナノマシン生物兵器みたいなwこういうすこぶるシンプルな構造物が複雑な生物種に対して甚大な被害を及ぼす、という意味ではそれもあながちうがった見方ではないよな、と思っても見たり。
また以前なにかの本でも読んだが、ウィルスというのは子孫を増やすという生殖活動による”縦”の遺伝子の伝播に対して、同種族の水平個体間やさらには異種族間の個体の間という”横”に遺伝子を運ぶある種のシステムなのではないか?というのがあったが、それも言われてみればうなずかざるを得ないところもあったり。
なんにせよ、複雑な生理的構造や意識や知能といったややこしいものを持っていても、人間もまたひとつの生物機械・・・ということなのかもしれんな。
とりあえずこの機会に読み直してみて、上のようなことをいろいろと考えたので敢えて記事にしてみた次第。毎日電車通勤している人は読まない方がいいかもね、人によっては気分悪くなると思う。
ただ、この機会にある程度自身でシミュレーションしておきたい、という人は目を通しておいてもよいかもしれない。各自自己責任で。