前回の凱旋コンサートがあまりな出来だったので行くか迷ってたコンサートだが、チケットがとれなさ過ぎてムカついて逆に意地になって取ってしまったので行ってきました@池袋・東京芸術劇場。
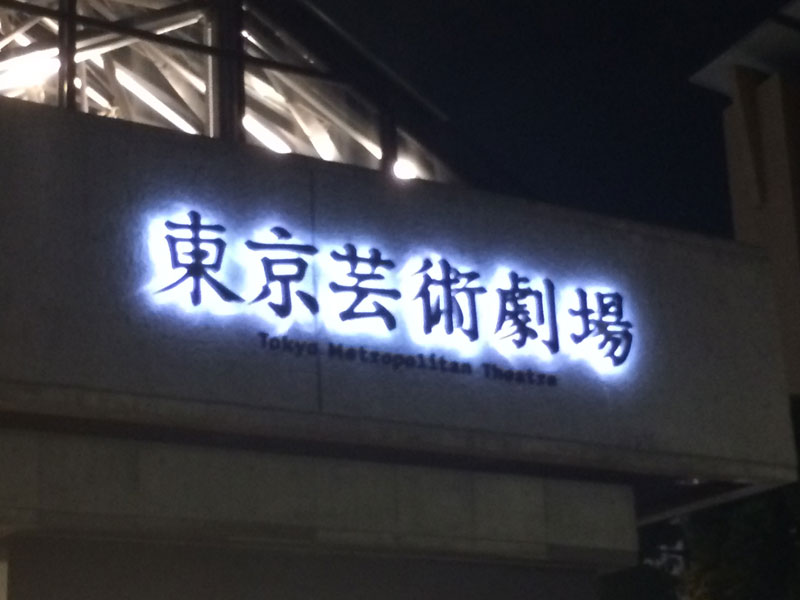
結果、前回の演奏とは比べものにならない良いコンサートだった。やはりオーケストラというのは生モノだわ。
前述のようにチケット取るときに「まあ当たれば観に行くか」ぐらいに思っていたんだが―音響S席?的な席狙ったせいか―外れてばかり。ほんでムカついて意地になってチケット探してると、最後の一般販売の時に一般席で3階席とはいえセンター近くの席が偶然とれそうだったのでぽちっとな。例によって店頭での引き換えという罰ゲームを経て(泣)行ってまいりました。
初回に名古屋でみた時は1階席、前回の凱旋公演は2階席、そして今回は3階席ということで、結果、ひととおりの席種を経験することになって、これはこれで怪我の功名だったかも。
そして前回と同じ池袋・東京芸術劇場だったわけだが、今回なんと場内にバーカウンターみたいなものがあること発見、わーいw
のど渇いてたこともあって白ワインひっかけて気分よく席に向かう。
(で、これがあとで裏目に出たわけですが)
3階席になると当然かなりの高さ。残念ながら目のあまり良くない自分では、ステージの詳細見分けられない感じの距離。まあ今回は前回との音の面で比較できればよいかと思っていたので、ここは目をつぶる。
今回の構成は演奏される曲の内容から、chelestaが入っていてその存在感を主張していた。生で聴くのは初めてだったがいい音だったな。同じくアコーディオンも入っていて、これもいい感じ。
実は前回あんなに酷評した東京室内管弦楽団であるにも関わらず行ってみようかと思った理由の一つに
「叛逆の曲調なら意外とこういった構成にいちばん合うのかもしれない」
という読みのようなものがあって。
これはご存知の方ならお分かりと思うが、本作品のサウンドトラックはどちらかというと”静”の印象の強い曲調が多い。なのでダイナミクス的な意味での破綻が少ないだろうということが一点。また公演予定を見るに同じ楽団で先に大阪で公演済み、加えて東京公演も同日昼夜の二公演、なら演奏上のリカバリは十分やってくるだろうと踏んだわけで―結果この読みは大当たりで、今回は前回がウソのような良いパフォーマンスだった。
唯一難点を挙げるとするとすれば、やはりいくつかの曲で演奏が走っているように聴こえてしまうことがあること。
ただこの点、あまり気にならず、ピアノやフルートなどのソロ的なパートのある楽曲でも、前回と違って落ち着いた感じで弾いてくれていたので、十分満足できる内容だった。
そういうステージ側が良い演奏をしてくれていたわけだが、ここで残念な結果が現われたのが「3階席」であるということ。
違うんですわ、明らかにその音圧が(泣)。明らかに薄いの(泣)。
もうなんちゅうかあちらを立てればこちらが立たず、帯に短し襷に長しと申しましょうか―オーケストラというのはやはり生モノなんだなあ、というのを強く実感。
しかし、今回こういう経験をしたことで、どういう席がどういう意味合いを持つのか?というニュアンスのようなものと、変則構成とはいえ、生オーケストラというものの判断基準のようなものが、ようやく自分の中で最低限確立されたような気がする。
ということで今回はなかなか自分的には、悲喜こもごもな感じの回でした(泣笑)。
加えて、前述のワイン引っかけたことも災いしたのか、はたまたここ数日の睡眠サイクルのせいか―本編演奏中、睡魔さんが襲ってくる襲ってくる(泣)。
これは逆に言うと、静かな曲調で安心して聴かせてくれるレベルの演奏だったからというのもあると思うが、がっつり聴きたいなと思っていた自分涙目ですよ。
前回悪いこと書いた罰があたったのかもしれません。
ということで、できればもう一回ぐらいベストな席とベストなコンディションで聴いてみたいものですが、はてさて。
ちなみにこのあと予定されている北海道公演では、今回の新編分に加え、前回の映画版前後篇分を合わせて昼夜公演やるとのお話がMCで出ていた。
さすがに北海道まで遠征する予算も気力もないが、再度全曲生で聴いてみたいという方には朗報だろう。
(指揮者の方の仰ってたように演奏する側からすれば、曲数的に地獄だろうが:苦笑)
再度凱旋公演的なものがあるのなら―今回のレベルでやってくれるのであれば是非もう一度行ってみたい―そう思える良いパフォーマンスでした。
追記:
今回司会は杏子役の野中さんであったが、2部構成のステージのそれぞれ冒頭と一部に劇中のセリフの朗読あり。まあこれは楽しみにされている方がいるだろう演出なので、このまま続けてもらう形でもいんじゃないかな。
で、もうすっかりこの東京芸術劇場では映像的な演出はなくなってるが、これはすごくいいことだと思う。
ライティングでの演出等は見られたが、これだけしっかりした作りのコンサートホールなので、音をじっくり楽しむ構成としたのは英断だろう。また本作品のスコアは全曲それに耐えられるだけのクオリティを持っていることは間違いない。
あとは可能であれば、メンバーをなるべく固定して、演者側のそれぞれが曲に対する、それぞれの追求を高めていってもらえたならいうことなしなのだが。
こういった比較的敷居の低い、サブカルチャー的なコンテンツをベースにしたコンサートで、ハイクオリティな演奏を維持して頂くことが、結果こういったオーケストラ界隈の人口というか、層の厚さを創っていくことになると思う。
それってすごくWin―Winの関係じゃないかと自分などは思うのだが、いかがだろうか?

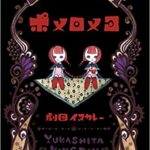

![【レビュー】『魔法少女まどか☆マギカ[魔獣編] 1巻』ハノカゲ](https://www.thx-design.net/blog/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/25.jpg)
