さて、今年も年末恒例の悪あがき(苦笑)、今年印象に残ったメディア作品の個人的まとめ。
いつも年の瀬押し迫ってから書いてるので、切羽詰まった中の耐久レースのような有様でドMなことこの上ないが(苦笑)、まあせっかくなので続けられるところまで続けてみましょう─ということで興味の湧いたお時間のあるそこのあなた、気になったところだけポチっとする感じで一つお付き合いいただけるとこれ幸い。
※以下Amazonのアフィリエイトを一部使って作品を紹介しているので嫌な人はご留意を(引用の書影はその作品「らしい」モノを選んでいる)。
■コミック作品
例によって乱読であるが、数を読んだからこそ分かるのは我が国におけるこの分野の圧倒的な層の厚さ。気楽に読めることが多いのでいわゆる「なろう系」的なファンタジーものも読むことが多いのだが、それすらもいまはけっこう骨太な作品が出てきている─「異世界転生ファンタジー」という”看板”をかけておくことで逆にそれぞれのテーマにのびのびと挑めているのではないか、という印象だ。それもこういう圧倒的な層の厚さ故の産物、というのは海外でのアニメ・コミック文化での存在感の著しい伸長からも見て取れる。我々はそういう恵まれた文化の果実を享受できる時代に生きている、というのは幸せなことだと思う。
『薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解き手帳~(サンデーGXコミックス)』

薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解き手帳~(サンデーGXコミックス)
今期秋シーズンのアニメ化でも話題になっている一作。以前試読で読んでいてチェックはしていたんだけども、このアニメ化のタイミングのセールで”サンデー版”を。
そう、この作品珍しくコミカライズが複数の出版社から同時に出ているという珍しいケースで(以前の『まおゆう』以来か?)スクエアと小学館からそれぞれ刊行されている。試読で読んでいたのはスクエア版だったのだが、今回まとめ買いするに当たって単純に「出ている冊数がこちらのほうが多い」という理由で小学館版を選んでみたのだが、個人的にはこれで正解だった。
どうもこの小学館版のほうが少し大人な雰囲気というか、描線がカチッとしていてギャグ要素なども抑え目、謎解き描写の方に力を入れている感じ。コミカライズ担当の方がある程度キャリアがあり、かつ中華系の作品もこれまで出されていた漫画家さんのようで、そのあたりも両者の違いに大いに繋がっているようだ(例の作中の書き文字描写が日本語か漢語かでもこちらはちゃんと漢語であった)。
ただ前述のアニメ化に関してはスクエア版ベースのようで、より”マンガ的”なのだが、分かりやすいぶんかなり好評のようだ。
ストーリーとしては”架空中華王朝の後宮もの”という女性向けファンタジーの定番。その舞台で薬学・医学をベースにしたミステリもの、という感じ。ただやはり話題作だけあってキャラクターの立ち具合やそれぞれの配置はうまく出来ていて、ちょっと冷めている感じの主人公・猫猫(マオマオ)がよい。ストーリーも各話の小さなエピソードが大きく朝廷まわりの存亡に関わるようなより大きなストーリーへと繋がっているのもうまい。最新巻ではその大きなストーリーのほうでかなり大きく動きそうな描写も出ているので次巻が待ち遠しいところ。
『ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~』

いわゆる「架空中華王朝の後宮もの」を未読の方がいるなら、最初の一作にはこれを強くおすすめする─『薬屋のひとりごと』の次に来るのはまず間違いなくこの作品だと言ってもいい作品だ。現時点では既刊の巻数が少ないこともあり『薬屋~』より舞台がコンパクトな感じもあるが、その分わかりやすく、なにより主人公の”キャラの強さ”が凄い。なんで病弱なはずのヒロイン玲琳をしてファンから「鋼(はがね)さま」と呼ばれるのか─是非一読してその目でしかと確かめていただきたい(笑)。
ストーリーとしては「心身入れ替わり」の方術で入れ替わった二人の雛宮(皇太子の後宮)の姫─玲琳と彗月が、対立しつつも結果的により大きな悪意を暴いていくことになる、という感じなのだが、この作品のいいところは『薬屋~』が王道の男女のロマンスを一応軸としているのに対し、こちらは二人の姫たちの「友情」をベースとしているところ。(当初は彗月が玲琳を妬み陥れるために入れ替わったのだが─あまり書くとネタバレになるので)
昨今、ヘンに同性愛的なもの(BLや百合)に市民権が与えられてしまったせいか、同性二人組の場合、すぐにカップリングというか性的な妄想の対象とされてしまうが、この作品のそれは単純にこの年頃ならではの同性の友人に対する友情であり純粋な憧れ、ということで良いと思う(4巻までの第一幕に相当する部分の大きな背景も実はその構造で韻を踏んでおりそこも美しい)。なんでもカップリングへ堕す汚れた大人の皆さんは猛省してほしい(プンスカ)。既刊は5巻までだが上述のように4巻までで1エピソードがきれいに収まっているので、まずそこを一区切りとして読んでみることをおすすめする。アニメ化するならまず間違いなくこの区切りで行けるはず。なにより落ち込んでいたりするときにこの”鋼(はがね)さま”の言動には元気をもらえる(笑)。泣いて・笑って・スカっとできる─かなりおすすめの一作である。
※とか書いてる最中に最新刊6巻が出たw全巻から登場のお兄ちゃんズも美形なのにぶっ飛んでていいキャラしてる
『悪役令嬢の中の人~断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします~』

悪役令嬢の中の人~断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします~
”女性同士の友情”ということでいえばこれもまさにそれ。作品としては「異世界転生もの」に間違いなくカテゴライズされるのだが、本作はその部分にかなりひねりの加えられた作品で、異世界転生で体を共有した二人が”表の人格”となっていた転生者のために”復讐”(という名の”救世”)をしていく、という作品。
とはいえ話の本筋に入ってからは比較的シンプルで、本来悪役令嬢となるべきはずであった主人公・レミリアが自分を唯一人大切にしてくれた転生者・エミの名誉を守るために世界を救っていく─ただただ彼女の名誉のために・・・という物語。そしてタイトルに有るように、もう一人の転生者として敵対する嘘つき聖女(星の乙女)が出てくるが、このキャラクターのいかにもな憎々しさも良い(苦笑)。それだけに本来悪役令嬢であったはずの主人公・レミリアの孤高の気高さ・美しさ─それ故の真のヒロインとも言えるエミへの友情の美しさが際立つ。また『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』でもそうだったが、本作も主人公が徹底して強いというのもスカッとして良い。またイケメンの魔王様も出てきて彼女と共闘するが、魔族もまた元は人間だったという設定がきちっと描かれているのは比較的珍しいのではないか(設定自体はよく見られるのだが)。そして本作のもう一つの魅力─特にこのコミック版ならではのそれ─は、出てくる神々のデザイン。非常に幾何学的というか一つ間違えればデモーニッシュというか、どこか「まどマギ」における劇団イヌカレー的なセンスの良さを感じる。一見あらすじや設定だけを見ればありがちな作品のように思われる本作だが、個性的な各要素が他の要素と相乗効果となって、非常に独特な色を持った作品となっている。なにげにお気に入りの一作。
『甘い生活』
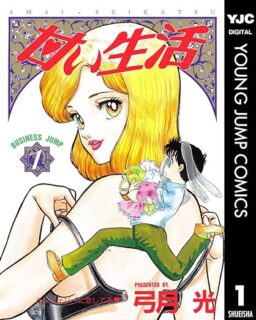
『甘い生活』
確か自分が学生の頃から連載されている作品で、集英社の『ビジネス・ジャンプ』(BJ)誌の看板作品の一つだったはず。それだけに既刊数が膨大で読むのためらっていたんだが、例によってセールの際に購入。けどまだ完結してないのよね、コレ・・・(苦笑)。
天才下着デザイナー・江戸伸介はその下着への愛から触れた女性を昇天させる「神の手」の持ち主だが、女性そのものには興味がなくむしろ奥手で、彼に惹かれていくヒロイン・若宮弓香はいつも気が気でない・・・という感じのエロチック・コメディ作品。とはいえ、著者の弓月光先生は女性誌がデビューということもあってかいい意味で硬質な描線で、肌色成分の多い作品だが、必要以上にいやらしい感じはしない。それよりも本作で驚くのは御年74歳の弓月先生の時勢というか社会の変化へのさりげないキャッチアップ能力の凄さと、それをあまり古臭く感じさせない筆力の凄さだろう。本作にはヒロイン・弓香と凸凹コンビともいえる河野美也というキャラがいるんだが、彼女まわりがハッカーやオタク的な描写になっており、そのマンガ的な荒唐無稽さと現実にありそうな部分のミックス具合が実にうまい。また伸介が自身の会社を立ち上げていく後半では女性のことを考えた福利厚生や食堂の重要性など、マンガならではのファンタジー的な要素はありつつも、現実社会でも後追いで最近になってようやく「あたりまえ」扱いされているようなことを数年先行して描写していたであろう所には恐れ入る。そして基本的にコメディなので気楽に読めるのだが、実はこの巻数を積み重ねてきたからこそ成立するキャラクターたちへのシンパシーがあってこそのクライマックスシーンの感動があった。それは第一部のクライマックスともいえる新会社立ち上げのファンションショーでのランウェイでのフィナーレ・・・正直広義のエロコメ作品でこれだけボロ泣きさせられるとは思わんかった(苦笑)、こんな可愛らしいヒロインおらんやろ─またやんちゃキャラである美也の涙もいい(泣)。伊達にウン十年連載し続けているわけではない、というのを思い知らされたエピソードであった。
弓月先生は少女誌出身、と書いたが、実はこういう出自の男性作家の方は息の長い作家さんが多いのだなあ、というのは改めて思ったが、なにか秘密があるのだろうか?魔夜峰央先生もパタリロ描き続けてらっしゃるし、数年前に筆を折られたと聞いているが柴田昌弘先生も非常に多作な方だったという印象。
なにはともあれチャンスが有れば一読に値する作品だといえる。ただその際に表面的な描写に惑わされない理性は必要とされるだろうけども(苦笑)。
『イノサン/イノサン Rouge』(完結)

イノサン/イノサン Rouge(ルージュ)
フランス革命前後に実在した処刑人の家系に生まれたシャルル・アンリ・サンソンとその異母妹マリー=ジョセフを主人公とした力作。この坂本眞一という方の執拗な描き込みは時々目にすることはあったが、こうやってあらためてまとめて読んでみるとその狂気というか熱量に当てられっぱなしである。絵柄からも想像がつくように耽美でゴスで不道徳で─そして圧倒的に”美しい”物語だが、こういうものを生み出すには作家の側にある種の狂気がなければなし得なかったであろう奇跡のような作品だ。
そしてゴスや耽美と書いたが本作は圧倒的に”自由”への希求の物語でもある。それは作中におけるメタ的な描写─悲劇の女王・マリー・アントワネットの幼さをあえて表現するために現代風のSNS的な描写を取り入れたり、学生モノのフォーマットを敢えて使ってみたりと非常に挑戦的なところからも見て取れる。このあたりは連発されると陳腐になるのだが、そこも本作はちゃんとその描写に対する演出上の必然性を忘れていないため作品の価値を損なわず効果を上げている。そして分量的にも抑制的に使っているのでこういった”飛び道具”ならではのインパクトをむしろ高めている。
物語としては内向的な兄のアンリと奔放な妹マリーが、それぞれなりのやり方で呪われた家業と斜陽のルイ・フランス王朝を覆う重苦しい現実という”不自由”に抗い、もがき苦しみ、けど諦めずに戦う、という意外なほど真っ当な物語だ。
ただ処刑人という職業柄、拷問やむごたらしい人体損壊などの描写も当然あるので、この耽美な絵柄と相まって、読む人をかなり選ぶ作品でもあると思う。
しかしこんなある意味命削って描いている作品を数百円から~全部揃えても数千円・一万円ちょっとで読むことができるという日本という国は、つくづくいい意味で狂ってると思うなあ(苦笑)。
万人にはおすすめできないが、手にした方にはその感想がポジティブであれネガティブであれ─なにがしらかのエネルギーを注がれること間違いない劇薬のような作品だ。
※ちなみに当然フィクション作品ではあるので創作された部分が多々あるが、マリー=ジョセフはかなり膨らませているようだ─たしかにこんな魅力的なキャラクター出来てしまったなら、キャラのほうが勝手に”自分”を強く主張してくれるだろう(苦笑)
『チ。―地球の運動について―』(完結)
国名や場所をいちおう伏せてあるようだが、15世紀のヨーロッパにおける地動説を証明しようとした人々と、それを追い続ける処刑人の長い長い物語。もちろんフィクションではあるので、史実をなぞるとかそういうことではないようだが、ポーランド周りが舞台のようだ。
長い長い物語─と書いたが、これはエピソードごとでメインとなる人物が入れ替わったり殺され(処刑され)たりするためで、彼らによって受け継がれ続けた「本当はこの大地が太陽の周りを回っているのではないか?」という素朴な疑問とその観察結果がリレーのバトンのように受け継がれてゆき、それはついにたどり着くべき場所へ到達する。
いまでこそ当たり前の地動説だが、本作のような中世─特に教会がその世界観をつくり、その峻厳たる守護者であった世界では、その疑問を抱くことさえも重大な罪であったということがヒシヒシと伝わってくる─文字通り”命がけ”の疑問であり、思考だったというわけだ。
しかし人間の持つ思考や好奇心・探究心というものは結局なにを持ってしても・誰を持ってして求められない。それは科学というものの持つある意味負の側面でもあるのだが、人が知恵の実を喰らって生まれてきた生き物である以上、我々にできるのはそれを認め、それとうまく付き合っていく・認めた上でコントロールしていくことしか出来ないのだろうといういうことも、逆説的に考えさせてくれる作品であった。
『正反対な君と僕』/『氷の城壁』
ご覧のように「ジャンプ」ブランド=少年マンガというくくりに一応なると思うのだが、これ一昔前ならメインストリームの少女マンガ作品よなあ。2作品同時に紹介のような形となったが、両方とも作中の雰囲気は同一=おなじ作者なので当然なのだが、その主人公の性格付けが「外交的」か「内向的」かで、両者がいいコントラストになっている。
そのうえで、いまどきの高校生のディティールでありながら、いつの時代でも普遍的なこの年頃の若者たちならではの切ない悩みやら胸のときめきをビビッドに描いている。しかしどちらの作品も阿賀沢紅茶、という著者ならではの独特の「軽やかさ」(「軽さ」ではない)があって、非常に気持ちよく読める。
絵柄─というかギャグのときの崩し方が少しクセはあるので、人によっては苦手な方もいるかもしれないが、基本いまどきの高校生の感覚をリアルに感じさせてくれる良作だと思う。個人的にはこの作家さんはいわゆる「信頼できる作家さん」だと、この二作品読んでみて確信した=つまり新作出たら無条件で買っても外す可能性低い才能いうことである、いい人を発見した。
『ニンジャスレイヤー』
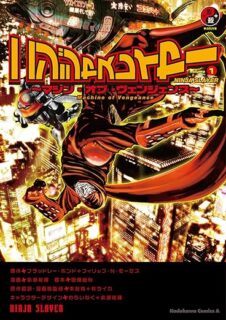
ニンジャスレイヤー
「アイエエエエ! ニンジャ!? ニンジャナンデ!?」
・・・・・非常にメタな作品である。55円だか33円だかのセールの際に購入。
いわゆるハリウッド映画などで時々見られる「トンチキジャップランド」を濃縮還元して果汁100%にしたような作品。テキストベースの外国人による原作がある、という体裁になっているが、これどう考えても作者は日本人だろう(笑)。そうでなければここまで立体的に飛び回るトンチキ日本語で話組み立てられんわ!?もちろん日本語でのベースとなるテキストはあるようでTwitterとかでアップされていたとか(もちろんテキスト作品として書籍化済み)。それをマジンガーシリーズなどのスピンオフ作品などで高評価を得ている 余湖裕輝✕田畑由秋組がコミック化 しており、島本和彦作品とはまた別の意味で暑苦しいことこの上ない!(爆笑)そして困ったことにすんごい面白いのよ!?
余湖✕田畑組ということで、平井和正ファンとしては「こんなもん描いてないではよウルフガイの続き描いてくれ!」と思っていたんだが、これを読んでしまったあとは「・・・これはしゃあない、許すw」となってしまった。
「ハイクを唱えろ!ニセイッキュウ=サン」(ハイク=俳句=辞世の句、ということらしいw)
うん、まあ日本語の「立体機動」をみれるというか、ある意味日本語のもつハイコンテクスト性の極北のような作品ですね・・・「アイエエエエ! 日本語スゲェェェェェ!?」となる作品(違
『大相撲令嬢 ~前世に相撲部だった私が捨て猫王子と はぁどすこいどすこい』(完結)

大相撲令嬢 ~前世に相撲部だった私が捨て猫王子と はぁどすこいどすこい
いわゆる”悪役令嬢”ものの定番として、悪役令嬢に転生した主人公が断罪されるシーンから始まる事が多いが、本作はその断罪シーンにうけた「平手打ち」から前世の記憶=「張り手」を思い出し、聖なる相撲パワーで仇なす敵をこれでもか!と投げ飛ばしていくという横綱相撲的な作品(違)。いやもうこれはほんとセンスと言うか遊び心というか、その発想の自由さが羨ましい!?(爆笑)。
私の頬がなり、痛みが片頬を焼いた。
その瞬間であった。私の心の中に、
【相撲】
という言葉が輝き立ち上がった!(原作小説より引用)
いやいやいや待って!?【相撲】という言葉立ち上がってこないで!?(笑)という感じだが、この説得力のうっちゃりはすごい(違)。そしてこれに限らずとにかくその発想の自由さ・奔放さのぶち抜けぶりが凄い。「清めの塩」は悪霊をも払う「セイクリッド・ソルト」だわ、神秘的な力で土俵が立ち上がってくるわ、軍配を預かる行司が召喚されるわ、懸賞金も召喚され兵士たちの兵糧や軍資金それで賄うわ・・・どういう脳みそ持ってたらここまで突き抜けた発想ができるのか!?正直ちょっと羨ましい(違)。そしてなにげに本作はその自由奔放な原作をマンガ作品としてわかりやすく整理し・落とし込み、ある種の少年マンガ・スポ根マンガ的な熱さえも付け加えたコミカライズ担当・影崎由那氏の力量も特筆しておくべきだろう。
そしてこの手の作品を読んでいつも思うのは、なにかしら一本軸となるジャンル(本作なら相撲)がある場合、そのジャンルへの理解や愛情が深ければ深いほど、作品としての面白さは高まるということだな(もちろんそのための筆力や画力が一定以上であることは必須条件ではあるが)。
バカバカしいほどのめり込んでいるジャンルであればあるほど、そのジャンルはそういったのめり込み=愛情に対して裏切ることはない。
世のパロディやお笑いの大半がそういったことを理解せずに、安易な引用や本歌取りで笑いを取ろうと思っても、見る人が見れば一発でその浅薄さが分かる。本作の無駄に暑苦しい相撲愛(笑)は、そのことを改めて教えてくれるようだ。3冊しかないので、ちょっと面白くてスカッとできる作品が読みたい方には強くおすすめできる一作。
しかし主人公令嬢の照れ隠しが「はあ、どすこい どすこい」、愛が高まると思わず歌ってしまう相撲甚句てwww
是非機会があればご一読を。
『悪食令嬢と狂血公爵 ~その魔物、私が美味しくいただきます!~』

悪食令嬢と狂血公爵 ~その魔物、私が美味しくいただきます!~
魔獣を食べる「悪食令嬢」と噂されていた伯爵令嬢メルフィは、婚約相手を見つけるために望まぬ社交場へと出席していた。そこに突如現れた狂化した魔獣から老夫婦を助けようとしたところを「狂血公爵」と噂されるロジェに窮地を救われる。彼は魔獣の頻出する領地を任されており常に魔獣と戦い続けていた。その彼につい「魔物食」の話をしてしまったことから、二人の間にあれよあれよと婚約話が進んでしまう。理由があって「食」としての魔物を研究していたメルフィと魔獣と戦い続けることで国を守り続けてきたロジェは、互いの孤独を知る者として急速に惹かれていく。
本作は転生云々のない、本格的な王道ファンタジーなのだが、特色としてタイトルになっているように「食」としての魔獣がテーマとなることで独自のカラーを作り上げている。ヒロイン・メルフィの魔物食は、亡き母から受け継いだ研究=厳しい環境の自領・マーシャルレイドの食糧事情を少しでも改善するためのもの。それが敬愛する兄王の障害とならぬよう臣籍降下し、辺境で魔物と戦い続けるロジェに見初められるきっかけとなり、二人はその特殊な立ち位置ゆえに唯一互いを理解できる存在となっていく。
フックとしての「魔物食」というところを抜きにしても、けっこう骨部な感じのある作品で、ロジェは嫁取りにドラゴンに騎乗してやってくるのだが、このドラゴンでの編隊飛行・集団戦などの描写も意外なほどきちっとやっている。最新刊では父のいるマーシャルレイド領を離れロジェの領土であるガルブレイズの城塞都市ミッドレーグへ到着したばかりなので、本格的な戦闘描写などはまだお預けだが、けっこうきっちりやってくれそうだ。メインの魔物食に関しても血抜きと合わせて魔力抜きを行ったり、きちっと魔物をさばくためには良い刃物が必要、ときっちり要点を抑えた描写になっているのもよい。そのうえで実食になるとどんな味がするんだろうとワクワクを止められないメルフィやロジェと気心を通わせている副官・ケイオスのボケツッコミの漫才的描写なども読んでいて楽しい。このようにけっこうギャグ描写の比率も高いのだが、本作のいいところは各話やエピソードの締めの部分できちっとシリアスに・誠実な描写で締めてくれる部分。この硬軟双方のバランスが実に素晴らしい。
以下で紹介する『北欧貴族と猛禽妻の雪国狩り暮らし』もそうだが、こういうポジティブな感じの嫁入り・嫁取りの物語を読んでて「良いなあ」と思うのは、これらがある種「群れの動物としての人間」の物語でもあるからかな、と。こうやって「一族郎党」を作って人は生き延びてきたのだなあ、そういう原始的(プリミティブ)な部分を間接的に感じさせてくれるからかもしれない。けっこう次巻が待ち遠しいタイプの良作。
『北欧貴族と猛禽妻の雪国狩り暮らし』

北欧貴族と猛禽妻の雪国狩り暮らし
ファンタジー系作品かと思って読んでみたら「北欧」とあるように、ある程度実際の土地をベースにした物語の模様。主人公リツハルドの領地の名前からするとスカンジナビア半島あたりの話であろうか。
両親がふらっと失踪してしまったために、その領地を受け継いで領主となってしまったリツハルド。厳しい気候の中での生活にこれまで一緒についてきてくれる女性はいたものの逃げられてしまっていた。そんななか、社交のために出席したパーティで彼は赤髪の凛々しい姿の女軍人・ジークリンデと出会い、その場で求婚する。年齢のことや軍務の将来に展望を見いだせていなかった彼女は「1年間、仮の夫婦として過ごしてみよう」と彼の求婚に対し提案し、二人はリツハルドの領地へと帰還する・・・・・。
こういう開拓地もの、というのはノンフィクションやファンタジー作品でもけっこう色々あるが、ここまでハードモードというか地に足の付いた作品はなかなかないのではないか。主人公のリツはとにかく働き者で、義両親からも「働きすぎ禁止令」を出されるぐらいなのだが(笑)、これはある意味それぐらいマメでないとこの厳しい環境の中では生きていけない、ということでもあるのだろう。そして奥さんになるジークリンデが元軍人というのもある意味納得で、それぐらいの基礎体力と過酷な環境への慣れがないと、こういう生活の中で「すこやかに」生きていくのは難しいからだろう。気候が厳しいのもあるが(作中でも描写があるように)こういう地域は夜が長いのだ。そら心身ともにタフでないとやっていけないだろう。とはいえ、そういうハードモードな環境だからこそわかる自然の恵みの素晴らしさや、そこに生きる人達の強かさ、そしてだからこそ分かる人間関係の大切さ、本作はそれをしっかりと描いている。リツの家系が元々外来の家系ということで土地の人達からはやや距離を置かれていたのだが、新妻ジークリンデが来たことによって、その関係性にも少しづつ変化が起きていく。その変化はとても暖かいもので、読んでいてこちらもほっこりする─これまで孤独が当たり前だったリツハルドの隣にジークリンデが居ることで彼自身の気持ちにもよりポジティブなものが生まれていくのだ。
本作はこういうハードな環境をハードに描くのでなく、その豊かさのほうを中心に描いているのが素晴らしい。なんにせよこういった生活圏に深い造詣がなければこういう作品は書けないだろう。地に足をつけて生きるということはこういうことなんだな、ということを感じさせてくれる良作。都会というシステムに守られて惰眠に生を貪っている自分としては恥じ入るばかりだ・・・。
『魔王と勇者の戦いの裏で』

魔王と勇者の戦いの裏で
ほんと偶然に読んだ作品だったが、個人的には本年一のあたり作品。異世界転生者ではあるが、主人公自身は勇者や英雄でもなんでもなく「その友人(モブ)」に転生、しかし前世の(=ゲームの)知識だけはあるので、やがてこの王都が魔王復活による魔獣の暴走=スタンピードで壊滅することは知っている─死にたくないから今の自分でやれるだけのことをやるしかない、という展開。幸い転生先が貴族の子息だったので金や知識の力を使って自身でできるだけの準備はし、ゲームの主人公たる「勇者」には関わらずにおこうと思ったらまさかの同級生。結果的に彼=マゼルのトラブルを救ったことで懐かれてしまい、こうなれば「毒を食らわば皿まで」と、積極的に彼と関わっていくことに。
とまあこれだけだとどういうところが良いのか分かりづらいかと思うが、まず本作で良かったのはその集団戦の描写。作者男性名だが絵柄を見るにどうも女性じゃないかな?─その描線に独特の「細さ」があるのだが、それが結果的に一部の画面をやや乱雑に見せてしまってる。しかしそれがかえって最前線の「乱戦」の描写に一役買っていて非常に勢いがある。この対スタンピード戦は「本来のゲームなら人類側拠点壊滅イベント」とも言える戦闘なわけで、その「息もつけない」感がすごくよく出ていて、この描写がまず白眉。そして「線の細さ─画面的にやや乱雑」と書いたが、逆にこれが通常の人物描写のシーンではすこぶる美麗で魅力的に映るのだ。特に王族周り─ヒロイン・ラウラ姫や一癖も二癖もありそうな美麗かつ美丈夫な感じの王太子ヒュヴェルトゥスなど、非常に眼福である。また美麗なだけでなく迫力もあるので、この王族周りの描写に自ずと重みが出ているのも良い=シナリオ的にも主人公が政治的な「欲」を持っているのかどうか探りを入れられるあたりでこれが一番活きてくるので、物語世界の厚みを感じさせるのに大いに貢献している。またこれは些細な点になるが、数名出てくる女騎士たちも、お手軽ファンタジーに出てくるような軽装ではなく重甲冑に近いものを装着しているのも良い。にも関わらず美麗さを損なっていないのもさらに良い(笑)。これもこのコミカライズ担当の方の繊細な描線・筆力故だろう。
既刊の3巻分では序盤イベントであるスタンピードをしのぎ切って、その功績で主人公ヴェルナーは「子爵」ではあるが個人としての爵位も得、次の「イベント」であるヴェリーザ砦攻防戦に向けて友人でもある「勇者」マゼルのバックアップに奔走しているところまで。ここまでのスタンピード戦といい、かなり作画カロリー高いシーンだったと思うんだが、「人類側壊滅」という本来のシナリオが変わってしまっている=国軍はある程度の規模で残存しているので、次の攻防戦もひょっとすると大規模戦になるのだろうか?ただ主人公ヴェルナーはマゼルの積極的介入を遠ざけるように動いているので、このあたりはどうなってくるのか楽しみだ。
『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』

最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。
世にあるフィクション─物語というのは、ある種の類型をたどるのが世の常だと思うのだが、一時期大きく流行したものが時がたつに連れて忘れ去られ、マイナーなものに変化すると、かえってそれがすごく新鮮なものとして目に映ることがある─本作はある意味それだろう。いわゆる「家なき子」的な幼い子供の放浪譚の作品だ。
スキルを複数持って生まれてくるのが当たり前の世界で、動物を使役できるスキル「テイム」ひとつしかなく、おまけにスキルのグレードを示す「星」もない「星なし」だった主人公・アイビーは、両親に疎まれるどころか命の危険まで出てきたために、生まれ育った村を逃げ出すようにあとにする。唯一彼女をかまってくれた優しい占い師の教えに従って危険を避けつつ、森の中や村の「捨て場」で狩りやゴミ拾いをしてなんとか生活していたが、ある日森の中で不思議なスライムと出会い、彼のことを「ソラ」と名付け、一緒に旅を続けていく─。
この作品のなにげに特徴的なポイントは「不便さ」であろうか。知恵はあっても小さな体ではなにも出来ないし、不思議な力を持っていそうな相棒・ソラとも言葉で意思疎通できない(彼はプルプル震えているだけだ)。そんな環境にあって健気な主人公・アイビーがいろんなピンチを、占い師に教えてもらった知恵や、旅先で出会う善良な大人たちに助けられながらくぐり抜けていく。こういった物語が成立するのも、昨今のこのジャンルでは軽視されがちなこれら「不便さ」にあると思う。「苦難」があるからこそ、それを乗り越えていくカタルシスがあるわけだが、本作はそこをイージーな「チート」で無双していくのが売りの昨今の作品への、さりげないカウンターになっている。そういう意味でも本作は一周回ってかつてのスタンダードであった古典的な物語の魅力─その再発見になっているとも言えるのではないか(作者の方がそれを意識されているのかは分からないが)。
すでにアニメ化も決まっているようで年明けから始まるようだが、こういった「古典回帰」的な部分を、現役最前線のスタッフがどう扱うのかは、少し注目しておきたいと思う。
『没落令嬢、貧乏騎士のメイドになります』

没落令嬢、貧乏騎士のメイドになります
欧米などのサブカル系作品の反応をまとめているまとめサイトなどを見ていると、時々見かける表現として、甘々のラブコメ的関係に対して「糖尿病になるw」といった言い回しがあるのだが、本作は文字通り「ああ~これはめっちゃ糖尿病になるわ~w」といいたくなるズブズブ甘々の作品(苦笑)。
父親の汚職疑惑で没落した伯爵家の娘・アニエスは、かつて王宮の宴席から抜け出した庭園で出くわしたトラブルから救ってくれた騎士爵の主人公・ベルナールの元で匿われる。しかし当のベルナールはその庭園での出会いの際に睨みつけられたことを忘れられず、当初は騎士としての義務感だけで彼女を匿っていた。しかし徐々に二人の距離が近づくにつれ誤解は溶け、互いに知らず知らずのうちに惹かれ合っていく、という感じの作品。
んー、もうこれは特に説明要りませんわな。ありますやん、時にデロっデロに甘いケーキやドーナツ食べたいなあ、っていう時が。そういう感じで読む作品ですね。ただ甘い作品ではあるけれども、下品な甘さではなく、ちゃんと抑えている部分もあるからこその、余計引き立つ甘さといいましょうか─思ったほどは砂糖使ってないよ?みたいな(苦笑)。
ただまだ物語は序盤のようなので、このあと場合によってはビターテイスト要素もあるのかもしれないが、だとしてもきっとそれはこの甘々な感じをより引き立てるためのものとなるでしょう、ハイ。
こういう上質な、けどデロデロに甘くもある作品というのも、時には接種したいですよね、と。
疲れた脳に糖分補給されたい方は是非どうぞ!(違)
『月出づる街の人々』

月出づる街の人々
異形のものたち版『三丁目の夕日』、と言える作品─こう書くと少し乱暴だろうか。透明人間やフランケンシュタインに狼男、彼らが普通に暮らしている街の市井の人々を描いたオムニバス的な群像劇。作品の世界は同一で、毎エピソードごとにスポットの当たるキャラクターは変わるが、前のエピソードの人物が次のエピソードの友達として出てきたりする。異形─いわゆる古典的なモンスターたちの日常生活を群像劇で・・・という時点で発想としてすごく面白いが、彼らが種族ごとにまとまって生活しているのではなく入り混じって存在する、さらにある種族の子が同一種族で生まれてくるとは限らないという設定もこの作品ならではの特徴だろう。このことがより物語をふくらませることに貢献している。
そしてそういう登場人物たちにも関わらず、各エピソードはどこかほっこりするものばかりで、さきほど『三丁目の夕日』と例えたのはあながち間違っていないとおもうがいかがだろうか?
昨今何かとやれ多様性だLGBTだと騒がしいが、こと我が国においてそういった多様性は、外から強要されるまでもなく意外と普通に許容されていたのではないか。でなければこういう素敵な作品が生まれてくることはありえないだろう。
この作品にあるように些細な違いに悩みつつも、それを許容し受け入れ、ともに生きていく─それこそが真の多様性というものなんではないかな。少なくともこういった素敵な作品を生み出す土壌を・文化的な伝統を、我が国は昔から持っているのだ。そこは自信を持っていいと思う。
ちょっと脱線したが、どのエピソードどのエピソードもほっこりした読後感で、何人かのメインキャラクターたちに関してはその関係性の発展も読むことができるので、「一粒で二度美味しい」感じ(笑)。個人的にはなにがどうというわけではないのだが「フランケンの糸」というエピソードがなんとなく心に残った。
『登拝女子と山伏さん 人生変わった御利益登山』

登拝女子と山伏さん 人生変わった御利益登山
エッセイコミックであるが、本作に先行して読んでいた『登拝開運祈願 山伏ガール』が面白かったので購入。今回は登拝を続けていたらその中で出会った山伏さんと突然結婚することになり、その一風変わった新婚生活を著者自身の視点から描いている。
この方読む限りかなりガチの厳し目な登拝もこなされており、その時点でかなり好感が持てる─なんというかこの手のジャンルにありがちな浮ついたところが少なく地に足がついている感があるというか。この作品の前に「あ、そっちいっちゃう?」という感じの本のコミカライズ担当されていて少し心配したんだが、本作読むとそれも杞憂だったようだ。これも良い伴侶の方に巡り会えたからだろうか。
エッセイではあるが、先に書いたようにけっこうガチ目の登拝なのでドキュメンタリー的なところもある。また結婚された相手の方が現役の山伏さんなのでこういった登拝まわりの文化のディティールも、普段そういったことに縁の薄い我々一般人には新鮮で面白い。
もともと持病のことや、それに悩んで訪ねた占い師から酷いことを言われたことがきっかけで始めた登拝活動のようだが、あとがきで持病も手術を受け快癒したとあり本当になによりだ。
なかなかこういう実際の体験をコミック化して追体験させてくれる作品というのは貴重かと思うので、できればこのシリーズ続けて行ってほしいと思う。
『野球場でいただきます』(完結)

野球場でいただきます
子供の頃の近所のおっさんから受けた無意識な暴言のせいで、基本野球まわりが苦手な自分であるが(時々映像で試合を見たりはするが)、これはどちらかというと球場まわりの食文化の話、ということでスルッと読めた。なかなか楽しく全3巻というのが少しもったいなかったぐらい。
この作品をみるに、球場まわりの食事の風景というのは、ちょっと競馬場や公営ギャンブルのそれと似ているところがあるのかもしれない─小汚い公営競馬のそれとは雲泥の差だが(苦笑)。
応援に訪れる各球場ごとの食事事情を中心に、意外と語られることの少ない「野球そのもの”以外”」の部分を主題とした非常に珍しく貴重な作品と言えるだろう。
前述のような理由で「野球=社会的に知っててあたりまえ」みたいな野球脳筋人種はいまでも苦手なのだが、こういう周辺文化自体には興味があったので、非常に読んでいて楽しい作品だった。チャンスが有ればぜひ球場に足を運んでみたくもあるのだが、そういった機会はおそらく今後もあまりないだろうな(苦笑)。
『機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー・ライデンの帰還』(完結)

機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー・ライデンの帰還
『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』終了後、ある意味専門誌『ガンダムエース』の柱となっていた一作と言ってもいいが、ついに全26巻で完結。
この作品はある意味『機動戦士ガンダムUC』とは別のベクトルで”ファンが見たかった”ガンダムの続編、というのを非常にうまくやりきった作品かと思う。ガンダム関連のコミカライズは非常に地雷率が高いが、それはこのジャンルの宿痾として”ロボットプロレス”的な側面をどうしても優先せざるを得ず、人間ドラマやファンションセンス的なものが軽視され、その部分が長い間「いかにもオタク」的なもの(センス)でお茶を濁されてきたことが多かったからだろう。しかしそれでは昨今色々な作品に触れているであろう目のこえた読者にはやはり陳腐に映る。そういったネガティブ要素の部分に甘んじることをよしとせず、きちっと一定以上のクオリティで作品を世に送り出せばちゃんと評価されるというのを示したのが『機動戦士ガンダム サンダーボルト』と本作だろう。どちらもちゃんとこれまで別作品で評価されてきた実力のある作家さんを持ってきた、というのが全てという気もするが。
で、本作は謎のエースパイロット「ジョニー・ライデン」は本当は誰なのか?というところから始まり、姿を消した彼の存在がジオンのある”遺産”のカギとなっている、という設定で、冒頭のミステリ的な要素から連邦軍内部の政争~その隠された”遺産”の争奪戦へ、という具合にうまく話を広げている。そしてその争奪戦のなかで活躍する道具としてのモビルスーツがあり、ベースは謎解きに振り回される主人公レッドや各キャラクターたちの人間関係のドラマになっていて、そこがちゃんと”読める”内容になっていたのが大きい。またゴップやヤザンといった本編の名脇役をうまく作中に絡め、彼らを知っている人にはニヤッとせざるを得ない演出もうまい。最終的にここにパイロットとして「お外に出たがる」赤い人も登場するのだが、彼をはじめそのセリフ回しに全く違和感がないのも見事だ。
そして最終的にはユーマとイングリッドという二人の強化人間、彼らのエピソードを縦糸に、当時ジョニーの居場所であったキマイラ隊の瓦解の謎を解き明かした上で─この二人を含む”子どもたち”への物語として本編を締めくくっている。同じ作者のガンダム作品としてヒトラー暗殺を模した『ギレン暗殺計画』という先行作品があるが、この作品でもそうだが、このチームの作品は、ある種の”疑似家族”への帰着をもって物語を終えることが多く、またそれがいい味を出している。前後する『トワイライトアクシズ』もこのチームの原作だが、本作にも登場する”戦えない強化人間”・アルレットをはじめ、このチームは強化人間に”優しい”のもいい(本編が”強化人間絶対コロス”マンなのと正反対である:苦笑)。
そういったところを含め、本作で一番存在感のあったのはゴップ議長とその養女となった”強化人間”イングリッドだったといえるかなあ。結果、彼ら二人が物語の最後を締めているのもむべなるかな、という感じ。
とにかくきちっと読めるクオリティの人間ドラマがあり、かつそのための説得力あるモビルスーツ戦もあるという理想のガンダム作品のひとつであった。脇役に渋いおっさん連中がわらわら出てくるのもいい(笑)。また本編からの設定の流用の仕方も絶妙で、ある意味”正史”的に扱ってもいいクオリティをもった作品だったといえるだろう。もし新規IPのスケジュール的なものがなければ、アニメ化最右翼だった、といっていいレベルの作品だろう。
いまの所可能性は何となく低そうだがどうすかね、バンダイさん?なにげにバリエ展開劣り気味のゲルググがメインのキマイラ隊なので、ガンプラ販促にはもってこいかと思うんですけど?(苦笑)
■小説
今年は続き物などでは小説もいくつか読んでいたのだが、あまり新規開拓には至らない年ではあったので、結果的に以下一作のみご紹介である。
『QJKJQ』
『QJKJQ』
なにかと広告などで目にすることの多かった『テスカポリトカ』、それをセールかなんかで電書で買って、それを読む前に同じ著者の作品─なんか短めのものでも読んでおきたいな、と思って読んだ作品。ちなみに肝心の『テスカポリトカ』の方はまだ読んでいない(苦笑)。
女子高生殺人鬼─しかしその一家全員が殺人鬼、というラノベのような設定で(苦笑)、事実冒頭の主人公の厨二病的な少女のひとり語りの文体などからしてもそんな雰囲気強いのだが、それがちゃんとした”小説家”の作品だとどんどんその描写される世界観にリアリティと重みが加わっていく─こういうところが直木賞受賞するような作家の力量ということかな。発想自体は似たようなものであっても、そこに至るまでの描写の説得力の違い、とでも言えばよいだろうか。
で、物語のオチ─というかどんでん返しの部分はそこだけ聞けばありきたりに聞こえるものではあるんだが、相沢沙呼の『medium』のような読者を騙すべくして騙すような反則感はなく納得の行く描写。というか、本作はそこまでの雰囲気─主人公である少女の心象風景にこそ作品として語りたい部分ということなんだろう。ラノベ的─と書いたがラノベというよりはジュブナイル作品、といったほうが近いかと思う。ちょっと変わった設定の作品を書かれることの多い作家さんのようなので、今後ちょくちょく機会をみて読んでみるつもり。とりあえずは積んでる『テスカポリトカ』からやな(苦笑)。
■映像作品
『進撃の巨人 完結編』
アニメ版進撃の巨人、ついに完結ということで一応取り上げておく。
原作は読んでいたし高評価なのだが、実は自分はあまりアニメ版の方はしっかり追いかけてなくて。これは一つは当初から一部の声優さんのキャスティングに違和感があったため。なので断片的にしかみてこなかったのだが、さすがにこのラスト付近は一応見ておくかということで拝見。舞台がマーレに変わってから制作がWITからMAPPAになったのだが、作品のカラーがよりシリアスさを増すというタイミングだったのでこれは結果的に正解だったのかもしれない(WIT時代には合ったいい意味でのアニメ的な甘さ加減が減った)。
で、この完結編・前後編だが、前篇はハンジさん最初にして最後のの活躍など非常に見どころがあり素晴らしかったと思う。先程のキャストの違和感と書いたことの一つがこのハンジさんのキャストだったんだが、もうここまで来ると文句なし─というかアニメ版はアニメ版としてのハンジというキャラクターを確立させたといっていいだろう、特に兵団の皆との別れのシーンなどは素晴らしかった。
そして肝心の後編なんだが─ここは作者自ら手を入れたというコミック版になかったセリフの改変・増補が素晴らしかった、なんなら原作の方も今後これで統一してほしいぐらい文句のない改変となっていた。ここは評価する。ただそれ以外の部分は残念ながら「スケジュールギチギチでなんとかアニメ化しましたぁ・・・・・」的な感じを受けた、というかとにかく原作をなんとかそのままアニメ化するのに手一杯で、厳しいようだが原作の描写に満たないシーンが多々見られたように思う。特に残念に思ったのが、動かさなくていい止め絵に近い一部カットのクオリティの低さ。これは『北斗の拳』とか『ジョジョの奇妙な冒険』など原作の描線が多いタイプのアニメ化作品でよく見られるケースなんだが、とにかく線を入れることに意識が行ってしまって一枚絵としての魅力や構図を失念してしまっているというパターン─これに近いものがけっこうみられたのが残念だった。
そして演出的に一番残念だったのは、ある意味いちばんこのパートで精神的にきつい「ラガコ村の再現」の部分。ここが見せ方(演出・構図)があまりうまくなく=怖くない・絶望感が足りないので盛り上がりに欠けた。これは前述のように絵的なクオリティの問題で、巨人化した馴染みのキャラクターがあまり元のキャラクターを感じさせなくなってしまっていたことも大きな要因の一つだったように思う。このシーンはある意味原作でも白眉の悪魔的な演出の部分で、ここ迫力なければ意味ないでしょうが!という部分なので非常に残念だった。
ただ最後スタッフロールに合わせて流れるエンディングシーンは、原作からいい具合に少しだけ盛っていて、ここは良かったと思う。
総じて作画カロリーべらぼうに高い作品ではあるので、これらの指摘は酷だとは思いつつも、もう少しどうにか─特に止め絵のクオリティなどは─ならんかったのかなあ、と思う、スタッフさんの労力が半端なかっただろうこと想像できるだけ余計に。
この進撃終盤を引き受けたこともあって、その前後から海外などではMAPPAの評判は高いようだが、ここは確か都度スタッフを外部から呼び集めて作品作ってると聞いたことあるので、あまりブランドとしては評価していない。特に昨今ビッグタイトル引き受け過ぎで、今回それが悪い形で証明されちゃった感あるかな。
元はと言えば片渕須直監督の『この世界の片隅で』のために作られた組織だったはずが、中身が変わって別物になってしまっているようでなんとも残念な話ではある。
『水星の魔女(2期)』
 機動戦士ガンダム 水星の魔女
機動戦士ガンダム 水星の魔女
こちらは1期の終わり前後でちょっと主人公のスレッタちゃんがサイコな方向へ触れ過ぎな感じで、悪い意味で「どうなるんや!?」と懸念していた作品。しかしかなりシナリオ的な紆余曲折はあったようだが、グエルを始めまわりのキャラクターのキャラ立ちの強さに救われて見事リカバリーを果たし、最後の隠し玉であるあのMSの登場もあって見事持ち直した。加えて「終わり良ければ全て良し」を体現するようなエンディングで、結果、なにかと大もめしがちなガンダムシリーズの新規IPとしては近年稀に見る成功例となったのではないか(このあたりバンナムの株主総会でも言及されていたらしい)。
とはいえ作品の背景的な設定などは事前にきちっと作り上げられていたようだが、キャラクターの回りはけっこう立ち位置が変わっていたようで、終盤に出てきたガンダム─シュバルゼッテなども当初はグエルが乗る予定だったとか。そういった視聴者には見えないところでの変更は多々あったものの、初の女性主人公や学園モノという、これまでのシリーズにはない新規の要素を入れ込んだ上できちっと結果を出したのは素晴らしいと思う。このあたりは最終回前後にちゃんとキャラクターへの感情移入ができるようになっていたことも大きかった(未見だが鉄血2期はそれで評価割れた)。正直1期終了前後のスレッタの描写は気味悪くさえあったのが、彼女が最後に乗った機体のなかでパーメットのフィードバックに苦しめられながらも「家族」を取り戻そうと孤軍奮闘するシーンなどは文字通り手に汗握ってハラハラさせられた(こういう心配をさせられるのは久々だった気がする)。もちろん、各所から指摘されるストーリー上の整合性の面での粗さは残るのは事実だと思うんだが、これはこれでいいんじゃないかと─この点同じような指摘あった『リコリス・リコイル』にも言えることかもしれない。
繰り返しになるがやはり本作の最大の強みは各キャラクターの「キャラ立ち」の強さにあったのかな、と。正直ここに救われた部分はかなり大きかったと思う。ぱっと見にはかなり唐突に見える例の「メスガキ懺悔室(笑)」もあのセセリアのキャラの強さがあってこそのシーンで、そこをちゃんとストーリー上に繋いでいるのも強い。最後のまさかの4号とかキモいといわれつつ一部の女性から絶大な人気を誇るシャディクなども、結局そのキャラ立ちの強さが強烈な魅力となり、新規の若いお客さんをたくさんこのシリーズに連れてくることになった(Youtubeなどで水星の同時視聴から他のガンダムシリーズ見てみた、という動画をちらほらみかけた)。夏に行われた「全校集会」名目のイベントもブルーレイ化が決定するほどの人気だったようで、これはちゃんと結果を出した、ということにほかならないだろう。
惜しむらくはあまりにもきれいにたたみすぎたので、この魅力的なキャラクターたちに再度会う機会はあまり期待できそうにない、という事か。ベリショーのニカ姉可愛かったのに(違
あと特筆すべきは2期エンディングのアイナ・ジ・エンド『Red:birthmark』が素晴らしかったっちゅうことすかね。
あまり音楽聴き慣れてない層には「キモい」とか「声が嫌」とか言われていたようだけど、近年稀に見るブルージィかつソルフルな名曲だと思う。個人的には10年に1曲あるかないかの曲と言っていいレベル─ただここ数年はミレパx椎名林檎の『W●RK』とかそんなレベルの曲多すぎるのよね(苦笑)。
AiNA THE END “Red:birthmark” – NHK WORLD-JAPAN Music Festival
『葬送のフリーレン』

葬送のフリーレン
今期一番の話題作と言っていい作品。原作は以前にレビューしたが、正直このストイックな原作がここまでふくよかな豊かさを含んだ、素晴らしい映像化作品になるとは思っていなかった。監督は昨年の1,2を争う話題作であった『ぼっち・ざ・ろっく』の斎藤圭一郎氏。ほんとに実力のある演出家・監督が久々に表に出てきた、という印象。
本作の魅力はある意味”回顧=想い出”の魅力かと思うんだが、昨今の目まぐるしく動くのが当たり前のアニメ作品業界にあって、この坦々とした原作をどうさばくのだろう?というのは放送前から気にはなっていた。
しかし斎藤監督はこの坦々さをいい意味で逆手に取り、静かなところは文字通り坦々と、そして要点となるポイントではしっかり動かす─こちらの想像以上に動かす、という演出方針で映像化作品のある意味お手本のような仕上がりとなっている、正直すごい。”静かなところは坦々と”と書いたが、実はこれほんとうに難しくて、その平坦な流れ行く場面をダレずに見せるにはある種の思い切りの良さと、フィルムに対する”リズム感”のようなもの─そのセンスが必要不可欠だと思うのだが、本作はそこが本当に見事。『ぼっち・ざ・ろっく』もそうだったが─この作品が「音楽」がテーマだったことからもわかるが─この斎藤監督はおそらくそういうある種の”リズム感”に天分を持ってらっしゃる方なのではないか。
緩急の付け方、というところでは前半のクライマックスである「断頭台のアウラ」戦を2話に分けてやった部分などでも、前半は愛弟子フェルンや戦士シュタルクたち若いメンバーたちの戦闘をこれでもかというほど動かしてみせ、ボス戦にあたる対アウラ戦では回想をメインに逆に静かな戦いで魅せきった。ここが実は凄いのはアウラ戦では激しい戦闘というのが本当にほんの少しで、しかし回想シーンで視聴者の興味をちゃんとつなぎ、クライマックスでは作中の重要な設定の開放を音楽の力─エヴァン・コール氏のBGMが素晴らしい─を借りてガンッ!と盛り上げるという緩急の付け方の上手さ。そして『ぼっち~』と同じく8話で主人公の真の姿を見せる=作品タイトル回収!そらアウラ様もネットミームにされますわ!?(違)。
総じてハイカロリーになりがちな昨今のアニメ制作トレンドにおいて、こういう全体の労力を考えての緩急の設計ができる人材は貴重だろう─もちろん、それが通用するタイプの原作を選んだところから制作側の上手さを感じられるのだが。
・・・・・と思っていたんだが(笑)。
実は”坦々と”と見える場所にもなにげに作画カロリーめちゃくちゃかかってるかもしれん(笑)。特に最新話とかの冒頭ザインの少年時代の手をとり引き起こす~走る二人の少年の足元のカットとかあれなによ!?あとその前のSNSで大きな話題になっていたダンスシーン!これなんかどう考えてもTVアニメのレベルじゃない─劇場作品のそれよな・・・!?これも当初は「キャプチャーか?」「ロトスコープか!?」と言われてたが、どうもキャプチャー自体はしたようだが、結局そのままでは使えず手書きでの作画ということらしい(!)わかりやすい部分ではフェルンがクルッと回るところでのスカートが遠心力でふわっと広がるところのエレガントさなども凄いが、もっと凄いのはそれをエスコートするシュタルクの服の燕尾部分の布の質感・重さが伝わってくるような繊細な動き、ぐはー!?こんなモンただで見せてもらっていいのか!?というレベル(いや、アマプラに課金はしてますけども・・・)。
ということで連続2クールの前半を年内で終わり、年明けからは2クール目─一級魔法使試験編がはじまるのだが、若干心配しているのは、この2クール目のほうがシーン的に作画カロリーはかなり高そうだ、ということ。果たして1クール目のように静かな場面で節約して動かすところにリソース投入する、といった手段を取りにくいこのクールで、どういったモノを見せてくれるのか─このあたり良くも悪くも楽しみにして待ちたいと思う。
あと本作の唯一の疑問点は「主題歌は作風とあまりあってないよな?」という点なんだが・・・実はYOASOBIあまりピンとこなかった勢のワタクシ、曲としてはこの曲これまでで一番好きだったりするのだ(笑)。良曲が必ずしも良作にマッチするとは限らないし、良作のOPになったからといって良曲が必ずしもマッチするとは限らない─面白い話ではあると思う。
『PIG/ピッグ』
うちは地上波見れるテレビがない+コロナですっかり映画館へ足を運びにくくなった─ということで最近映画を見るのはもっぱらアマプラなのだが、サブスクあるあるで、いざ見ようと思っても謎の「今はまだその時ではない」が発揮されて、すっかり見る数が減ってしまったわけだが(苦笑)、本作は今年見た数少ない実写作品のひとつ(2022年制作)。

ピッグ/pig(字幕版)
本作はなにがびっくりって、その主演俳優が「あの人」ということですね。たしかそれをSNSでみてウォッチリストには登録したあとすっかり忘れてから見始めたら「えー!?」という感じ。いやびっくり、この人こんなちゃんとした役もできる俳優さんだったのか!?と。
作品としても過剰なディティールはあえて語らず、どちらかというと断片的な情報と構図=画作りでその雰囲気を感じ取るタイプの非常にストイックな作品─ただこの点、なにか仕掛けのあるハリウッド映画的な作品と誤認して見始めると肩透かし食らう感じはあるので、その点は注意が必要かな。
とにかく独特の雰囲気で、とにかくその静かな空気感が素晴らしい。そしてその静かな空気感の真ん中に佇む静かな孤独・怒り・寂しさ─。
派手なタイプのアクション映画も自分は嫌いではない─むしろ好きかも(苦笑)─が、こういうポートレート写真のような、静かで陰影のある作品というのも、やはりいいものだと久々に感じさせてくれた。
まあとにかく主演俳優の「あの人」の変貌ぶりを見るだけでも一見の価値ある作品だ。
『ゴジラ-1.0』
一部ではドラクエの映画での”やらかし”のせいでやたら評判の悪い山崎貴監督作品、ということで当初は観にいく予定なかったんだけれども、日本よりも海外での反応がやたら良いらしいと聴こえてきて「むう、確かに観もせずに決めつけるのもアレか」と思い駆け込みで観てきた。
※こちらは年明け公開予定のモノクロ版トレーラー
結論としては、非常によくできている作品で少なくとも上映時間の間にずっと集中力が途切れることもなく最後まで楽しく(?)見れる良作だった。
もちろん細かなところではいろいろ「ん?」とか「ここはどうにかならんかったんか」という部分はあるにはあるんだけれども、エンタメ作品としていま国内で作れる作品としては考え得る限り一二を争うクオリティになっていると言っていいだろう。だれるようなシナリオのへぼさもないし、監督自身がVFXに造詣が深いならではの大胆なカット割りなどは、タレントの人気頼みでなんとか制作費を回収している平均的な凡百の邦画とは比較にならない。
そして「海外でより受けた」というのもなんとなくわかる。よく指摘されるのがアメリカなどの紛争派兵からの帰還兵といった層に刺さるシナリオだった、ということもあるだろうが、基本、ドラマパートの部分が非常に普遍性が高いというか、全体のシナリオがあまりローカルな事情に左右されない分かりやすい構造になっている、というところにあるのだろう。海外も視野に入れて制作したのか?という質問に監督のほうもそれらしい答えをしているらしいとも聞いたので、ここはなるほど、という感じ。
ゴジラということで東宝系の劇場で観たのだけれども、ここ数年のクソ値上げラッシュで2000円の鑑賞料金だったが、まず値段分の値打ちはあった、とは言ってよいと思う。
そのうえで─。
これより一つ前の作品に当たるのがいろいろと物議をかもしつつも大きな話題作となった『シン・ゴジラ』なわけだが、個人の好みでいうと自分は『シンゴジ』のほうが圧倒的に好み。
本作も悪くない─むしろ一般家庭のみなさまにはむしろこちらの方をつよくおすすめするほど、この『ゴジラ-1.0』はよくできている。
ただなんというか物語がすごく「コンパクト」なんですよね、わけのわからない「世界が終わるかもしれない」といった恐怖や狂気は薄い─というかほぼない。もちろんそれは悪いことではなくて、こういった万人に向けての良質な作品を作れる可能性がある才能だから山崎監督には次々と作品のオファーが来るのだろう。
しかし自分にとってはあまり”毒”のない作品に感じられて、積極的に肩入れしたくなるような要素は少なかった、といえばよいか。ある意味『君の名は』の大ヒット以降の新海誠監督のそれと似ているかもしれない。ハイクオリティだしよくできているんだけど、あまり深くは感情移入できないというかな。ただそのご両人の作品がこういう形でちゃんと数字で結果を残していっている─それも海外を含めて─なので、いい意味でちゃんとヒットメーカーとしての才を存分に発揮されている、ということだろう。単純に斜陽気味と思われる本邦の実写映画業界にとっては非常に良いことなのではないか。
で、「これは不可抗力だよな~」と思いつつ、あまり深く思い入れできなかったことの理由の一つに「役者さんの顔の薄さ」がある─あまり人間的な厚みを感じられないというかな。敗戦直後でそんなにふくよかできれいな顔してるかな?というあたりがやはり深い感情移入を妨げていた感はあるかと思う(例外は「昔の女優顔」的なところもある浜辺美波さんか─この方もう立派なスター俳優だな)。ただそれを抜きにするなら、俳優さんたちの演技自体は素晴らしかった。なのでさすがに断食しろとまではいわないけど(苦笑)もうすこしメイクなりで汚すとか、ポスプロで補うとかはあってもよかったんじゃないかなとも思うが、ここは予算の問題もあるんだろう。ただ近年の作品にしてはモブのおっさん連中の配役はなかなか素晴らしかったし、こういう”昔の顔”というか、馬面・鬼瓦的な個性的な俳優さんたちにはもっとスポットを当てるというか、積極的に登用していくことは邦画業界は考えるべきだろう。線の薄いペラいイケメン俳優ばかり厚遇していることが邦画の土壌がやせ細ることになっている大きな原因の一つではないのか。あと上映前の予告でちょうど『ゴールデンカムイ』の予告も流れたが服が「綺麗すぎる」のよ。戦争帰りでろくに風呂も入れない環境のヤツがあんなきれいな制服着てるかっちゅーの(その点本作は汚し頑張ってたが、それでもまだ薄いと感じる部分は多々あった)
とはいえ、いろいろと今後の邦画の可能性を考える意味では、少し希望を持ってもいいのかな?と感じさせる良作だった。とりあえず駆け込みでわざわざ映画館で見ておいてよかった一本であった。








