この間の東京国際映画祭でガンダムUCの一連のシリーズがスクリーンでかかっていたのだが所用で観に行けずちょっと悔しい思いをしていたのだが、なにげにTOHOシネマズ新宿の上映スケジュールをみると「ガンダムUC EP7(MX4D)」とある。
EP7は何度も見返していたがMX4D自体はそういえばはじめてだな、パシフィックリムで体験した4DXとどういう部分が違うんだろう?ということもあり日曜日の夜の回を観に行ってきた。

この間の東京国際映画祭でガンダムUCの一連のシリーズがスクリーンでかかっていたのだが所用で観に行けずちょっと悔しい思いをしていたのだが、なにげにTOHOシネマズ新宿の上映スケジュールをみると「ガンダムUC EP7(MX4D)」とある。
EP7は何度も見返していたがMX4D自体はそういえばはじめてだな、パシフィックリムで体験した4DXとどういう部分が違うんだろう?ということもあり日曜日の夜の回を観に行ってきた。
今月はこちらが意図したわけではないんだけれども、見ておきたいライブが集中していてライブ月間―それも世間的に見ればいわゆるオタク系なライブばかりでアレなのだが(苦笑)、個人的にこの界隈の音のほうが巷の下手なポップシーンよりも国内の旬のポップシーンのリアルなんじゃないかと思う節もあるのでまあガシガシいってるわけですが、さすがに連チャンで続くと記事書くのも大変、オマケに今回は2DAYS両方ともあたっちゃったよ~!?けど偶然とはいえ2DAYSいっておいて正解だった。
という事でちょっと日にち経っちゃいましたが先日12,13と行ってきました澤野弘之LIVE2015 [nZk]003!
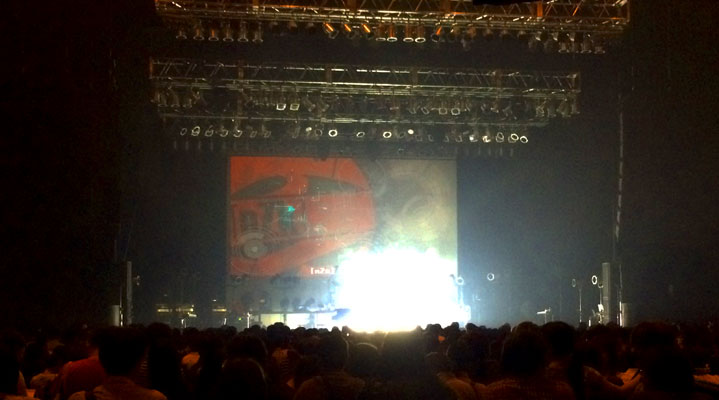
劇伴(BGM)を数多く手掛ける澤野弘之氏のボーカル中心のライブ。一昨年より毎年行われている恒例のライブで、今回はその三回目となる『澤野弘之LIVE2015 [nZk]003』となる。氏の手掛けるボーカルプロジェクト[nzk]としてこれまで参加してきた数多くの多彩なボーカリストが登場する贅沢なライブで、ライブ直前に発売となったニューアルバム「o1」とサントラベスト「emU」の曲を中心に数多くの名曲が生で披露された。
原作の福井氏のインタビューをちょっと読んでみたくてガンダムA(雑誌)の増刊号的なUCAのバックナンバーを買ってみたのだが、以前からぼちぼち評判のいい外伝マンガも一部載っていたので成り行き上読んでみた。
するとけっこうおもしろかったので、bookwalkerのポイントがぼちぼちたまってたこともあってこの機会にまとめて読んでみた。
主に敵方となるジオン残党「袖付き」、そのMS各機の「整備責任者=機付長」からの視点でUC本編を補完するような形の「~機付長は詩詠う」、かたやそれと対をなすように連邦寄りの視点から展開される「星月の欠片」、そしてハードな劇画調でミリタリーテイストあふれる「MSV楔」。特徴として同一誌掲載という事もあってか、作家は違うものの作中世界の横の整合性をきちっと取ってあり、かつ本編とも著しくかけ離れた描写もなく各エピソードのエンディングの先に本編が想像できるような構成になっている作品がけっこうみられる。またこういう企画系の作品群としては比較的「読める」作品が多い印象。
Aimer嬢のパート未収録でAmazonレビューでは発売前から大酷評されていたパッケージ(苦笑)だが、実際に観に行った者としてはまあ一応持っておくかということと、もう一つ理由があって購入。
昨年7月、UC完結を受けて行われたパシフィコ横浜でのコンサートライブのパッケージ化。当日おこなわれたオーケストラライブを中心にトークショーの様子や昼夜公演でそれぞれ異なっていた朗読パートを収録。ただしEP6、EP7の主題歌を担当したAimerの歌唱パートは未収録。
ここ数年ガンダム関連のコンテンツが活発化していたせいか、ネットでもいろいろと周辺情報・関連の話題が取り上げられることが多かった。
その中で折に触れてときどきぽこっと言及されることがある作品で、内容的にちょっと気になるので手に入れてみた。
1992年発表の作品。名義は後にクロスボーンガンダムのコミカライズを担当する長谷川裕一作品。舞台は逆襲のシャアの手前、宇宙世紀0090年―”逆襲”前のアムロ・レイ、シャア・アズナブルの消息が公にされていないところをうまく使い、その時期に木星圏で働いていたジュドーを主人公とした”if”のスピンアウト。この空白の期間二人はある”物体”を追い、ともに木星圏へと赴いていた―それは全長100mを越えるであろう伝説の”巨神”だった・・・。
昨年末に出ていたモノだがいちおうレビューしておく。
昨年完結したガンダムUCの評論集。皆河有伽、堀田純司、切通理作などの文筆家らによる作品の解題をメインとした評論集。それに加えビジネス面としての作品をサンライズ宮河恭夫取締役、制作面を古橋x小形x福井の三氏による座談会、そして〆として原作者・福井晴敏氏によるニュータイプ考察の私論とされた一文が載る。