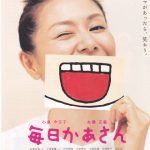内容の是非は例によって賛否あると思うが、とにかくべらぼうにわかりやすかった。
円高の正体 (光文社新書) [新書] 安達誠司 (著)
先日取り上げた『「復興増税」亡国論』と同じく、リフレ派の著者による行き過ぎた円高の悪影響の指摘、および、それに対するインフレ誘導を主張した一冊である。内容的にはリフレ派のそれであり、本書ならではの特徴的な主張はないようだが、こういったテーマを理解する際に必要となる、基礎的な知識の解説が非常にわかりやすかった一冊。
これから先の景気動向を知る意味では、ぜひたくさんの人に読んでおいてほしいと思う。
基本的な内容は『「復興増税」亡国論』と同じ論調の内容だが、本書のいいところは、具体的な数字やグラフが的確なところでふんだんに使われていること。
筆者の主張するところを、そういったグラフ類を使って、かつ、非常に平易な説明で解説してくれている。
この一点だけでも、ぜひ一読をお勧めする。
ただ、これだけわかりやすく書かれている本なんだが、例によってamazonのレビューをざっと読んでみると、当然ながらいろいろと反論はあるようだ。
その多くはやはり、金融緩和(日銀⇒市中銀行へと資金供給を行い、お金の流通量自体を増やす)によって資金量を増やしても、投資する先がないのでインフレにはならない、というあたりだろうか。
このあたりがどういう動きをするのかが、確かに一つのポイントではあると思うのだが、自分的にいくつかの本やネットなどでも反インフレ派の論などをみて思ったのは、ここの問題は資金供給量のスケールの寡多によって大きく違ってくるのではないか、ということ。
ようするに、これまでの資金供給量では、圧倒的に少なすぎたのではないか。
もちろん、かといって基本的に市中に流れるお金の量をどっと増やすという方法なので、机上で考えるよりイージーなことではないと思う。
しかし結局”インパクト”が足りない、ということではないか。
ようするに資金供給をうけた市中銀行(いわゆる普通の銀行)がそれにより投資なり融資なりに動かなければ、インフレは発生しないわけだが、その際の銀行が動き出す根拠となるのが繰り返し出てくる”期待インフレ率”というヤツかと思うんだが、ここで銀行側が
「うわ、こらとりあえず資金を何らかの形で運用(投資や融資)しないとしゃれならんわ」
と思うところまで行っていない、というか。
もちろん、有望な投資先がないというのも一理あるし、個人的にはそういった野放図な経済拡大に抵抗感もあったりはする。
しかし、この手の話を少し勉強して実感したのは、こういう通貨供給量というのは、ほんと社会にとって血液なんだな、ということ。
そして有望な投資先がない、と嘆いてみても、日本経済全体というスケールでみると、その体の大きさに対して、明らかにその”血”が足りていない。
(かなり利益を上げている企業ですら、資本準備金的な額面を拡大させる一方で、従業員の給与になかなか反映しないというのは一つはこういったこともあるのでは?)
少なくとも、血液を循環させるだけのマージンが取れていないという印象がある。
それが世界各国の金融緩和による相対的なマネタリーベースの減少なのか、高齢者の貯めこみによる循環阻害が大きいのかはわからないが、とにかくお金が必要な形で回っていない。
これは、ある種高齢者問題と似ているのかもしれない。
日本という社会がもう成長をやめて老齢期に入った、というのなら有望な投資先がない、というのも一理あるだろう。
だがしかし、現実は日本人は―特に若い人たちはほんとうに満たされているのだろうか?
ここ数年、よく若い人は車に乗らなくなった、といわれるが、そういった人たちにまず余裕を持って車を帰るだけのお金が渡っているのか?
渡ってないよね、たぶん。
そういう層を―蛸が自分の足を食うように―犠牲にしている構造が、まず間違いなく今の日本社会には存在していると思うが、そういう視点を抜きにして、単純に有望な投資先がない、というのもナンセンスだと思う。
つまり成長する器官(世代)へ血液(お金)が回っていない、回せていない。
乱暴な例えをすると、高齢者というガン細胞が血液を溜め込んで、成長できるはずの正常な細胞に血液が回っていない、その結果、成長できるはずの身体が育たず、全体(日本経済)が多臓器不全⇒壊死しかかっている―。
そうは言えないか?
そういう構造的な問題があって、そこへ単純に資金供給量だけを増やしても仕方がない、というのはある意味事実。
だが、そういう構造を変えていくにしても、とりあえず、ショック療法的にでも経済を”動かす”、お金を”流す”というのも、必要だと個人的には思う。
だから本当は、資金の供給と同時に、そういった社会構造の変革も行わなければいけないんだろう。
ただ、それをするための基礎体力的なものが、いまの日本は非常にむづかしいバランスにある。
しかし、個人的にはとにかく”流す(流れている)””動かす(動いている)”というのは、この世のある種の真理の一つだと思っているので、絶対量が減っているのか、溜め込んでいるのか、その原因はともかく、とにかく”流す”というのは大事なような気がするんだが。
とまあ、こういった自分のような雑な感想はともかく、本書は、いま日本の世の中が直面している大きな構造的な問題、それを読み解き、これからまだ人生を生きていかなければならない人たちにとっては、ある種、自分たちの置かれている立場とはどういうものなのか?それを解き明かすための助けになる、そういう一冊ではあると思う。
賛否はある―この手の経済書についてはどれもそうだが―ということを念頭に置いてでも、ぜひ読んでおくことをお勧めする。
余談
自分は本書をNexus7のKindle版で読んだ。前から薄々感じていたが、電子書籍とこういった新書系の本はいちばん相性がいいように思う。
Nexusの場合はとくに縦長のレイアウトが新書のそれを髣髴とさせるので、ますますそんな印象が強い。
Kindle版のほうが少し値づけが安いので、対応するデバイスをもっていて、電子書籍に抵抗のない方は、こちらで読んでみるのも良いだろう。
円高の正体 (光文社新書) [Kindle版] 安達 誠司 (著)