かなり迷ったんだけれども、行っておかないときっと後悔すると思ったので行ってきた。
もともとまどかマギカという作品を知ってから、自分の中でその音楽のウェイトというのはすごく大きくて、比率で言うと―
「音楽25%/イヌカレー25%/その他の要素50%」
みたいな感じ。実を言うと単品で発売されていなかったサントラほしさにamazonで価格が安くなっている時をねらってチマチマDVDも買ってそろえてたというのは秘密だ(泣)。
(正直この歳でアニメのお皿買うはめになるとは思わんかったwおまけに今月サントラ単品発売でさらにぐぬぬw:泣)
それぐらいその音楽が大好きで、かつその中の弦楽器の曲が大好きだったので、実は「こういうコンサートないのかな~」と思ってた。
で、このコンサートツアーがあると知ったのが、なんと、東京公演終わってしまったあとで。まさにぐぬぬ!?
しかし調べてみるとあと何回か残っている。仙台は検討した日にちからすると日程的に厳しい。広島・高松はさすがに遠すぎる。で、残るは名古屋・大阪。
大阪にしてもよかったんだけど、もう年の瀬も近いので年末には帰省するだろうしなんだかなあ、しかし名古屋は唯一開始時間が遅め(19:00-)なので一泊必須。どうしたものか、そう思ってたら―
1 8 き っ ぷ の 期 間 が 1 0 日 か ら じ ゃ な い で す か ! ?
(名古屋の日程は11日)
しばし悩んだ後「今年のテーマのひとつはやりたいこと・したいことをなるべく我慢しないこと」、加えて普通のバンドのコンサートなどと違って、オーケストラというのは実はなかなかこういうチャンスは無い、というのがあった。
(オーケストラのほうが集客とその構成人数からどうしても開催要件が厳しくなる)
なので「よっしゃ!行くか!!」ということでオンラインで予約ぽちっとな。
(しかしこのチケットの引き取りがコンビニだったのである意味罰ゲームだったのは秘密なw-40過ぎのおっさんが「魔法少女」と記載されたチケット店頭で引き取るってどんだけ~(T△T))
で、鈍行に乗ってえっちらおっちら行ってきたわけですが、結果、行ってきた甲斐のあるすごくいいコンサートだった。
会場となった愛知芸術劇場コンサートホールはちゃんとしたコンサートホールで、席の構成からもそれ専用の設計というのはわかる場所。客層は作品のファンらしき層がほとんどだったけど、高齢の方や親子連れも多く、単純にこの作品の熱狂的なファンだけという感じには見えなかった。
面白かったのはグッズの販売で、キャラクターグッズが例によって販売されていたんだけど、その中でピアノスコアの楽譜が在庫瞬殺だったのが、なんとなく客層を想像させてニマっとした。
で、肝心のコンサートだが、ほかの場所では各キャラクターの声優さんが司会進行のような形で出てくるらしいのだが、この名古屋公演はスケジュールが合わなかったらしく、ほむら役の斉藤さんの録音で。
その代わりかどうかは知らないけれど、背景のスクリーンに曲の進行に合わせて作中のシーンが投影されていた。
(※ちなみに冒頭に貼った写真は演奏などの邪魔にならない開演前に、場内案内係の方にお聞きしたうえで1枚だけ取らせてもらいました)
しかし個人的には、こういった演出は(あっても悪いものではないが)別に無くてもよかったのではないかと思った。
それぐらいこの作品のスコアはクオリティが高いし、オーケストラというものとの親和性が高いように感じていたので。
事実、自分の場合はスクリーンほとんど見ずにオケのほうばかり見てた。
「ああ、この曲はあの楽器だったのか」「えー!?この曲こんなに少ない構成でこんなに存在感あったの!」「バイオリンやっぱりええなあ(うっとり)」etc,etcという感じ。
もちろんちょっと惜しい、というか聴きなれている曲だけに違和感のある個所もあったりはしたんだけれども(一部のコーラス、打楽器類のベロシティ・リバーブのとっちらかり具合とか)やっぱり生の楽器の生演奏というのは素晴らしいのが圧倒的に勝った。
(バイオリンのソロとったおねえさんが、そのきびきびとした動きに加え、ノースリーブの黒い服+ズボン姿でなんかカンフーの達人っぽいのもよかった:違)
特に今回改めてすごいなあと思ったのはバイオリンという楽器。
そのサスティンといい強弱のコントロールといい、なんと広い音域を自由自在にコントロールできることか!特にこれは自分が言うまでもないことかと思うが、あのグーッと伸びる音というのは本当に気持ちがいい。
そんなバイオリンが―目視で数えた限り16台―一斉に鳴る曲なんかはまさに圧巻。
そこに加えてオーケストラがまさに全体で一気に奏でるタイプの曲(コンサートの前半ラストの「she is witch」、後半の中盤「Surgam identidem」等)は、生ならではの迫力で、本当に聴いておいて良かった。
一応パンフレットから演奏曲目を書き写しておく(誤字あった場合はご容赦)
sis puella magica!
terror adhaerens
salve,terrae magicae
ルミナス
postmeridie
puella in somnio
desiderium
未来
credens justitiam
venari strigas
clementia
warning #2
agmen clientum
amicae carae meae
wo ist die kase?
signum malum
incertus
serena ira
decretum
anima maka
a human bullet
inevitabilis
fateful #2
confessio
witch world #2
she is a witch
― 休 憩 -
fateful #4
symposium magarum
i miss you
numquam vincar
magia[guattro]
コネクト
mother and daughter
surgam identidem
sagitta luminis
her wing
rebirth
taenia memoriae
pergo pugnare
ひかりふる
※ボーカル曲もすべてオーケストラアレンジでボーカル自体は無し。
これに加えてアンコールで例のアヴェマリアとラストがMagiaで〆。
(ほかにもう1曲やったような気もするが記憶曖昧、スマヌ)
アベマリアはやっぱりすごくよかったなあ。
ポップミュージックもそうだが、いまこの商業音楽がなかなか厳しい時代にあって、こういった物語性の強いマンガやアニメを題材とするのは、けっこういい方法のような気が最近強くしていて。
これまでは、その物語性の強さが逆に音楽原理主義者的な考え方からすると”邪道”と捉えられやすかった、というのは、自分もその気があるタイプの人間なので非常によくわかる。
(いわゆる「アニソン」と下に見る傾向の原点はここだろう―ただそう言わざるを得ないクオリティのものが多々あったのも事実だが)
しかし、こういったマンガやアニメという題材の存在していたなった時代においても、その音楽が語ろうとしていたものはある種の「物語」ではあったわけで。
音楽単独でそれを語れるなら、もちろんそれはそれに越したことは無い。
しかし、実はそれら各々は対立すべきものではなくて、お互いをお互いに補完するものであるのが実は自然だったんじゃないのかな、という気がしはじめている。
音楽も、マンガ・アニメ的な表現も、それは人間の心に訴えかける「物語」というものを構成するための、ひとつの回路・装置でいいんじゃないか。
そのためにそれぞれが補完し合って、各々を奏で、創ってくれるひとたちがそれで生活できる糧が出来上がってゆくのなら―それは決して悪いことじゃないと思う。
そういう意味で、こういったクオリティの高いスコアを、ちゃんと生でみせる・聴かせる、という機会は大切なことで、こういった企画はどんどんやってほしいと思うし、その結果として関係者に正当な対価が渡るなら、それはとても素晴らしいことじゃないか?
ということで、もっとじゃんじゃんやってほしい。
正直、東京でもう一回ぐらいあるなら観に行くと思う。
それぐらい生オケの演奏って実は素晴らしくて贅沢なモンなんだよな。
※会場の愛知県芸術劇場は比較的新しいのかすごくきれいな建物で、内装がちょっとSF映画チックで楽しかった。
特にこのエレベータ周りのデザインがいいっすなw



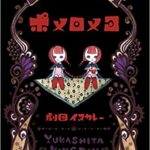

![【レビュー】『魔法少女まどか☆マギカ[魔獣編] 1巻』ハノカゲ](https://www.thx-design.net/blog/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/25.jpg)
