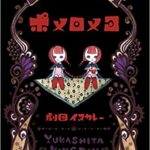昨年の3月、震災から1年をむかえた頃に出版されていた一冊。
コミュニケーションは、要らない (幻冬舎新書) [新書]
押井 守 (著)
国内よりも、むしろ海外の玄人筋に人気のあるアニメーション映画の監督であり、”安保”に乗り遅れた元左翼として自身の出自を自覚的に語ることの多い、押井監督による震災や原発―その前後の日本の言論空間の空疎さを指摘した一冊。
本書の中で監督は、あえて意図的に「僕は原発推進派である」との命題を設定して、論を展開している。
自分は脱原発~原発廃止の方向性を支持する人間だが、本書の監督による「原発推進」のスタンスはこれまで読んだほかのそれらと違い、論旨としてはいちばんうなずけるモノだった。
それは、本書で述べられているように、震災発生後のtwitter他のネット上での論争の多くが、意見の異なる双方が、それぞれを叩きまくり、挙句の果てに嘲笑・侮蔑で終わるという不毛なものがほとんどだったのではないか、と個人的にも感じていたからだ。
本書のタイトルはそのことを指して、それが「コミュニケーション」というならそんなコミュニケーションは要らない、ということではないだろうか。
そのうえで本書は、もともと異なる立場なり階層ごとの”言論空間”があって、その異なる言論空間に属するもの同士が、共通点を探ろうとする―それが本来のコミュニケーションである、と述べている。
これも至極納得だ。
(そういう意味で、自分は「放射脳」という言葉を喜んで使いたがる人たちは基本的に信用しない―なぜならここでいう”コミュニケーション”を本質的に拒否していることにほかならないからだ)
自分が上記のような震災後のネットの論争を見ていたときに、痛烈に感じていたのは
「互いに議論をするための共通の足場(知識)を揃えずに本当に”議論”になるのか?」
「なってないよな?」
さらに
「相手にわかってもらおうとするのではなくて言いたいこといって溜飲下げてるだけじゃん」
ということだった。
本書ではまた、本質的なことを論理的に筋道を立てて考えることの重要性を述べている。
この点は自分も易きに流れていた面はあるので、反省はしているんだが、この指摘を踏まえた上で、あえて述べておきたいのが、実はこのように一見「論理的」に命題を組み立てているようにみえる論者も、実はツールとしてロジカルに言葉を使っているだけで、本書の指摘するように決して「本質的」な部分までさかのぼって、論理的な言葉を使っていた人は皆無に近いと思う。
つまりそれぞれの主張を強化するためだけに「論理的」なだけであって、その主張の根源を本質的なところまでたどって論を展開していた人はほとんどいなかったのではないか?
(敢えていえば、モーリー・ロバートソン氏ぐらいではなかったか)
逆に言うと、そういう本質的なレベルまでさかのぼるのでなく、ツールとしての「論理的」な言葉を振り回す連中のほうが、個人的にはたちが悪いと感じている。
(よく「自動車事故の死者のほうが原発関連の死者より多い」というロジックを使いたがる原発推進派の方々などはそれに該当すると思う)
なぜなら、それは本質ではなくてディティールであるのに、ディティールをさも本質であるかのようにすりかえるための道具として「論理的な」言葉を使っているからだ。
そういう意味では、本書にあった「知識人」ではなく「教養人」たれ、という言葉は、深い。
昨今のビジネスシーンではやれこの本がいけてるビジネスパーソンには必読だ、なんだ、と喧しいが、実はそれはそういった、いわば「キャリア・ビジネス」とでもいうブロードキャストに反応して、単なる知識のコレクターと化しているに他ならないからだ。
もちろん自分も、そういった「いまはこの本!」というのには弱い(泣)。
しかし、奇しくも本書でも指摘されているのだと思うが―こういったコレクションするための知識でなく―教養というものを身に付けるためには、やはり”歴史”の感覚が必須だ。
そういった過去の人類の知恵の蓄積を紐解いて、そのうえで自分なりに咀嚼してはじめて、教養足りうるわけで、いくら流行の知識を身に付けても、それは流行であるが故に流行とともに廃(すた)り行く。
そういう意味で、本当の「議論」とは、本当の「教養」とは―
そういったことを身に付けたいと思う人は、読んでおくべき一冊であると思う。
冒頭にあるように、本書にはけっしてその答えそのものは載っていない。
しかしそこへ近づくための、足場は提供してくれている。
もちろん読んで賛否あると思うが罵りあうだけの、不毛な議論や、”共感”や”絆”などという、実は毒にも薬にもならない甘いだけの言葉を越えて、自分の立場や意見を異にする人たちとの間に建設的な”コミュニケーション”を持ちたいと望むなら―
本書は必ずそのきっかけを与えてくれると思う。
※本書で押井監督はあえて「原発推進」の立場で論をあげてらっしゃるが、まだレビューを上げれていないが、反原発の立場である、安冨歩氏の著書と部分的に似たような香りを感じたのは興味深かった。
このあたりは、手をつけてる最中の安冨氏の著書を読み終えた後に、チャンスがあればもう一度整理してみようかな、とは思っている。
あとパトレイバーの劇場版2作目きちっと見直してみないとな。
ちゃんと通しでみれてないのだわ。