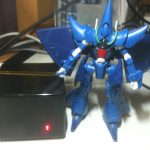しばらく更新滞っておりましたが、父の初盆で実家に戻っとりました。

ウチはとくに先祖代々がどーたらこーたらという伝統のある家でなく、ある意味ほとんど父方のばーさまからの家のようなものなので、そのあたりは気楽なんですが、逆に世間様一般のお盆の作法のようなものをあまり知らない(苦笑)。
そんなことやお寺様が10日ごろ来られるとの事で、それにあわせてやや早めに帰省しておったわけです。
で、母がお盆のやり方をお寺さんに改めて聞いてみたのですが、お寺側は「詳しくはお上人(お坊さま)が伺ったときに聞いてください」と。
で、お寺さんがこられた日に聞こうと思ったら「いやー今日一日で20件回らんといかんでな」とあまり詳しく聞く時間無し(汗)。
え、水塔婆?経木塔婆?なにそれおいしいの?状態。
でお寺様はかなりダイジェスト気味のお経(足しびれなくて助かりましたが:笑)をあとに颯爽と次の戦場へ向かわれたわけですが・・・。
なのでネットで精霊棚の作り方や一応のお作法は調べてなんとか形を整えーの。
そして少し早かったかもしれないけど、12日の夜に迎え火をたいて、自分は今日帰ってきたわけですが(送りは母に任せた)、やはり客商売をしていたこともあってか、来ていただくんですね、昔のお客様が。
自分はほとんど知らない方ばかりなので、応対は母に任せたんだけれども、こうやって本人がいなくなったあとも弔いに来て頂けるというのは父の人徳・・・だなあ、と母と二人でしみじみ。
そして、これは今回よりむしろ葬儀の前後のほうがよりつよく感じたんだけれども
「お茶を出す お土産を持っていく」
という日本の風習には、それなりに意味があるんだなあ、というのを改めて実感。
こういった葬儀でも旅行でも―そういったときに、客のほうが土産を持っていく。
そして「まあお茶でも召し上がってください」と―。
こういったやり取りの中で、共通の話題を横糸に、お互いの近況を確認しあう。
いまのようなネットや携帯電話がない時代には、そういった直接のコミュニケーションしかなかったわけで。
そのための潤滑油が”おみやげ”―。
弔事でなければそれ自体が話題のネタにもなるし、来客が重なる家には、持ってきてもらったもので次のお客様をもてなすことができる。
共通の知人であれば
「○○さんが持ってきてくださったんですよ」
「ああ、お元気でやってらっしゃるんですか」
と近況の確認にもなる、と。
旅行などのお土産もそう。
「○○へ行ってきたので」
「ありがとうございます、ではお茶でもいかが?」
で四方山話をすることもできる。
こうやって、近しい人たちとのコミュニケーションを密にする、潤滑油になっていたんだなあ、と。
ただ、いまこの現代ではそういった濃密なコミュニケーションを必要とする場が、圧倒的に少なくなっている。
会社の人へお土産を買う、といったときに、今どれだけの人がそれによってその人の体験してきたことを共有する機会や場があるだろう?
そういうものがないし、そういうこと自体が面倒なことだ、という程度のコミュニケーションが標準とされているので、会社でのお土産などは”儀礼的・虚礼的”であると感じる、無駄な出費と感じている人がほとんどなんじゃなかろうか?
ある意味その感覚は正しい―これは職場がどうあるべきか、という話にもつながると思うが。
(そういった四方山話もできない職場というのは、ある面では不幸だとも思う)
時代に合わせて儀礼やコミュニケーションも変わっていく。
時代によって、それらを取り巻いていた環境そのものが変わってしまったから。
それは変わるべくして変わるべきものでもあろうし、一概に否定するべきものでもない。
ただし、だからといってこれまであった儀礼が、まったく理にかなっていない虚礼であるか、というとそうではない。
そこには、その時代その時代、それなりの理由があった。
だからそれを否定することではなく、時代に合わせて産みなおしてやることが、本当は現代に生きている自分たちのすべきことなんだろうな。
盆の飾り付けに呻吟しながら、そんなことを考えておりました―。

![魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語(限定生産版Blue-Ray)](https://www.thx-design.net/blog/wp-content/uploads/MdMg_Rebellion001-150x150.jpg)