願うる限り最高のコミック版になったと思う。
『ウルフガイ 12巻(完結)』
新月の満身創痍の中、人狼・犬神明は人類の悪霊が憑依した羽黒と最後の対決を迎える。
羽黒の振るう日本刀に指を飛ばされ、腕を切り落とされ、絶望の中に追い詰められる犬神明。
しかし、そこに彼を見つめる最愛の人・青鹿晶子の真摯な祈りが奇跡を起こす―。
ということで小説版『狼の紋章』のコミック化作品、完結編。
いやー一つの文句もないわ!
これはほんとよくやってくれたと思う。
加えてこのコミック版の最大の功績は、以前のレビューでも書いたが青鹿先生の立ち居地を再構築したこと。
原作でもこういう立ち居地ではあったとは思うんだけれども、ある種サーガの第一巻目ということもあって、どうしてもここまでの描写になってなかった。
もっとぶっちゃけていうと影が薄かったとさえいえたわけで。
いやーだから後半(11巻前後から)になるになればなるほど
青鹿先生の
なんと美しいことか
平井作品と女神論のことは前回のエントリで書いたと思うが、いや、これ間違いなくちゃんと女神化してるわ。
うーん、これはここで終わってしまう、というのもこのバージョンで青鹿先生の女神化が一段階梯が上がってしまったからかも(笑)。
そりゃ、これまでウルフの女神様だろうといわれてた虎4のいる世界へ分岐させんわな(爆笑)。
青鹿先生が見事ウルフガイ世界の虎4化を阻止したのか。
そう考えると、ちょっとだけ納得w
ただ、この青鹿先生のキャラクターとしてのウェイトを持って本編をやらないと、実はウルフガイの本当のテーマということでは完結してないともいえるかも。
この青鹿先生の存在感で、小説版の最終章『犬神明』読んだらきっと涙止まらんと思うな。
とにかく『狼の紋章』のコミック版としては、個人的に”決定版”を差し上げたい。
スタッフの皆様お疲れ様でした&ありがとうございました。
そして上記のように書きましたが、場所や媒体を変えてもいいので
是非このつづきを!!
<以下蛇足>
ということで、シリーズ未読の方には、なんのこっちゃ?な部分を残しつつ「打ち切りだよねー」的にも見えるラストではありますが、何度か書いているようにこの『狼の紋章』はウルフガイシリーズという大長編小説の第1巻目の部分だけをコミック化して、その部分が12巻で完結した、ということでもあります。
シリーズをざっと上げると
・狼の紋章
・狼の怨歌
・狼のレクイエム第一部(虎精の里)
・狼のレクイエム第二部(ブーステッドマン)
・黄金の少女 全5巻
・犬神明 全10巻(最終章)
この中でも中断を幾度かはさんでいるので、シリーズ作品としてのカラーが部分部分によって少し異なる。
(登場人物/世界はずっと同じです)
多くの既成の読者が「少年ウルフ」と呼んで一番頭に思い浮かべるのはおそらく「狼のレクイエム第二部」まで。ここで事実話がいったん途切れたような形になり、作品の発表自体も次の「黄金の少女」までかなり開いてたはず。
ここでかなり世界観のリセット、というか舞台が北米へ変わり、肝心の犬神明はこのシリーズでは出てきません。そしてこの前振りを踏まえた上で、最終章『犬神明』編があるわけです。
今回取り上げたコミック版12巻、ラストのほうは実は「狼の怨歌」からと思われる描写です。(犬神明が蘇生するシーン)
ただ若干異なっているのは、原作だともう少し老朽化した地方の精神病院的なところに秘密裏に拘束されているのが、このコミック版だと近代的な設備の整った最新の病院施設らしい、というところ。
そしてここでのポイントは、その施設らしいところに記載されている「phoenix organ」の文字。
”phoenix”=不死鳥ですね。
この不死鳥、というのが以降のウルフガイシリーズの大きなテーマとなる「不死鳥作戦(フェニックスオペレーション)」を示唆してます。
原作でははっきりいっちゃってますが、ようするにウルフガイシリーズの一つのテーマは、”人類悪”そしてその延長にある”人種差別”だったりします。
そういったレイシズムに則った選民主義者たち、そういった”世界の支配層”たちが不老不死を求めて、不死身人間でもある人狼達を追う。
それが”レクイエム”までの話の骨子になっていきます。
そこに出てくるのが、組織の処刑人でキャラクターとして絶大な存在感を放つ殺し屋・西城だったり、中国の諜報部隊員で自身も人狼たちと同じ秘密を持つ日本SF史最高最強のツンデレキャラクター虎4だったりします。
この西城と虎4は以降のシリーズの、ある意味もう一方の主役で、最終章である『犬神明』編でも重要な役割で登場します。
なかでも虎4は、狼のレクイエム以降、作者が彼女がいなくなってしまったことで続きが書けなくなったと述べているぐらい重要なキャラクター。
(実はこの一件があって、”女神論”というのも出てきた)
他にもいろいろ魅力的なキャラクターが出てくるんですが、残念ながらこのコミック版のチームでのそれが見られる可能性は・・・どうなんだろうなあ。
せめてレクイエムまではやってほしいんだけど・・・。
で、本コミック版最終巻でいいところ決めていた神さんですが(苦笑)、彼はこの「少年ウルフ」シリーズではあまりメインでの活躍はありません。
彼の活躍―というか彼的な人物の活躍をご覧になりたい方はいわゆる「アダルトウルフガイ」シリーズをお読みになるのがいいでしょう。
ここでは、性格・キャラクターはほぼこの神さんそのままの、だけど名前が「犬神明」という大人版・犬神明が登場します。
ただ、このアダルト犬神明は、このコミックにもなった少年ウルフとは別人物。
ちなみに平井作品には、まったく別の人物として4人の犬神明が存在します。(含む神さん)
この大人の犬神明が活躍する、いわゆるアダルトウルフガイシリーズもシリーズで出てますが、残念ながらこちらはシリーズ単独としては未完。
けれどエンターテイメント小説として非常に魅力的なシリーズです。
興味のある方は手を出してみるといいでしょう。
ただしアダルトウルフ・少年ウルフともに、現在は書籍での新刊は出ていないので、オークションでの中古か、e文庫から出ている電子書籍(iPhone版でのアプリとしても出ています)かが選択肢となるでしょう。
ちなみに青鹿先生はスピンオフ作品として『女神変生』という作品に主役で登場します。
ただしこれは以前にも書きましたが、平井作品のオールスター総出演のお祭り的作品なので、シリアスさを求める方には不向き。
ましてやエロシーンをお求めの変態紳士の皆様におかれましては、大きく肩を落とされるであろうことはお断りしておきますw
そしてこれも自分もまだ未読なんですが、最終的に”犬神明”と”青鹿晶子”が出てくるのは『幻魔大戦deep-トルテック』という幻魔シリーズの最終シリーズになります。
と、まあこんだけガイドしとけば大丈夫だろうw
あとは皆様お好きな線で、ウルフガイシリーズを堪能されることを。
そしてできれば、そういう読者が増えてコミック版が再開!
なんてことになってくれれば、嬉しいなあ・・・・・。
虎4・・・みたかった(;;)
※2015/2/1追記
先日の平井先生の訃報を受けて、先生の後期作品の簡単なガイドを作らせて頂きました。よろしければご参照ください。
※2022/06 標題の表記を統一、リンク切れを修


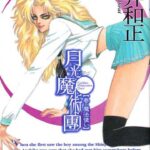

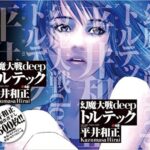

こんにちは。
今日アマゾンから届いた最終巻を読んでがっくり力が抜けてしましました。『完結』・・・なんですね、やはり。
現在「犬神明」シリーズ3巻を読み終えたところ。「ハルマゲドンシリーズ」と言うことで抵抗があったのです。すごく面白い!一気読みしたいのですが、全巻揃わないので先に進めない所です
平井先生の発想はすごいなあ・・・まさかクローン人間が出てくるとは・・・
少し異色な感じもしますが、やっぱりすごい「犬神明」シリーズ。以前と違うのは、作品の登場人物が楽観的な感じになった(少し漫画っぽい、虎4とか西城とか)辺りでしょうか?
漫画の続きを田端由秋さんのブログのねだっておきましたが、やっぱりダメですかねえ。
ごぶさたしております。
>今日アマゾンから届いた最終巻を読んでがっくり力が抜けてしましました。『完結』・・・なんですね、やはり。
確かに”完結”。だがしかしっ!
完結したのは『狼の紋章』なわけですよ!あの一冊だけなんですよ!!
なので、きっと、きっとどこかで続きのチャンスがっ!!!
・・・・・と無理に言い張ってみます(苦笑)。
で、ついに『犬神明』突入されたんですね。
個人的にはBeeと西城がアクション面を、犬神明が内省面を担当して物語が進んでいくように読みました。
西城好きなら、情けなくも愛おしい感じで彼のラストはけっこう気に入るんじゃないかと思います。
(けっこうほろっときました)
>以前と違うのは、作品の登場人物が楽観的な感じになった
これはものすごく鋭い指摘だと思います。
その傾向はどうも『地球樹の女神』あたりから出始めていて、『ボヘミアンガラスストリート』で顕著になります。
発表年を調べると、どうも黄金の少女→地球樹→犬神明(完結)→ボヘミアンガラスっぽい。
なのでその兆候が若干出てるのかもしれないですね。
ただ、そうでないと『犬神明』のラストのほうのエピソードは重すぎて、おそらくそれだけにフォーカスしてたら
筆が全く進まなかったんじゃないだろうかと思います。
そのせいか、以降の平井先生の作品けっこうはっちゃけてるんですよ(笑)。
『犬神明』で出し切ったのかもしません。
シリアスシリーズが好きだった人には不評なのかもしれませんが、個人的にはこの突き抜け方は好きです。
なにしろ、あの重く・苦しい幻魔がああいう転回の仕方をするとは誰も思わなかったと思うので。
個人的には「ボヘミアン~」が面白いと思えたら、以降の作品は全部OKだと思います。
チャンスがあれば読んでみて下さい―
・・・といいたいところですが、表面的にだけみちゃうと、あまり女性向けではないんですよね>ボヘミアン
ただ「神話」というキーワードで紐解くと、すごく納得のお話なんですが。
また「犬神明」の感想、お待ちしております。
はじめまして、こんばんわ。
古い記事へのコメントになりますが、ウルフガイ関連の話題はこちらでよろしいでしょうか?
つい先日犬神明を読み終わったのですが、ヤンチャン版の羽黒はウルフガイシリーズの様々なキャラの要素が盛り込まれていたのですね。
原作より戦闘のプロなのは西城、悪霊的カリスマで暴徒を率いる様はグレートセイタン、犬神明に対しお前に殺されれば本望と、病的な恋愛感情を募らせたのはアイスの律子と、パッと思いつくのでこれらのキャラが思い浮かびました。
あと最後の要素は、平井作品というより秋田・余湖コンビ作品屈指の糞ビッチ、龍子にも受け継がれましたね。まぁ本来この手の要素は女性キャラが持ってるのが当然なのですが(笑)
まだウルフガイシリーズしか読んでませんが、他の平井先生のキャラから拝借してる部分もあるのかな?
羽黒は新月時でさえ圧倒的に戦闘能力で劣る犬神明をほぼ負けまで追い詰めましたが、それも擬似狼男と化した千葉を倒したからだと思ってます。
そして「たまたま」千葉の輸血された人狼の血の効果が切れる頃に、「たまたま」刀を首に当てるという豪運を掴めたのも、上記様々な要素を持った、原作を遥かに超える怪物たからこそできたのだと思います。
原作版の1面ボス程度の羽黒だったら、日本刀を首筋に防がれ、そのまま無残に引き裂かれたかと(笑)
また今度は原作版についての話題ですが、犬神明を読んで分からない点があったので、そのことに関しての質問もこちらに書き込んでもよろしいでしょうか?
自分で謎を解くのが当然かもしれませんが、どうしても私の読解力では理解できなかった部分もあるため、よろしければご了承いただきたい次第です…
はじめまして。コメントありがとうございます。
こちらで宜しければどうぞ書き込んでいってください。>ウルフガイの話題
ヤンチャン版・羽黒のキャラクター造型に関するご指摘はなかなか興味深いですね。
いわれてみればそういった側面があると思います。気付いてなかった(笑)。
ただ個人的には脚本の田畑氏の手腕の部分が大きいのかなあと思っておりました。なにしろハリウッド映画的なものをかなり研究されてる方のようにお見受けしましたので。
(絵的な造型にマリリン・マンソン的なルックスを持ってきているのもそういうアレンジかなと思っておりました)
龍子≒律子、というのは当初からそんな感じはしていましたね。
というかあのショートエピソードをコミック版でやられると、アレンジの関係で博徳の誰かがエライ目にあわされやせんかとヒヤヒヤしてて、そっちの方が心配でしたが(^^;)
千葉を倒したからこそ得た自信・・・このあたりはヤンチャン版のいくつかあるアレンジ成功例の最たるものだと思います。このエピソードを入れたので仰るように羽黒くんは1面ボスから中ボスへ昇格したと思います(笑)。
このことを含め、羽黒のキャラクターを膨らませたのが、このヤンチャン版の成功のポイントの一つだったと思います。
原作版についての質問なども、宜しければどうぞ書き込んでください。
ただし当方、”不真面目な平井ファン”を自覚しておりますので(苦笑)、ご期待に沿えるかどうか・・・(--;)
同じ作品を面白く読めた読者同士としてなら、いつでも自分にお答えできるところはお返事させて頂きます。
どうぞおてやわらかに(笑)。
ご了承いただきありがとうございます。では早速質問及びそれに関する私の推測を書いてみますが、長いので項目ごとに分けたいと思います。
1.マーの正体とその目的はなんだったのか?
その正体は体を切り刻まれたロイスの意識だけが電脳空間に残った存在で、体はその都度用立てるってとこでしょうかね。
本編で犬神明の前に現れたのは、そのロイスの意識を青鹿先生のバイオニクスに注入した存在かと
そして不死鳥結社の壊滅どころか、人類の淘汰したりといった凶行に及んだのは、実験材料として非道に扱われ、
その結果人間に対して癒されることない憎しみを抱くようになったから?
犬神明にこだわるのもロイス本人だからで、人類を殆ど殺した後に、自分はまた息子と一緒に暮らせればいいと思ってそうだと感じました。例えそれが犬神明に見せたような近親相姦的なモノであっても・・・
あと虎2やBEEがその正体は虎4かもって言ってたが、これは全くの見当違いの推測でしたのかね?
2.BEEの当初の目的は、バイオニクスが人類に取って代わることだったのに、最終的に西城にその身を捧げようとしたのは何故?
マーの本体は、電脳空間から消滅することになるとのことだが、これはBEEがマーに勝利したからで、ただその際バイオニクスでも直らない深手を負ったため、
一緒に行動しているうちに愛が芽生えた西城のために死のうとした?
3.マーがエミリア達を殺したのは自分だと明かしたのは何故?
マーとしても自分が消えることを悟ってて、最後は犬神明とキム・アラーヤのために贈り物をしたくなったから?
4.ジム・パットンは何故不死鳥結社を作ったのか。本人的に白人以外が存在する地球は汚くて面白くないから?
また組織をにマーに譲り渡すようにしていたのに、結局反目しさらには自らを討たれるように仕向けたのはどういうことか。
あとそのマーを保護したのに、最終的に反目したのも性格が気に食わなくてかまうのに飽きたから?
5.グレートセイタンって結局なんだったのか?ジム・パットンのバイオニクスとのことだが、その割には余りにもやり方が非紳士的過ぎるような・・・
あとセイタンズ自体も不死鳥結社の下っ端みたいな存在で、目的は主に有色人種(場合によっては白人も)の虐殺、
本編中はそれに加え不死人間の捜索、及び接触した人間・地域への焼灼で間違いないか?
長くなりましたが、以上です。お手数ですが、もしよろしければお答えいただきたい次第です。
ちなみに某所でも同じ質問をしたことがあるのですが、1・2に関してはこの推測で間違いなさそうとの事でした。
1が合ってるとなると、つまりはマーの正体はロイス・イヌカミということになるのですが、その割には犬神明の決別に際しての態度は余りにも冷淡に過ぎると思いました。
自分の思い出の中の女神のような母親像に対し、現実に目の当たりにしたマーとして歪み果てた母親に幻滅したからもう2度と会いたくない、といった態度だったように見えましたので・・・
確かに優しかった頃のロイスと違ってその性格は暴君そのものでしたし、犬神明に見せた幻覚の内容から察するに、青鹿先生の体を使って近親相姦的な関係になってでも息子と一緒にいたいと望む様は、確かに昔のロイスを知る身としては我慢できないものがあるかと思います。
ただそうなってしまった原因は実験体として無残な目に遭わされたからであり、一番悪いのはロイスではなく不死鳥結社なのは間違いないです。なので、犬神明は母に対し優しくても良かったんじゃないかな~と思います。
もう2度と一緒に暮らせないのは変わらないにせよ、もう貴女と自分では人生の道が決定的に違うものになってしまったので、断腸の思いですが2度と会わないようにしましょう、とかそんな感じに。
また、あの決別の仕方では、美しかった頃のロイスがいつまでも心の中にいることになってしまって、本当の意味での母離れはできるのだろうか、とも思ってしまいます。歪んだ性格になっていたとしても、それを一方的に拒否するのでなく、その現実を受け入れ乗り越えるのが、あの場合必要だと思いましたので。
ご質問ありがとうございます、うわー膨大だ~(^^;)
さすがに全巻読み直してお答えするだけの時間が取れないので、覚えている範囲で書かせていただきます。
(間違いなどあった場合はごめんなさい)
まず個人的に感じているのは、最終章『犬神明編』の最深層にごろん、と転がっているのは母と子、父と子、そして父と母の相克の物語・・・だと自分は受け取っています。
マーの正体に関しては、ベースは確かにロイスだと思うのですが、”電脳化”された時点で”かつてロイスだった何者か”ー更にいうのなら、母親や受身の性である女性性の部分の怨念が結晶化したような存在ではないかと、自分は理解しました。
日本神話で言う”イザナミの尊”的な存在です。イザナミ様だからそりゃ全部滅ぼそうとしますわね(苦笑)。
(ロイスがそういう要素をふんだんに持っていた人物なのかは不明ですがーあったんでしょうね、結果からすると)
さらにいうと彼女(マー)は、家族関係を扱った臨床心理学系の本を読むと時々出てくる”グレートマザー”的な存在をもっと悪質化したものの様にも思います。”支配する母親”です。
だから”愛しい我が子”である犬神明を自分の手の内(寓意的な子宮内)に留めておこうとするのに対し、その絡みつく臍の緒を振り払って”自分”を取り戻そうとする、生まれ出ようとする子供―そういう物語が最終章である『犬神明』の裏のテーマではないか、と。
そして、そういう”乳離れ”しようとしている男の子を、”母親”から切り離し、広い世界へ誘い、連れ出すのが”父親”です、これが本作ではジム・パットン=ドードーでしょう。
(作中では彼の方が先に登場しますが、それ以前からマーは、ずっと犬神明を”監視”し続けていたと思いますので)
パットンのキャラクター造型はこの前後で平井作品でよく使われるようになったキーワードである”トリックスター”も兼ねていると思うので、そのあたりが複雑でわかりづらいキャラクターになっていると思います。
しかし、この一見ひょうげてつかみどころのない彼のキャラクターというのは、けっこう重要な意味を持っているのでは?と個人的には思っていまして。
なぜかというと、本作品の発表年度は1993~95年秋頃なんですね。
これはあくまで自分の仮説なのですが、95年というのは例のサリン事件があった年です。
そして、平井作品のもう一つの一大シリーズであった「幻魔大戦」シリーズ、この一連の作品の方向性からすると、平井先生はこの事件に凄く衝撃を受けられたんじゃないかと思うんです。何しろ作品のテーマが「真の救世主がこの世に現れたらどういう行動をしてゆくのか?」であり、かなり新興宗教的な描写と、きりきりとした禁欲的・ストイックなところへはまり込んでゆく可能性があった作風だったからです。(この点、表層的にだけ見れば、その言動というのは例の団体も似たようなことを表向きは言っているわけです)
このあたりの衝撃?反省?から、この前後を境にシリアスさや真面目さを煙に巻く、柔軟な心を持たないと扱いかねる”トリックスター”的なキャラクターが出てきているように自分には思えるのです。
真面目に、ものごとを表層的に、文字通りにしか捉えられない人間には全く理解できないキャラクター=トリックスターとして。
その意味で、パットン、グレートセイタン、ドードーというのはひょっとすると、書きながらその場その場でその性格付けが大きく変わっていったキャラクターなのかもしれません。
当初パットンは飄々として魅力的な、しかし正体の見えない、けれど真の悪人的な人物、ということでアダルトウルフガイシリーズ最後の方に出てきたメフィスト的な人物造型だったようにも、読もうと思えば読めます。
そしてそういった悪の複雑さをより深めるために、”わかりやすい”悪霊的なグレート・セイタンというキャラクターがあったのかも。そういう”明白な悪”を統べている人間がパットンのような”魅力的かつ複雑な人物”という意味でですね、そっちのほうがやばそうだと(笑)。
スタンダードなエンターテイメントだけの作劇でいくならこのままの方が盛り上がりやすいと思うのですが、そこで敢えてあのドードーが出てきた。
彼が二足歩行の巨大なウサギという姿をわざわざしている、というのもそういった根底的な認識の変化故に、出てきたのではないかとも思えます。
そういう作者側の心理的な変化がパットンという人物の行動・キャラクターの変化にも現れていたのではないか、と。
つまり「そういう四角四面な真面目さには飽き飽きする」という、トリックスター的な性格に変化したので、真面目さ、まともさをまぜっかえすことぐらいしか、あの曇った冬空のような”真面目さ”が覆い尽くした世界では、彼には楽しみがなくなっていたのではないでしょうか。それがパットンがマーに組織を渡し(飽きたので放り出し)、自分のやりたいようにやって、結果「自分で自分を嗤う」ような最後を、自ら選んだのではないか、と。
そういう複雑さを身をもって示すことで”世界の広さ”をこの場合の擬似的な息子の立場である、犬神明に示したのではないでしょうか。
逆にマーという存在は非常に”真面目”で”狭い”わけです、真面目で狭いので自分に敵対する存在をバカ正直に滅ぼそうとしているわけです。
そういう”真面目さ”の露呈の一つが、青鹿先生の似姿を使って犬神明の前に現れたことでしょうね。ここでもバカ正直なんです。
そしてこの時の青鹿先生の似姿というのは、いわゆるゲームなどにおける”アバター”だと思うんですね、マーにとっては単なるインターフェイスというか。いわば息子をあやすお人形のようなものだと思います。人形を使って自分が息子をあやしているかのような。息子が”いい子”にしていたらごほうびにあげますよ、的な意味で用意していたんじゃないでしょうか。
こういった性格はベースとなったロイスの遺した”怨念”の部分もあるかと思いますが、マーがあくまでも電脳ベースの存在であることも大きいと思います。
そして、そういった”狭さ”から一歩踏み出して、”複雑さ”=ある種の”人間性”を獲得しようとしていたのがBeeなのではないでしょうか。
Beeが西城を助けたのは、そういうマーにはない”複雑さ”を理解する、理解しようとする余地があったからーもっというと”面白がる”ことを彼女は知っていた。
だから、最後に自らが助からないかもしれない、とわかった時に、自分より弱弱しい存在である西城をー男女の愛情というよりペット的な愛着を持っていた存在である西城がー助かることがあれば”面白い”と思ったのかもしれません。
歪かもしれませんが、ある種の愛情ー慈愛に近いものかもしれませんね。
電脳ベースでありながら、彼女はそういう境地を手に入れた。
マーという存在が電脳の絶望を示したとすると、Beeは希望ーというか可能性を示したように思います。
ここは電脳だけでなく、母性とか女性性の部分の希望でもあるかもしれません。
そしてもう一人重要なのが、途中で”消失”してしまうエリー=エリノア・ハンターでしょう。
彼女は犬神明とあれだけ近い距離にありながら清い関係、かつ自分の全てを与えて彼を”導く”存在ーある意味この最終章を象徴する人物かもしれません。
彼女は彼を”独り立ち”させる存在、ある意味擬似的な、血縁を持たない母=聖母的な存在なのかもしれません。
そういった自分を信じてくれる存在に励まされて、男の子は男になっていく。
そういう構造もあるように、自分には読めました。
と、まあおそらく質問されたかった内容とあさっての回答が返ってきて、面目次第もないところですが、自分に正直にお答えすると、こういう回答になってしまいます。あしからずご了承くださいませ~。(^^;)
以上に含まれてないと思われる質問への回答は、以下に簡単に。
>虎2やBEEがその正体は虎4かもって言ってたが、これは全くの見当違いの推測でしたのかね?
これはおそらくマーの執念深さが、虎4のそれを感じさせたからではないかと思います。そういう部分で相似性があったということでしょう。
>3.マーがエミリア達を殺したのは自分だと明かしたのは何故?
これは仰るようにマーが最後に贈り物をしたかったから、ということでよいかと。
すこしは”母”の部分が残っていた、と自分的には解釈したいところです。
>4.ジム・パットンは何故不死鳥結社を作ったのか。
これも今となっては正確なところはわかりませんが、敢えて言うなら彼にとってはある種の”暇つぶし”だったのではないかと(苦笑)。
>本編中はそれに加え不死人間の捜索、及び接触した人間・地域への焼灼で間違いないか?
恐らくそれであっていると思います。結局グレートセイタンというのも、パットンという人格の一部を体現しているだけの”真面目”=”狭い”存在、アバターということでしょう。だから”真面目”にそういうことを実行する、と。
ゲームのコマとしては役に立ちますが、パットンを面白がらせるほどの存在ではなかったーだから後の方ではうっちゃらかされた、ということではないでしょうか。
>犬神明の決別に際しての態度は余りにも冷淡に過ぎると思いました。
これはある意味”憧れ”が強かったから故、からかと思います。
そして、これがないと上に書いたような意味では、彼は”乳離れ”出来ていない、ということになるんだと思います、なにせあれだけ母恋しで恋焦がれていたわけですから。
母との精神的な離別=独り立ちであるわけです。
そういう失望をともなう”乳離れ”をへて、彼はようやく自分の伴侶たるキムの元へ向かう、そういうことなのではないでしょうか。
キムは”母”の代わりにはなり得ない、そういう状態での選択でなければ意味がないように思うわけです。
・・・・・とまあ書きましたが、じつはこのあたり後続の作品を読むと、またこれ混乱するような描写がある作品※がありましてですね・・・・(^^;)
これについて書くとまたややこしくなるので、犬神明編、としてはここでは以上としておきます。
以上、とりあえずお答えさせて頂きました~。ふはー(^^;)
ご満足いただければよいのですが・・・。
※アウトラインだけ書いておくと
・月光魔術團の第三部では犬神明ほか大勢の本作のキャラクターが出てくる。
・その中にマーという少女がいるが、本作とどうもキャラクターが異なる(どちらかというとキムっぽい)
・月光魔術團がこの少年ウルフガイシリーズと同一の世界線かどうかは不明、かなり印象は異なる。
・幻魔大戦シリーズの最終章?『幻魔大戦deep-トルテック』にて犬神明が二人登場する。
・一人は神さんもしくはアダルト犬神明と思しき人物。
・もう一人は本作の犬神明と思しき人物。
・世界線は明らかに異なるが、世界線を移しまくる作品なので、同一世界・・・ともいえなくもない。
・そこで犬神明は青鹿晶子と再会する。
以上になります。読み終わってるんですけど、長すぎてまだ感想を記事として上げれてないんですよ。
(全部書こうとすると「アブダクションシリーズ」「幻魔大戦deep」「同トルテック」全部に目を通さなければいけなくなるので:汗)
ご回答ありがとうございます。
まず順を追って自分の感想を述べてみますと、ジム・パットンに関する回答は非常に納得のいくものがありました。
不死鳥結社を創ってマーに譲渡したのも、グレートセイタン及びセイタンズを放置してたのも、
本人的に面白そうだから始めてみたけど、最終的に飽きたからうっちゃらかす、というのが正にジム・パットン流のやり方という感じがしますw
マーに関してですが、どうも私は2人の出会いのシーンで、マー=ロイスということが頭から離れず、彼女の側に感情移入してたため、犬神明の態度に納得いかないものがあったのかもしれません。
ロイスがされたことは容易に想像が付くだろうし、同情して優しくしてもいいんじゃない、と。
なるほどロイス本人ではなく、ロイスであった何かに対し嫌悪感を抱くことにより、犬神明の母離れが完了するということであれば、
あの冷淡な態度も納得できます。母に似た何者かを相手にお互いの感情をぶつけ合うことで、母本人は死んだということを実感し独り立ちしていくことになる。
ここら辺は青鹿先生の体だけのクローンを見せ付けられることにより、彼女の死を何とか克服できたエピソードを彷彿とさせます。
想い出の中の存在からの独立といえば、BEEも同じことが言えるかもしれません。
自我が目覚め始めたばかりの頃は、虎4の記憶を元に犬神明を追い求めますが、実際会ってみると絶望から弱ってる姿を見て失望、
さらには不死人間はおセンチな性格ばかりと知り、自分はそんな連中と一緒ではないと、犬神明だけでなく自身の中の虎4からも独立を果たすことになったのだと思います。
ところで話はヤンチャン版の方に戻りますが、大筋は同じですが内容がまるで違うものになっているため、続きが気になって仕方ありませんねぇ。
まず青鹿先生についてですが、狼の紋章で原作より遥かに酷い目に遭っている事と、犬神明との関係がさらに深くなっていることを考えると、是非最後まで生き残ってもらいたいものです。
原作では、殺害の下手人であるドラッケンを赤の他人の西城が殺し、救うための努力も無駄に終わったため、空虚さしか残りませんでした。
ヤンチャン版の展開では、死んでも輪姦された様を世間に晒され弄ばれるという結果までは消えることはなく、
残された者にとって空虚なんて生易しいものではない、青鹿先生が死んでしまってなおその尊厳を汚し続ける有象無象に、身を引き裂かれるような憎悪が沸き起こるのではないでしょうか。
それこそ犬神明だけでなく、自称都会派の汚れたウルフである神明すら、不死鳥というか聖母結社の人類抹殺計画に加担しかねないほどに。
これで最後まで生きて犬神明と結ばれてハッピーエンドなら、2人で幸せにいられるのだから世間の悪評なんて気にならないってなると思うのですが…
羽黒も先に申したとおり、原作とは比べものにならない程の化物になっている上、犬神明の指を喰って擬似不死人間になった可能性もあるため、本当にあれで死んだか怪しいです。
あの演出だと魂まで喰われた、つまりは物理的にどうしようが復活のしようもなさそうに思えますが、それでもあの化物が死にっぱなしで終わるのか、とも思います。
また原作では最終的にマーなどの悪魔のごとき存在に駆逐された、「邪悪な人間」の象徴であることもポイントが高いです。
原作で最終的に一番力を持っていたのは、マー、BEE、そしてジム・パットン(ドードー)という、人間離れした悪魔王とか荒ぶる神とでも表現すべき連中だったため、
これらの存在に、バイオニクス化なりで能力はさらに化物に、人間的邪悪さもより増強された羽黒が噛んでくるのも面白いかもしれません。
また原作では1面ボス(笑)だったのが、あれ程強化されたのだから、後に出るキャラクターへの影響も計り知れないものがありそうです。
例えば西城なんかは、原作どおりのままだと羽黒に比べ小物扱いされかねないため、どういう能力・立ち位置になるか、とか。
最後に今回も長くなって失礼しました。質問にお答えいただいたこと、重ねてお礼申し上げます。
ご感想ありがとうございます。
自分の場合、あまりマー=ロイスとならなかったのは、ロイスはあまりその生前の描写がなく、ほとんど捕獲された時点で死んでたも同然と解釈して読んでいたからかもしれません。
マーにしても青鹿先生のクローンも、犬神明にとっては激しく精神を揺さぶられつつもやはり到底許容できるものではなかった、ということが逆に救いにつながったのかも知れないですね。
そういったことを含めて、読むたびに色々想像できる深さのあるエピソードだと思います、最終章は特に。
ヤンチャン版に関しては、例えて言うならば、昔の大ヒット曲を現代の力のあるアーティストがアレンジしなおしたリミックス曲のような感じかもしれませんね。自分も是非このスタッフでの全シリーズ完全マンガ化は望みたいところですが・・・なかなか難しいだろうなあ・・・。
青鹿先生の被った最悪の状況に対する怒り、というのは確かに仰る通りなんですが、ここが面白い・・・というと言葉が悪いんですが、その原因を犬神明は自身の持つ災厄性にある、と捉えているところがこの作品の妙味のような気はします。
普通は仰られるとおりに、その原因を他者(CIAだとか人類そのものだとか)に向けて暴発させそうなものなんですが、迎えた結末があまりにも最悪過ぎると、もうそこへ至らせてしまった自身を責めるしかない、というか。
(個人的には『犬神明』編冒頭の岩山のシーンは不死者でありながら精神的に”自殺”しようとしていた描写だと思います)
何度か出てくる人狼たちを占うゾラーさんのシーンは、そのあたりを示唆しているようにも自分には読めました。
個人的にこのヤンチャン版で以降が製作されるなら、やはりいちばん見て見たいのは、西城と虎4ですね。
西城はご指摘の通り羽黒君中ボス化で描写の難しいところもあると思いますが、彼は悪は悪でも”人間の範疇”にとどまった良くも悪くも”人間代表”みたいな感じで出てきてくれればなあ、と思ったりします。
悪霊のようなわけの分からないものに頼るのでなく、自信の力と能力を磨きあげて戦う「プロ」としての姿が見たいです。
虎4はもうただただその姿が動いているところが見たい、もうほんとそれだけです(笑)。
あのスタッフで例のアパートを何度も何度も思い出しながら引き払うシーン見たら確実に泣ける自信があります(笑)。
ちなみにあまりちらつかせるのもどうかと思うのですが、前回にも書いたように『幻魔大戦deepトルテック』に出てくる犬神明と青鹿先生は作品自体からすると枝葉のエピソードとして、明確な描写は避けられていますが、仰られている”最後まで生きて犬神明と結ばれてハッピーエンド”に限りなく近い状態です。
高い本かつ別シリーズになるので積極的にはオススメできないのですが、どうしても続編が待ちきれずしんぼうたまらん!?というのであれば、手を出されてもよいかもしれません。
(前作に当たる『幻魔大戦deep』のほうがiPhoneアプリ化で刊行され始めているのでそのうち電子版が出る可能性あると思います)
青鹿先生は幻魔大戦シリーズの主人公である東丈の私設秘書として、ウルフガイ本編に比べるとはるかに平和で人道的な立場を保証されて登場しています(笑)。
発表はヤンチャン版に先行していると思うのですが、自分はヤンチャン版の発表後に読んだので、ヤンチャン版の青鹿先生のビジュアルでイメージして読めたため「ああ、青鹿先生幸せでよかったなあ~!?」とひとり悦に入っておりました(^^;)
ただこのヤンチャン版的なニュアンスが好みでいらっしゃるのなら、未読なら先にアダルトウルフガイシリーズをお読みになるといいかもしれませんね。
完結していないのが悔やまれますが、こちらのほうがよりエンターテイメント色が強く、かつ並行世界の神さん?的な存在であるアダルトウルフはやはりすこぶる魅力的なキャラクターです。
こういったある作品について深く突っ込んだ話をする機会というのは普段なかなかないことなので、楽しませて頂きました
。
またなにかあれば遠慮なく書き込みして頂ければ。
ありがとうございました(^^)
紛らわしい書き方をして申し訳なかったのですが、前回の最後ってのはあくまであの分の中で最後という意味でした・・・
ただ、あまり長文ばかり書くのも悪いので、長文感想は次回、最後の質問内容次第では今回で今の所終わらせたいと思います。
文章のつながりを意識すると長くなりそうなため、ブツ切り感覚になりますが、ご容赦を。
平井和正先生の性癖についてですが、この人ってもしかして・・・百合好き!?
キム・アラーヤとエミリアの関係がどうも甘ったるいと思えたというか。
これだけだったら変な疑いは持つはずはないのですが、どうも別作品でJC同士が絡む描写があるとのため、なんか怪しいなぁ、と(笑)
またウルフガイシリーズと同時に、80年代後半~90年代中盤に連載された、とある女戦士のコンビが活躍するラノベを読んでいたのですが、
こちらは女主人公コンビが四六時中一緒になって行動しているけど、そういう雰囲気は全くありませんでした。
まぁ当時はオタ向け作品と言えど、女揃えば百合百合しいという昨今のような風潮はなかったのですが、
キム&エミリアのコンビはどちらかと言うと今風かなぁと思ったので(笑)
ちなみにエリーの元ルームメイトのカレンは、現実にいそうな乱暴なレズビアン女という感じで、百合がどうのという発想には結びつきませんでした。
話は変わってヤンチャン版について、青鹿先生の無残な描写が余りにもポルノとして出来が良かったため、
一部で(物凄く下品な言い方をすれば)爆乳女教師凌辱漫画として捉えられてしまった向きもあるそうで、製作陣が伝えたかったであろう
「原作もテーマにしてきた人間の邪悪さについて」が伝わりきれてないようで残念でなりません。
ただこれは完全に邪推ですが、9巻のレビューで「羽黒と犬神の2ショットはどう考えても腐なみなさまへのサービスカットでしょう(苦笑)」と仰っていましたが(笑)、
青鹿先生の描写ももしかしたらそういう下世話な受けを狙って描いたのかもしれません。もしそうだとしたら、製作陣の皆様にも責任がないとも言い切れないかなぁ。
原作では羽黒に強姦されたシーンは書かれませんでしたが、ヤンチャン版も具体的な内容は描かず、
「汚された」「そしてそれをネットに流された」という結果だけを強調する描写の方が、あらぬ誤解を受けることもなかったんじゃないかな~、とも思いました。
腐向け描写といえばこれは余談ですが、鹿目まどか役などでお馴染みの悠木碧さんは、かなり濃いオタかつ腐女子で有名ですが(笑)、
こういう人たちも本当に羽黒×犬神明の801妄想で萌えられるかどうか気になります。
腐女子と言っても青鹿先生と同じ女性なんだから、女の敵の羽黒に萌えることなどできるのだろうか・・・
青鹿先生は原作の女性読者から一番嫌われているとの事ですが、思いっきり偏見ですが女性のオタクって怖いなぁと思ってしまいました。
そりゃ男のキモオタだって、アイドルだの声優だの二次の萌キャラに恋人がいるとなったら発狂する奴もいます。
ただ青鹿先生のような悲惨な目にばかり遭うキャラに、自分にとっての萌キャラを取られたってだけで憎むなんて、次元が違うわ、と。
原作連載及び復刊当時の少女たちは、ヤンチャン版で更に酷い目に遭う青鹿先生を見たとして、
こんな可哀想なキャラを憎むなんて当時の自分は若かったと思うか、ザマァみろと思うか、
それとも犬神明と結ばれる青鹿晶子に相も変わらずヘイトを募らせるのか・・・
原作未読の方がヤンチャン版をレビューされていたのですが、もう一つのテーマは
「犬神明や羽黒のような強烈な生を前にして己の自意識を打ち壊され、自分の矮小さに絶望していく人間たちのドラマ」
と仰っていて、とても鋭いご指摘だと思いました。
思えば原作では木村紀子・委員長・田所教師といった「普通の人」にそこまで焦点が当てられることはなく、平井先生ご自身は、
「読者に彼らの事が気になる人がいるが何故だろう」という旨を仰っていました。
その後の狼の怨歌以降では、いわゆる「普通の人」が激減していきましたしね。
田畑先生はそんな当時の読者の気持ちを代弁するため、博徳学園のその他生徒・教師たちにスポットを当てたのかもしれません。
青鹿先生が汚されそれが大々的に報道された件で、彼らは深いトラウマを負いましたが、もし続編があれば何らかの救済措置がほしいところです。
特に自分のせいで青鹿先生だとバレたと思い込んでる委員長は・・・
まぁあの事件をドヤ顔で触れ回ってた丸山君は不幸になればいいし、糞ビッチの龍子はそのまま狂気のビッチ街道を歩めばいいと思うよw
また偽一休さんはエロ画像目当てでアクセスする変態紳士諸君を揶揄していらっしゃいましたが(笑)、
上記レビューをされた方はこちらのブログはお読みではありませんが、性癖的に思いっきりその層に当てはまります。
ただ8巻以降の展開を読んで、余りの無残さに(文章中で)号泣し、「残酷だけど、美しい生の物語」とも評価していらっしゃいました。
願わくば他の変態紳士の皆様も、ウルフガイにエロ以外の何かを感じ取っていただければ・・・
高橋留美子先生はウルフガイの大ファンでイラストも描いているとのことですが、この人の絵って明るすぎてウルフガイというイメージじゃないなぁ。
OVAのウルフガイは、クレジットには載っていなくとも高橋先生がキャラ原画を提供したものとのことですが、
ttp://www.youtube.com/watch?v=kiMGvNIYC8U
な ん と い う コ レ ジャ ナ イ 感
まぁ歌からしてポップ過ぎですが、まずこれを見た人は、明るく楽しく激しい青春アクション作品だと誤解してしまうんじゃないでしょうかw
ただ私は高橋留美子先生の作品を殆ど読んだことも観たこともないため、もし藤子F先生のごとく裏ではエゲつない作品を描いており、
ウルフガイを描く資格充分!ということならごめんなさい・・・
どうも、ヤンチャン版の絵が個人的に最高過ぎたため、他を受け入れらない、狭い思考回路に陥ってしまったかもしれません。
また泉谷あゆみ先生は古くからのウルフガイファンから煙たがられがちなそうですが、
私としてはトクマノベルズ版のいかにも90年代ジュブナイル小説といった絵柄は嫌いじゃないし、イメージも合ってると思いました。
あぁでも、高橋先生は虎4を女神扱いしてるだけあって、彼女については合ってると思いました。
私としては虎4って乱馬のシャンプーをエゲつなくしたイメージがあるのでw
ご紹介してくださった、各種関連書籍についてですが多くが電子書籍かぁ・・・
当方貧乏&本を置くスペースもないため、基本的に小説などは図書館で借りてるのですが、電子書籍となるとその方法も使えないのが残念。
さらには作品の一部を買ったら全部買い揃えなければ気が済まない性格のため、3部だけが電子書籍の月光魔術團は購入は遠くなりそうです・・・
ということで、まずは古い故に図書館に置いてあるアダルトウルフガイから手を出してみます。情報のご提供、ありがとうございました。
また今回はこれで最後の質問になりますが、偽一休さんは
サンデーで連載していた「うしおととら」「からくりサーカス」「ARMS」、ジャンプで連載していた「ダイの大冒険」、旧スクウェアから発売された「クロノクロス」、
これらの作品はご存知でしょうか?
個人的にウルフガイとこれらの間でちょっと考えることがあったので、気になって質問したい次第です。
ウルフガイに直接関係ない上、個人的なことなので、もしご存知でなければ先に述べたとおり、長文の投稿は今の所これで最後にしたいと思います。
またご好意に甘えるようで悪いのですが、また相手をしてもらえれば嬉しいです。それでは失礼します。
あ、まだ続きがありましたか。失礼しました(^^;)
>平井和正先生の性癖についてですが
いえ、単なる「どすけべえ」なだけだと思いますよ?(ほめ言葉)
というか、すごおおおおく「女(の子)好き」ということかと思います。
ようするにかわいい・綺麗な女の子のエロティックな姿が大好きといいますか。私?私も大好きです(自爆)
個人的に凄いなあと思うのは、還暦を過ぎてこういうエネルギーを作品に注ぎ込めるというのは本当に素晴らしい。
加えて特に最近の作品により顕著なんですけど、その「すけべえ」さというのがあまり陰湿でない、というのが良いですね。
菊池秀行氏が好んで書きそうなものとは正反対といえばよいでしょうか。
もちろん作中に話の流れから必然的なそういうシーンがなくはないのですが、もの凄くウェイトが軽いです。
地球樹の女神あたりからその傾向が出始めているように思いますが、近作はほとんどそのあたり・・・百合だろうがインセストタブーだろうが・・・のリミッター外れまくってるように思います。
昔の硬い平井作品だけを想像すると面食らう方は多いのではないかと思います。
>ポルノとして出来が良かったため、
これはそう捉えられているんだろうな、という気がしていました。そして製作側の責任が・・・とのご指摘ありましたが、そう思う反面、ある意味製作側は確信犯的な部分もあったのではないかと自分は考えています。
なぜかというと、原作、作画、作監、加えて原作という4つのクレジットが入って、かつお世辞にも発行部数が良好とはいえない秋田書店のマイナー青年誌に掲載なわけです。当然マネタイズ・・・といいますか、なんらかの形でインカムに結び付けないと経費自体がまかなえないわけです。にもかかわらず単純なアクション漫画にするわけにもいかない。
で、原作のテーマ性・プロットと矛盾を生じさせず、かつある程度の集客・話題性を作る、となるとああいうブーストが消去法で出てきてもおかしくはないと思います。
(個人的に現在出版界の状況を考えるに、秋田書店だとそれぐらいぎりぎりなんじゃないかと想像します)
なので仰るように「ネットに流された」的な結果だけを強調する、というのはある意味正統な演出かと思いますが、あえてああした側面はあると思います。(その描写の是非はともかく)
そうしておけば逆に言うと、ああいったひどい描写を低減させてディレクターズカット的な編集もあとからやろうと思えば出来るという読みもあったんじゃないですかね。
青鹿先生が女性に嫌われている、というのはある意味腐云々抜きにして、意志表示が少ないキャラクターだからではないかと思います。(原作版は特に)
女性側から見て、自分のモデルケースになるような気風のよさがあるわけでもなく、なのに美貌とかスタイルとかそういう努力ではどうにもならないものを与えられ、にもかかわらず自分で積極的になにをするわけでもないのにあたしの明君をあんなにベタぼれさせて!きーっ!?くやしー!?なにこのアマ!?・・・というところじゃないでしょうかねえ(苦笑)。
もともと腐女子とかBLの文化も、そういう女性性のもつ独特の嫉妬から開放されて恋愛モノを楽しみたいから発生した、というような話は、大御所の女性マンガ家や女性作家のインタビューなどで読んだような記憶があります。
個人的には変態紳士の皆様であろうと、腐女子の皆様であろうと、紳士・淑女たるマナーを守って(爆)脳内のうちにその妄想を留めておかれるのであれば、それはそれでけっこうだと思うんですよ。
しかし作品そのものを愛しもせず、その先にある物語本来のテーマ性に触れようともしないまま、キャラクターをただもてあそぶだけならば、その人たちは紳士・淑女ではなく、ただのポルノ好きな変態漁色家にすぎない、とは思います。
ここは腐っても「愛だろ、愛」ということで一つ(苦笑)。
ただ、これだけネット上にえげつないありとあらゆるポルノグラフィがへーきで転がってる時代では、そういった矜持を保つというのはむづかしいのかもしれませんね。
>原作未読の方がヤンチャン版をレビューされていたのですが、もう一つのテーマは
「犬神明や羽黒のような強烈な生を前にして己の自意識を打ち壊され、自分の矮小さに絶望していく人間たちのドラマ」
これはすごくよい見方だと思います。たしかにそういった側面も意識して製作側はアレンジもしてたんじゃないでしょうか。ダイの大冒険を出してらっしゃいましたが、詳しくないのですがあの作品で言えばポップ・・・でしたっけ?あの魔法使いの男の子の立場のようなものですかね(彼は最後凄く成長したようですが)
>高橋留美子先生
確かに自分もウルフガイに関しては、高橋先生の描くイメージはすこしピンと来ませんでした。
ただし、機会があれば『るーみっくわーるど』の第1巻や『人魚の森』シリーズはお読みになることをオススメします。
高橋先生の中に流れる平井作品的な系譜を感じることが出来ると思います。
ちなみに自分もさほど高橋作品は詳しくはありません。
>電子書籍かぁ・・・
>当方貧乏&本を置くスペースもないため、
このあたりはそれぞれご事情あるかと思いますので、言えることだけ。
自分も本に関してはけっこうそろえてしまう方なので、ただでさえ狭い6畳間が本だらけになっておりまして、いやおう無しに(スペースを確保すべく)電子書籍へ移行できるものは移行しようとしている最中です。
特にコミックなどは使用するデバイスの解像度に左右されるので難しいところですが、基本小説などの文字ベースの作品は、いまあるデバイス類で十二分に実用になります。
自分はiPadで最近の平井作品をおそらく50冊弱ぐらい読みましたが、ある意味紙の本よりも読みやすいぐらいでした。なにより場所をとりません!50冊だろうが100冊だろうがメモリの容量の限り1台のデバイスに詰め込めます。
ということで、積極的にとは申しませんが、チャンスがあれば是非一度お試しになられることをオススメします。
入門機であれば1万円を切っているものもありますので。
>サンデーで連載していた「うしおととら」「からくりサーカス」「ARMS」、ジャンプで連載していた「ダイの大冒険」、旧スクウェアから発売された「クロノクロス」、
藤田先生の作品は上にあげられているものは未読ですが、講談社から出ている短編集を数冊読んだことがあり、凄く力のある作家さんだなあという認識です。一時期手を出すべきかどうか検討したんですが、どのシリーズも膨大な巻数なので早々にあきらめました(笑)。
あとの作品に関しては残念ながら存じ上げません。
今回に関しては、こんなところで。
またなにかあれば、どーぞご遠慮なく(笑)。
ご回答ありがとうございます。私の挙げた作品は触れていないとの事なので、これらについて前回以上の言及は避けたいと存じます。
ドスケベというのは平井先生に限らず同性愛者以外の男性全員の共通事項ですが(笑)、
平井先生及びその息子くらいまでの年齢の作家の方々って、レズ描写が控えめのように思えたためそれがこの人の特殊性かなぁと思えました。
日本の二次オタ文化の発祥とさえ言える手塚先生も、ロボ娘だのケモノだのBLだの散々その他異端な性愛描写は描いても、百合はなかったように思えます。
菊池秀行先生を例に出していらっしゃいましたが、その盟友である夢枕獏先生はその格闘描写で
「半裸の鍛え抜かれた男が(寝技などで)でネチっこく絡み合うなんて、なんていやらしいんだ」
的なことを書いており、レズはどうでもよくてホモの方に興味があるんじゃないかと思えますw
百合専門の話以外にその手の描写が増えたのは、大体00年代以降という割と最近の話じゃないかなぁ。
ただこれも私の認識不足で、90年代以前も百合作品は結構あったぜ!ということならごめんなさい。
ヤンチャン版のポルノ描写も売るためにそうした可能性は大いにアリ、かぁ・・・
プロとして出版する以上、漫画は作品であると同時に商品ですからそれも批判される謂れのないことかもしれません。
あとディレクターズカットという言葉で思いついたのですが、もしアニメ化するとしたら(残念ながらまずないでしょうが)、
本放送では問題のシーンはカットで、ディスク化に際して原作を完全再現したよ!むしろ動きがついた分、青鹿先生の爆乳も揺れまくりでさらにエロくなってるから紳士の皆様は要チェックだよ!
って感じで下衆な売り方をしてくれたら、いっそ清々しいくらいかもしれません(笑)
ただ、田畑&余湖両先生コンビはもしかしてウルフガイでエロについて味をしめた・コツを掴んだのかもしれません。
前作のアクメツはSFアクションだけでなく、日本の現在の政治という重い話題を扱っていたためエロはなかったのですが、
次回作の真マジンガーはまだ詳しく知らないのですが、ヒロインがロボットに登場する際股間にプラグのようなのを突っ込んだり、別のヒロインは青鹿先生ほどじゃないけど爆乳のうえピッチリしたスーツをまとうという外見なので(笑)
それでは今までお付き合いしていただき、ありがとうございました。こちらこそまた何かありましたらお邪魔するかもしれませんが、その際はよろしくお願いします。
別の記事との連投失礼します。
以前青鹿先生に対する女性ファンの評価について言及しましたが、ヘイトの標的になってしまったことについては時代性もありそうだと思いました。
声優の悠木碧さんについても述べましたけど、今時の腐女子・女オタクのというのは、この人のようにキャラ萌えが多岐に渡る人が主流と聞きました。
具体的にはBLだけじゃなく女の子も好きだし、当然百合やノーマルカップリングもいける、下手すればゲイ向けアダルトビデオをコメディ感覚で見たりとか。
まぁ、最後のは流石に悠木さんやごく一部の方々じゃないと無理だと思いますが(笑)
ともあれステレオタイプ的に「イケメン以外は萌えられんから、それ以外の男と女は不要、気に食わない女がヒーローと結ばれるとかマジムカツクし!」なんていうのは時代遅れ、
またそんな意見を強弁すれば、腐女子でも最下層のゴキ腐リ扱いすらされかねないそうです。
それ故、ヤンチャン版からウルフガイを知った女性読者は、70年代当時のように青鹿先生を嫌ったりはしないんじゃないかなぁ、と思いました。
それに原作より存在感が濃くなって言動もアグレッシブになったため、嫌われる理由の一つである、特に目立った活躍もしてないくせに犬神明の愛を独り占め、って感じはなくなりましたしね。
とまぁ語りましたけど、そもそもこの漫画の女性読者は少なさそうというのが悲しいところですが・・・
私は女性だけど、ウルフガイシリーズで一番好きなヒロインは青鹿晶子です。
女性の読者に嫌われているとは最近まで知らなかったです。
同じタイプの杉村由紀、るみな、五鈴は苦手なのに。
多分、私は一番最初にレクイエムから読んだからでしょうね。
少年犬神明にこんなに愛される女性はいないし、他のどの女も青鹿晶子には勝てないです。
>飲マスクさん
時代性というのは鋭い指摘だと思います。BLどころかやおいなどという言葉すらなかった発表当時と、良くも悪くもそういった本来あだ花である文化が百花繚乱のいま現在では、女性の受動性という点でも雲泥の差があるように思います。ましてやこのヤンチャン版と原作では(キャラクターの核心は別として)表面的なディティールがかなり違うように思いますし。
しかし悠木碧さんてそんなに腐れ(失礼)なんですかw
>ほとりさん
女性読者に嫌われている云々、というのは自分も詳しくは知らないのですが、平井先生のエッセイなどを見ると断片的にそういった感じのことは書かれていましたね。(どの程度なのかは不明です)
あとはほんとに読まれたタイミング、というかそのキャラに感情移入できるかどうか、というところじゃないでしょうか。
自分は本とは”出会う”タイミングがある、と思ってる人間なんですが、本の中の登場人物とも”出会う”タイミングがあるかどうかなのかな、と思っています。その人にとって。
ウルフガイとは外れますが、自分は嫌われキャラでいうと久保陽子(幻魔大戦)が好きなんですよ。
なんというか哀れで。最近のハーレム路線(苦笑)の平井作品なら報われてたろうになあ・・・(^^;)
(ご存じない場合はスルーしてくださってけっこうですw)
私の意見ですけれど、青鹿晶子が嫌いな女子は「少女」であったからかなと思っています。
まだ穢れていない少女らは穢れを受け入れたくなかったのだろうと、しかし「女」となり「母」になったであろう現在は青鹿晶子の受けた地獄の痛みが分かってあげられると思っています。
陽子さん、懐かしいですね(中3の頃平井さんの作品は、角川とか徳間ものは全て読んでました)
すみません!私は幻魔漬けになる前から苦手でした。
自分もだから分かるんですよね、少女のこずるさが(*^_^*)
郁江みたいに同情はしていないです。
本当にみちるか人美あたりに矯正して欲しかったですね。
ああ、なるほど~少女ならではの潔癖さということですか。そのあたり女性としての経験値で受ける印象が全く違ってくるのかもしれないですね。
あ、それでも久保陽子はNGですか―いや、だからこそかな(笑)。
個人的には(その動機は不純であれ)東丈の道筋を開いたひとりではあると思ってたので、業が深い分、どこかでいい方向にごろんと”転んで”くれることを期待してたのですが。『ボヘミアンガラスストリート』あたりなら絶対こんなにねじくれるところまで行かなかったと思うんですけどね(苦笑)。
(意外なことになぜか伊福部ちゃんあたりを想像します)
確かに人美さんあたりなら「もう、しょうがないなー!」とか言いながらしっかり矯正してくれそう。なにげに人美さんは平井ヒロインの陽性な部分の集大成のような気がしています。
自分も角川・徳間の文庫で一通り読んだ口です。
>ほとりさん
遅レスの上ブログ主さんでもないのに横レス失礼します。
私が青鹿先生が女性読書から嫌われてると知ったのは、徳間書店ハードカバー版狼の怨歌のあとがきからでした。
当時の少女たちが、青鹿先生の被ってしまった穢れを受け入れられずに、またそれにより発生した心の闇をどう処理すればいいか分からず、キャラ叩きに走ってしまったというのも納得です。
こちらとしては青鹿先生ほど悲惨な目に遭ったキャラが、主人公の愛を独り占めにしたというだけで嫌われる(それも汚した張本人たちより)というのが非常にショッキングでした。
またそこまでショックを受けた理由は、原作よりヤングチャンピオン版を先に読んだためです。
原作でも確かに非業の死をとげますが、SF・ファンタジーでそういう運命にあるキャラはそこまで珍しくはないと思います。
余談ですが、神明が犬神明に対し「オタクより不幸な奴なんていくらでもいる」と叱咤しましたが、これは亡き青鹿先生についても言及してるように思えます。
神明=アダルトの犬神明だとすると、アダルトウルフガイには青鹿先生よりある意味さらに悲惨な死に方をした女性たちもいましたから・・・
流石に望まぬ妊娠は悲劇過ぎですが、その際には廃人同然になっており自身に起きた悲劇を認識すらできなくなっていたため、ある意味ではアダルトのヒロインたちよりは悲惨さはマシと言えるかもしれません・・・
翻ってヤングチャンピオン版ですが、こちらは汚されたという事実が日本中に知れ渡り社会的に殺されてしまいます。これは最早本当に死ぬより辛いと言えそうですが、ヒロインとしてここまでされてしまったキャラは、先述のアダルトウルフガイどころか他の作家の方々の作品にも滅多にいないと思います。
こちらのブログ主さんは「本とは出会ったタイミングが重要」と仰っていましたが、一番最初に出会った青鹿晶子がヤングチャンピオン版だったため、嫌われるて知ってショックを受けたと自分でも思います。
アダルトウルフガイも読み終わっての感想ですが、原作の犬神明たちはヤンチャン版に比べて随分性格が丸いなと思いました。
原作の少年犬神明は殺人を忌避しあの羽黒を殺したことすら後悔してました。
アダルトの犬神明は作品の性質上、殺人・破壊行為に少年ほど抵抗はないものの、そこにヤンチャン版で羽黒やその一味に向けたような明確な憎悪・殺意はなかったように思えます。
漫画という視覚的に直接的に訴えてくる媒体では、原作の犬神明たちは大人しすぎると判断しての改変かもしれませんね。
またこれもアダルトとヤンチャン版を比較しての感想ですが、
「18禁やエロ描写満載の作品より、そうでない作品のエロの方がそそらる」
ということです。非常に下世話な話で恐縮ですが・・・
まずアダルトは濡れ場が多くて「またか」という感想は否めませんでしたw
ただ、ヤンチャン版も例のシーンに行き着くまでエロはなかったかと言えば当然違います。
青鹿先生の色気ムンムンな容姿や悲惨な過去はエロティックですが、それらをあまり露骨にならないようギリギリまで溜めて、あの場で爆発させたことで「常に性描写をしてる作品には出せないエロス」を表現しえたのだと思います。
ただしシチュエーションの悲惨さを思えば、エロいからって単純に喜べるものではありませんが・・・
話は変わりますが、以前のヤンチャン版の青鹿先生のごとく社会的に殺されたキャラはいないってのは間違いでした。早とちりして情けない・・・
それに絡めての話ですが、ヤンチャン版で青鹿先生を襲った悲劇はアダルトの「虎よ!虎よ!」を参考にしたように思いました。
青鹿先生は辛うじて救いがありましたが、もし犬神が救出に失敗し羽黒に殺されたら、あのエピソードの緒方クミと同じような目に遭ったのではないかと思えてしまいます。
他者に屈辱を与えることに快感を得た羽黒は、用ずみになった青鹿先生を殺すなんて「お優しい」ことをしそうにないですし、舎弟の中には「飼いたい」という奴もいるだろうが、それも許さず路頭に迷う様を見てニヤニヤしてそう・・・
ただ一応救われたといっても、仮に続編が出る場合、展開次第では緒方クミのごとくになってしまう可能性も捨てきれなさそうです。
強姦された女性が周囲の偏見・無理解に苦しめられるいわゆる「セカンドレイプ」の描写は、こう言ってはなんですが、作劇をする上で有用な素材だと思いますので、このネタを活かさないとは考えられません・・・
続編は切に望みますが、こういった描写もあり得ると考えると複雑です。まぁ、一読者の被害妄想的な思い込みかもしれませんが・・・
もし出た場合は、原作にはなかった犬神明との愛のあるセックスシーンも描いてほしいと思います。
以上になります。また長文になって申し訳ございません。言い訳になってしまいますが、ウルフガイシリーズ別の側面を見て、また新たな刺激を得てしまったもので・・・
お久しぶりです。コメントありがとうございます。
アダルトウルフガイのほうも読了されたようでなによりです(^^)
いろいろとディティールが違って見えるところあったようですが、やはりヤンチャン版はコミック作品ならではのアレンジがされているのもあると思いますが、時代性ということもあるんじゃないかと。
なんせ原作が発表された年数を考えると、さすがに人の倫理観のようなもの自体が、大きく違ってきてしまっているように思います。
話題にして頂いている性描写なんかその典型例でしょうね。原作発表当時だったらこんなの発禁どころか逮捕者出ていてもおかしくないでしょう。
これは果たして良いことなのか悪いことなのか・・・悩ましい問題ではあります(^^;)
これは性描写に限らず実は暴力描写に関してもそうですよね。きょうたまたまガンダムの冨野監督が進撃の巨人について言及されているメルマガのバックナンバーを読んだのですが、そういういろんな意味で”剥きだし”の描写はどうなのか?的なことを仰っていました。
ヤンチャン版少年ウルフの描写はコントロールされているとはいえ、あそこまで本当に必要だったか?という話にはなりますね。ただ羽黒のブーストにしてもそうですがあそこまでやらないと、いまのある種刺激に慣らされて不感症になってしまっている我々の時代にはセカンドレイプ等含め”真の暴力”というテーマが通らなかったのかもしれません。
アダルトウルフのほうに話を戻すと少年ウルフと違って、実はあまり暴力と結びついた性描写というのが少ないんですよね。このあたりそれぞれ作品の主役の性格の陰陽が大きいのかも(苦笑)。彼は間違いなく艶福家ですw
>まずアダルトは濡れ場が多くて「またか」という感想は否めませんでしたw
とありましたが、このあたり少年ウルフの世界でのアダルトウルフ=神さんが「お宅は美女とっかえひっかえで不公平だ!」とぼやくシーンが『ウルフランド(旧題?狼の世界)』にあったかとw
言及してもらっている『虎よ!虎よ』は実は個人的にはアダルトウルフ以前に同テーマ・同プロットでの短編があるので、個人的には「番外編」的な感じです。(この時代のことを一部では平井和正「虎の時代」とも言うそうです)
これは『人狼暁に死す』も同様なんですよね―この作品は実は池上遼一氏作画による和製『スパイダーマン』の1エピソードが初出です。なのでこのあたり実はアダルトウルフの本筋・・・という感じがあまりしない、という。
アダルトウルフで個人的に一番好きなのはやはり『若き狼の肖像』ですかね、次に『人狼戦線』。
『人狼白書』にはじまる寺島雛子が出てくるシリーズはある意味アダルトウルフ本編中の本編なのですが、残念ながらここから続く『人狼天使』に至っては、次の『幻魔大戦』のプロットが入ってきてしまっていて、結果作品自体が宙ぶらりんで閉塞しちゃっていますので・・・。(面白さは抜群なんだがなあ・・・)
『人狼戦線』は最初に読んだ中学生のころは一番つまらなかったんですが、おっさんになって読むとその犬神明の”死と再生”の構造に気づいてノックダウンですわ(笑)。『若き狼の~』はこれ、ある意味一つの平井作品の頂点といってもいいんじゃないでしょうかね。青春の輝きと哀愁、その渾然一体となった切なさ、というか。ラストシーンがいいです。
と、まあここまでウルフガイシリーズお読みになってしまったら、次は行くしかないですよね、『月光魔術團』(笑)。
ちゃんと少年ウルフのその後が描かれてますよ―ただし入手可能な物理版(通常の書籍)では、おそらく彼の出てくる巻は現在ほぼ入手不可能かと思います(–;)
シリアスなウルフとはほど遠い雰囲気の作品ですが、シリーズ中いちばんエロっぽい・・・いや色っぽい(としておきましょうか;)作品なので、読んでみられても良いかと思います。
その際はまた感想聞かせて頂けるだろうことを楽しみにしていますw
>原作発表当時だったらこんなの発禁どころか逮捕者出ていてもおかしくないでしょう。
なんとも意外な情報、昔の方が表現に関する規制は全面的に緩いものだとばかり思ってました。
例えば、昨年度下期にジョジョの奇妙な冒険1・2部が深夜でアニメ化されましたが、原作連載当事ならゴールデンでも放映できたであろう内容なのに、思いっきり規制入りまくりでした。
また富野監督について言及しいらっしゃいましたが、正直今Vガンダムも深夜ですら放映できないと思います。このアニメののグロテスクさは、ジョジョ序盤と差ほど変わらないと思いますので(方向性がビジュアルか精神的かで違いがありますが)。
もっと酷いところでは、ドリフターズで生きたウナギをミキサーにかけたという情報すら聞いたことがあります・・・
自分の実感&聞きかじった情報を元にすると、昔はむしろ少年誌ですらヤンチャン版のような展開をできたんじゃないか、って思えてくるのですが、昔と今では自由の「範囲」が違うということですかね・・・
話は変わりますが、最近のアニメ界隈では「クレイジーサイコレズ」なんて言葉が流行ってますが、ヤンチャン版の羽黒は正にクレイジーサイコホモでしたね。
まぁ上記レズたちに比べ、やらかしたことが(ヒーロー漫画の割りに)現実的な悪事だったが故、サイコっぷりが洒落になってない、という違いがありますが。
p.s.
月光魔術團ですが、なんと自転車で少し遠くまで行った所にある図書館に書籍として全館揃ってましたので、近いうちに読んでみようと思います。
ただ、現在別のシリーズも読んでる&話が長いので読了は当分先の話になりそうですがw
>なんとも意外な情報、昔の方が表現に関する規制は全面的に緩いものだとばかり思ってました。
これはある意味簡単で、一昔前は暴力は身近にあるものであったということと、いまのようなネットがない=エロのダダもれは無かった=決してイージーでも、身近なものではなかった、ということでしょうか。
暴力、という点では体罰のことを考えてもらえればわかりやすいかと思います。昔は体罰のほうがむしろスタンダードといっても良かったわけで。結果、総じて暴力表現に対する禁忌は低かったのではないかと思います。
かたやエロに関してはそういう表現をしようとする際に、資料が潤沢にあるわけでなし、あったとしても(ネットがない=)イージーでもないわけです。ましてやそういう経験を豊富にしている=満たされているひとがわざわざマンガなどという労力のいる表現に向かうはずがありません。(だから昔は紙媒体のエロというのはいわゆる無修正写真とかだったんでしょうね、再現のための資料の必要もなく、現物をただ見せる、ということで成立するわけですから)
そういう意味で、当時の人から見ると、いまの我々はある種のニンフォマニアと見られても仕方ないような状態にある、というのは、あながち言い過ぎでもないような気がします。
ネットによるそういう情報の氾濫+ハードルのダダ下がりに加え、日本の場合は、そういう表現スキル(マンガ等)のある層が普遍的に存在した、ということもあるでしょう。
さらに、所詮記号としての描写しかされていない=けっして人間の本質を含んだ描写ではない、それ故にパターン化せざるを得ない=結果、飽きられないように奇矯なバリエーションをたこ足的に増やしていかざるを得ない、ということもあるのではないかと思います。
なので「18禁やエロ描写満載の作品より、そうでない作品のエロの方がそそらる」と書いていただいてましたが、それは、そこに少しでも人間の本質を描こうとするなかでの性描写だったから―なのかもしれません。
>「クレイジーサイコレズ」なんて言葉が流行ってますが
これも耳にはするものの詳しくは存じません、が、上記と同じくある種「お約束化されたパターン」のような気がしますねえ。
ヤンチャン版の羽黒は、もっと言うと簡単なことで
「自分と同じ(=対等である)友達がほしかった」
が究極にはあったのではないかと。そこに生物的にいちばん生殖能力の高い年代なので、性欲も交じってワケワカメな状態になった・・・的に考えるのはきれいすぎますかね?(苦笑)
まあ一番の結論は、以前も述べたように腐った皆様へのファンサービスかとw
※月光魔術團アプローチしやすいようでおめでとうございます。ただ、下半身が充血しやすくなる作品ですので(苦笑)、読まれる際は周りの環境に十分ご注意ください。
>まあ一番の結論は、以前も述べたように腐った皆様へのファンサービスかとw
実を言うとこのご意見はネタなのかガチなのか判断に迷っていましたw
というのも個人的な感想としては羽黒は一般的な腐向けキャラと違って、
悪党としてあまりにもガチ過ぎた(悪党なりの魅力のある矢島や初期西城と違い)、
何より顔が顔がクリーチャーっぽいと思ってましたので。
幸いYC版ウルフガイ好き(原作未読)なお腐れな方がいたので、「羽黒は腐女子一般に人気出そうか」と質問したところ、
答えはNoでした。やっぱり顔がよくないからだそうですw
あと性格があれでも顔が良ければ腐人気は出そうとのことです。
腐女子は男のキモオタと違って顔はあまり重視しないと思っていたのですが(何せリアル政治家とかでBL妄想できるくらいですしw)、
「同じ作中であれば顔が悪いのより良いほうがいい」とのことでした。
そんな訳でソッチ方面では犬神明・神明、そして羽黒に犯されてしまった千葉が人気出そうとか。
あのシーンで千葉に受けキャラとしての萌に目覚める人は多そうということ。
最後にオチつけるようでアレですが、この方は青鹿先生Loveで羽黒ヘイトなので、
公平性は期待できないかもしれまないとのことでしたw
もっとこの漫画が話題になってれば、最大公約数的な意見も出てたろうになぁ、と残念に思ったり。
ああ、自分もその辺りは特別詳しいわけではないので、広義の腐な皆さんへの釣り針程度だったのでは?的な意味で書きました(苦笑)。
例に出されている政治家云々の話からも想像できるように、個人的にはツボにはまれば基本何でもアリの人種かと想像してましたので。
要はアレでしょうね、そういったことを作り手側が想定して提示しても、そういった皆様のなかできっかけとなる作動スイッチというのは、想定外も想定外な斜め上なところにあったりするのでしょう。
自分のような所詮しがない一般人(苦笑)では分かろうはずもございませんw
それよりも以前この欄でコメント下さったほとりさんという方といい、ヤンチャン版青鹿先生が女性からの支持がありそうな感じというのが、自分的には興味深いですね。どのあたりがポイントになるんでしょうね。
別記事との連投失礼します。
今月光魔術團を読んでいる最中(まだ2巻目)で、読了後当該記事へ感想を書こうと思っていたのですが、この作品と
>ヤンチャン版青鹿先生が女性からの支持がありそうな感じというのが、
で気になることがあったので、先にコメントします。
まず私が質問した方が青鹿先生を好きになった最初の理由が、ぶっちゃけエッチな外見だからとのことでした。
(ちなみにその人の名誉のために言っておくと、外見のことはあくまで好きになったキッカケで、ちゃんと中身も好きになっていきましたw)
これは以前も申したように女性のオタク・腐女子といった人々の趣味が多様化したことの顕著な例だと思います。
で、月光魔術團についてですが、どうもこの作品は内容が女性向けを意識して作られたんじゃないか、と感じました。
90年代頃(セーラームーンあたりが節目?)から、女性向けでもエッチな要素を割りと前面に出しつつ、だが男向けのそれとは確かに違う作品が増えてきて、月光魔術團もその流れの中にあったんじゃないかなと思いました。
何故こうなったかは不明ですが、こういう作品が増えていく中で、女性たちの嗜好が変化していったのだと思います。
ちなみに月光魔術團が女性向けっぽいと思った理由が、
「泉谷あゆみさんの絵が当時流行った少女革命ウテナのように、女性向け作品にありがちなキラキラした雰囲気を持ちつつ、ボディラインをエロティックに強調するような感じだった」
という第一印象からです。
第二に、のっけからふんだんにあるレズ描写(笑)が、なんというか昨今の男性向け作品のように「萌え」を意識したものでなく、
いきなり乳を掴んだり、強姦され心に深い傷を負った女性がその看病をしてくれた少女たちに激しく求愛(見ていてなにやってんだと思えるくらい)したりと、
「男の妄想する理想的な百合描写」なんてどこ吹く風と書いている、って感じがしましたw
まぁこれも2巻までしか読んでない上での感想ですので、最後まで読めばまた印象は変わるかもしれません。
月光魔術團について、そのものよりもウルフガイ原作・ヤンチャン版双方について気になったことがあるためこちりに感想投下いたします。
月光魔術團は最後まで読み終わったのですか、結局本作でも「マーの悪意」ともいうべき部分に救いがおとずれることはありませんでしたね・・・
マーのような悲惨な過去を持つ悪役は最後なんらかの救いがあってしかるべし、というのが個人的にエンタメ作品に求める要素なので、ウルフガイの感想にも書きましたがこの点は前作通して悲しいことでした。
ただ気になるのが、マーと名乗るどう考えてもキム・アラーヤにしか思えない少女の存在。以下推測になりますが、何故キム・アラーヤと名乗らなかったについて、キムとマーの良心ともいうべき部分が合体して生まれたのが、「月光魔術團のマー」なんじゃないかと思います。適当な思いつきみたいでアレですが、そうでもないと、前作で荒ぶる神というべきマーとあのような可憐な少女結び付きませんので・・・ あと犬神明への負い目を感じるような態度も、過去自身が行ったことへの反省もあるのではないか、と思ったり。
そんなこんなで残ってしまった「マーの悪意」が「校内管制室のバカ」と呼ばれる存在になっていったのではないかと。以前マーをイザナミに例えていらっしゃいましたが、「校内管制室のバカ」はそのような悲しさをも感じさせる神ではなく、人間を軽蔑し堕落と不幸に導く普遍的な悪神のように描かれてるように思えました。それもマーから良心的な部分が抜けてしまったからではないかと、こじつけじみたことを愚考する次第です。
月光魔術團でふんだんに盛り込まれたエロシーンwを見たら、ヤンチャン版の青鹿先生にも愛あるセックスシーンを描いてほしいとさらに強く思いました。
ぶっちゃけますと、今までちゃんとしたセックスの経験がない女性が生まれて初めて心から愛する男と結ばれたらどうなるか、という下世話な興味もないではないんですが、
全うな行為を描くことにより青鹿晶子というキャラは当然として、作品そのものや読者の心も浄化することになるのだろうと思います。
以前ヤンチャン版がアダルト漫画のように扱われていると申しましたが、それもいわゆるエロ要素の大半が青鹿先生への強姦絡みにあったからだと思います。強姦というのは、性欲を満たすために対象の尊厳を蹂躙する行為であり、このようなシーンばかりのため上記のような評価されてしまったんじゃないかと。
ここに犬神明との愛ある濃いセックスを描けば強姦描写の印象は薄れ、この漫画に対する評価も改められるんじゃないかと思いました。無茶なショック療法的な思いつきですが・・・
ただ読者が望んでも、原作的にあの段階で二人の愛を結実させるのは不可能なこと。そのため繰り返しになりますが、ヤンチャン版の続編で原作とは違った結末を迎えてほしいものです。
また幻魔大戦deepトルテックにて二人は再会するとのことですが、その青鹿先生はパラレルの同一人物であり、犬神明が愛した青鹿晶子とは別人なんじゃないかと思ます。 それに犬神明は過去の思い出は振り切り少女マーと結ばれたのだから、青鹿先生に再会したからってそちらになびくのはどうなのか・・・
まぁこれもdeepトルテックを読まない上での感想なので、的外れなことを言っていたら申し訳ございません。
月光~読了お疲れ様です。
自分も読後暫くたっているのでピンボケ・誤読あるかもしれませんが何点か。
>「マーの悪意」ともいうべき部分に救い
この点は個人的には「あり得ないのではないか」と思っています。
なぜならマーというのはロイスそのものではなく、ロイスの怨念の部分が電脳化されある意味結晶化したものだと捉えているからです。
発端はロイスそのものかもしれませんが、その怨念には、救いや癒しを受けとめるための肉体がもうないわけで、いわばループするプログラムのように、怨念だけが結晶化されていた存在になり果てていたように思います。
それが『犬神明』最終章で示唆されているBeeとのサイバー戦でどちらが勝ったにせよ甚大なダメージを受け、それすらもまともに機能していないんじゃないかなと。(だから「校内管制室のバカ」程度に落ちぶれている)
加えて『月光~』ではおそらく世界線が変わっていると思いますしね。
繰り返しになりますがマー≠ロイスです。加えてマー=マシン或いはプログラム的な人格でしょう。
ロイスそのものはもういないと考えたほうが、個人的にはしっくりきます。
>キムとマーの良心ともいうべき部分が合体して
これは面白い見方ですね。別の言い方をするのなら、ロイスのDNAをベースに加工して作られている可能性があるわけですから、ある意味同じロイスという母体からわかれた『犬神明』でのマーと同等のウェイトを持った(しかしプラスマイナス逆の)存在、というのがしっくりくるかもしれません。(これはいま書いていて気付きました、ありがとうございますw)
えーと、あと青鹿先生に強い強いこだわりがおありでしたら、満足されるかどうかは別として『女神変生』をお読みになられるとよいかと。
>強姦描写の印象は薄れ
これは個人的な見解になってしまうのですが、本作のなかでやる必然性はないかと思うんですね。
なぜかというと、ああいうえげつないことを、ある状況におかれれば平気でやってしまうのが人類そのものだ、というのが少年ウルフの前半での一つのテーマでもあると思うからです。
そういう胸糞の悪さに気づいてしまった人は、それをイージーに善行描写で昇華させてしまってすっきりしては意味がありませんし、ああいう描写をポルノ描写として喜べる層はもともとそういうことを感じるセンスを持っていないでしょう。
そんなセンスを持ち得ていない層に”きれいなセックス”を見せても、なにも浄化されることはないと思います、哀しいことですが。
>その青鹿先生はパラレルの同一人物であり、犬神明が愛した青鹿晶子とは別人なんじゃないかと思ます。
これは半分その通りで、半分違っていると思います。
平井作品の、特に近年のそれの特徴の一つは、登場人物の人格の変異の凄まじさです。それを別人物と捉えるか、光のプリズム分解のように捉えるかでかなり印象が異なると思います。このあたりはいずれ機会があればおいおいと。
(このあたりは『アブダクション』シリーズ読めば少し印象変わると思います)
とまあこんな感じですが、どうしても怨念的なものをすっきりさせたい、という場合は左にリンク貼ってありますが『相羽奈美の犬』を読んでみてください。そういうものがどれだけ簡単にすっきりさせられないものなのかというのがわかります(ぇ
またそうじゃない、”愛”が足りなくてすっきりしない!ということであれば(苦笑)『ボヘミアンガラスストリート』をお読みください。これはおそらく平井作品の中で一番砂糖菓子のような甘さの詰まったシリーズです。
加えて後半のほうになりますが、そういうイザナミ的なものへの寛解ともとれる描写が部分的にあるように思います。
(ただ例によってある種のハーレム状態ではありますので、女性からはどう読まれるかはわかりませんw)
個人的にはすごく好きなシリーズです。
青鹿先生について仰るようにこだわり過ぎかもしれませんが、それというのもヤンチャン版の犬神明と青鹿晶子の関係はまだ終わったとは思えないためです。原作の二人は「犬神明」で決着がつき(月光魔術團で補足もされ)ましたが、ヤンチャン版の狼の紋章は核心こそ同じもののそれ以外は大分違うため、狼の怨歌以降が描かれたら原作とはやはり違うものになるのではないかと思います。これがバッドにしろハッピーにしろ、狼の怨歌以降につながらない終わりかたならヤンチャン版も終わったものとして処理できるのですが・・・
そんなわけで「原作の」青鹿先生はその行く末を見届けた感がありますので、せっかくおすすめいただいた女神変生ですが、読むのは後回しになりそうです。平井和正作品で目下気になるのは物凄い馬鹿作品っぽい(誉め言葉)「超革命的中学生集団 」と、なんとあの富野監督モデルのキャラが出るという「時空暴走 気まぐれバス」のため、今読んでるボヘミアンガラスストリートを読み終わったらまずはこちらからとりかかりたいと思いますw
あとこれはガキっぽい願望かもしれませんが、作品のテーマに反してでも、それこそ「安易な善行描写」をしてでも二人は幸せになってほしいというのが本音です。原作の青鹿先生の最後も無惨でしたが、ヤンチャン版の展開から同じ結末を迎えるのはあまりにも惨すぎると思いますので・・・
また卑俗な話で恐縮ですが、あからさまなエロ要素の多い月光魔術團と比べてもヤンチャン版の青鹿先生の外見は正直「下品」だと思いますw まずスカートが短すぎ&タイトすぎ、おっぱいデカ過ぎ、何故か谷間を強調する服を着る、と清純設定の割にツッコミどころだらけなデザインしてるんですよねw まぁ、これも悲劇のヒロインと同時にお色気キャラという役割も負わされたが故なのでしょう。ただこのような外見にも関わらず聖女的ポジションを確立できたことについて、製作陣の方々は本当に良い仕事をされたと思います。
変わってマーについてですが、彼女(?)の救済にもこだわったのは、以前少し触れたARMSという漫画の存在が大きいです。
この漫画の原作の七月鏡一氏は月光魔術團開始にあたってお祝いの文を寄稿するほどの平井和正ファンで、
(参考url:http://www.ebunko.ne.jp/july1.htm
http://www.ebunko.ne.jp/july2.htm)
上記ARMSは「犬神明」を参考にしたんじゃないかなと思える部分がありました。
ちなみに話のキーワードは不思議の国のアリス関連で、ラスボスの名前はズバリ「アリス」です。このアリスはマーに似た存在なのですが、最後は救済されました。この展開は七月氏によるマーという存在に対するアンサーなのではないか、と思った次第です。
ただマーはもうロイスではないとなると、救済はあり得ないでしょう・・・ マーはロイスに起こった悲劇を我が事のように語っていましたが、これも仰るようにロイスの恨みなどがマーにプログラムとして焼き付けられたためでしょうね。
ちなみにARMSは「犬神明」との関連性抜きに面白く、長さも20巻くらいと手頃なため、オススメですw(ステマ)
最後に話は思いっきり脱線しますが、アダルトウルフガイで親日や全日を「ちゃんとしたプロレス団体扱い」されたことについて、思わず「嗚呼プロレス幻想・・・」と思ってしまいましたw 物心ついた時にはプロレスが深夜放送されてた世代としては、この当時はあらゆる意味でプロレスに対する幻想を信じていられたんだろうなぁ、という感慨を抱いてしまいました・・・
また青鹿先生にこだわり過ぎと思われてしまうかもしれませんが、こちらのYC版ウルフガイの記事に青鹿先生の外見に関することは言及されていませんでしたが、「原作からのファンとして」どのようにお思いでしょうか?
上記感想で「清純設定の割に下品」なんて申しましたが、私なんかはヤンチャン版から知った上、低俗な人間のためそれを喜んで受け入れたりしましたが(苦笑)、他の原作からのファンの方々の感想を読むと、
「無駄に色気があり過ぎ。原作通り『どんな地味な格好をしても邪悪な人間に狙われてしまう悲劇性』の持ち主であってほしかった」
「平井和正は~~(名前は失念)が描いた青鹿先生はグラマラス過ぎて駄目出ししたのに、これは悪い意味でその上をいくのではないか」
というような感想が見受けられたため気になりました。
ただそれも原作に思い入れがあればしょうがないことかと。
やはり原作の青鹿晶子といえばか弱い悲劇のヒロインの象徴であり、それがあんな色気ありすぎる見た目では不満も出るのはある意味必然。
また平井先生はフォロワー的存在である菊地秀行先生や夢枕獏先生を「エロに頼りすぎている」と評したこともあるそうですが、ヤンチャン版の青鹿先生まわりは同様に評されても仕方ないかも(以前評されたように、「大人の事情」的などうしようもない点もあるかもしれませんが・・・)。
以前高橋留美子先生が参加したOVA版の絵を「コレジャナイ」なんて評しましたが、少年ウルフガイという作品自体はともかく、青鹿先生の外見イメージ的にはあちらの方がヤンチャン版より原作に近いのではないかと思いました。
ご無沙汰しております。コメントありがとうございます。
YC版青鹿先生のビジュアルなんですが、雑誌連載で初見の時は「お、かなりきれいに描いてもらってるな」という感じでした。
色気云々より時々でるいま風の若い口調やギャグ調のコミカルな顔を見た時点で、これは新しい青鹿先生像を作ろうとしているなというのが見えたので、自分は好感を持ってみていましたね。
たしかに過剰な色気云々の部分も描写の関係上あると思うんですが、マンガという視覚が重要な媒体だと「地味な格好でも~」云々というのは記号的にかなり難しいようにも思います。
ましてや掲載誌の読者層を考えると、そこまで高度なものを求めている読者というのはほとんどいないでしょう。そういう文句を言ってる人たちは少なくとも掲載誌を買ってやってから言うべきだと思いますね。
あと最大のポイントとしては、顔・・・というか表情がずっと清潔感を持ち続けていたので、自分は過剰な色気云々というのはそこで相殺されていたように思います。
表情というのはこういうマンガ媒体において最大のキャラクター表現だと思うので、ある意味そこがすべてを決定づけていたと思います、自分の場合は。
「原作どおり」が大切なのであれば、いまこの21世紀の時代にマンガという媒体でやる必然性あまりないと思うので、自分は本作でのビジュアル面の造形は全肯定です。
菊地・夢枕両先生に対してのそれは、テーマ性の問題じゃないかと思いますね。夢枕先生のそれ系のはあまり読んだことがないので断言できないんですが、菊地先生のそれ等は、エロのためのエロ、暴力のための暴力で、あまりテーマ性と関連はない・・・というかそれ自体が目的化しているような印象を受けます。
なのでフォロワー的に世間では受け止められているかもしれないんですが、基本的に似て非なるものだと思うんですよ。
この連休を利用してってわけじゃないんですが、少年ウルフガイ原作(レクイエムまで)を読み返したら、原作の青鹿先生は悲劇のヒロインとしての弱さが立って、自分から何かをした人ではなかったように見られました(普通の人があんな異常な環境に巻き込まれれば何もできないのが当然ですが、ヒロイン補正でなんとか乗り切れるのが多くのエンタメ作品というもの)。
この点が虎4の方が人気出た理由であり、女性ファンから叩かれたってのは(高橋留美子先生はじめ女性人気も高そうな)虎4に同調したフシもあるのかなと思ったり。
その点このヤンチャン版は、悲劇性がより増した分、行動的になり、アダルトウルフガイの石崎郷子のような(本人としては忌まわしくてしょうがない)サキュバス的性質が付加されたり、犬神明に力を与える巫女のよぅな超能力?も発揮したりして、ただ悲劇に遭うだけ・守られるだけのヒロインではなくなりました。
なもんで私としては原作からのファンの方々が言うような「格好が派手過ぎ」という意見も理解できるのですが、地味な見た目では弱々しそうで「ヤンチャン版の青鹿晶子」は務まらなかったと思います。
そのため私としては、色気のみならず母性も過剰なあの外見は最適解だったと確信しています。
p.s.
上記ヤンチャン版の絵を受け付けなかった方々は最初の方だけ読んで、そこで切っていました。
まぁ読書なんて所詮趣味だから好みに合わなきゃ読まなくていいというドライな意味でも、若い頃トラウマになるほど衝撃を受けた作品が自分の好みに合わない形で甦ってはタマらないというセンチメンタルな意味でも、「ヤンチャン版を読まない」という選択肢も正しい。
また逆に、ヤンチャン版を読んで原作はこれとは別物と判断して読まなかったという人もいらっしゃいましたし。
さらに余談になりますが、ヤンチャン版を絵ではなくシナリオが合わない理由で、切った人もいました(トドメはライオンが出たシーン)。
その人は月光魔術團も受け入れていたので、ウルフガイらしさはより強いヤンチャン版を受け入れらなかったのは不思議だったので理由を聞いてみたのですが、残念ながら教えてはもらえませんでした。
私女性で、しかも妊娠だの出産だのしてませんが、青鹿先生大好きですよ。
凛として、女神性に溢れてて、まあエロいのは時代を問わずエンタメ作品ですからそれこそ読者サービスとして。
ヤンチャン版も不快感は覚えず(そりゃあ自分があんな目にあいたくはありませんが)なんていうか、極限まで汚されることも含めて、自分の肉体を踏みにじられ、死しても本質の誇りを失わず、また輝く…というところが、犬神と対になりうる唯一の存在だな、と。
まあ、こういう意見も、若いふじょしは夢見がちだね、で一蹴されてしまうと思いますが…
そもそもあの作品を読んでファンになる女子で、犬神好きだから青鹿嫌いとか言ってる人は、少なくとも私の周りでは見たことないです。
もっと深いところにこそテーマがあって、そこに惹きつけられているのは、大人も子供も、男性読者も女性読者も同じ筈。
女のオタクは萌えてるだけ、のような言われかたはちょっと違和感あります…生意気だったらすみません。
青鹿先生大好きです!
はじめまして。コメントありがとうございます>彩さん
まず最初にもし本スレッドのやり取り見て不快になられたのなら最初にお詫びしておきます、ごめんなさい。
そのうえで一応こちらの意図してたところを若干説明させて頂きますね。
>犬神好きだから青鹿嫌いとか言ってる人は、少なくとも私の周りでは見たことないです。
これは自分も見聞きしたことありません・・・というかまず周りに本作品を知っている人自体がほとんどいないので。
加えてこの話の出所は出典明示できなくて申し訳ないんですが、平井先生のあとがきかエッセイにこれに近いような内容があったと記憶していたので話題にさせてもらった次第です。
ファンといっても世代の違いや、思い入れの濃淡あると思いますので、こういった傾向が当たり前だ的に決めつけるつもりもありませんので、そのあたり斟酌して頂けると助かります。
>女のオタクは萌えてるだけ、のような言われかたはちょっと違和感あります…生意気だったらすみません。
これも十把ひとからげにするつもりはないので、不快に思われたのならすみませんでした。
結局上記のやり取りで主に取り上げられているのは、本作品の「熱心なファン」の方についてではなく、こういったコミック化やそれに伴うアップデートを送り出す側、出版や制作・・・つまりパブリッシャー側ですね、そういう立場の人ならこういう認識でプロデュースしていっているのではないか?という推論です。
というか、いまこの時点で元となった原作(小説)を普通の一般書店の店頭で見かけることはまずないと思うので、そういったところまで追っている方は当然テーマやキャラクターたちの精神性に引かれてる部分があって当然だと思っています。
あとは時代性の問題・・・ですかね。
女性ファンが全部萌えだけで手を出しているなどと言うつもりはさらさらありません。が、上記のように出版や放送などのパブリッシャー側はある種の「保険」としてそういった要素を「意図的」に組み込んでいることが最近は非常に多いように感じています。
(なかには自分の「好み」でやっている制作側も少なからずいるかもしれませんが・・・)
そしてそういった「保険」の部分があることを、受け手側も至極当たり前のようになっていて、そういった構造に無自覚なままただ数を消費している層には、それが作品として「普通」だと刷り込まれている部分はあると思うんですね。この点、男性女性関係ありません。
(おいしいおいしいと炭酸飲料飲んでたら実はべらぼうな糖分入ってた、というのと似ていると思います)
そういうある種の「感覚の麻痺」というリスクは、常について回っていると思います。
と、ここまで書けば御理解いただけるかと思うんですが、本作品―とくに原作版はそういった小手先の細工からは全く遠い作品なわけでして。
ただ幸か不幸か、平井作品はあるところでは「キャラクター小説の元祖」とまで言われるぐらい、ビビッドな登場人物たちが活躍するわけです。
なので、昨今の「保険」がかけられた作品群を疑問を持たずに、ただただ消費している層なら、作中の全く違う意図で書かれた描写でも、自分たちの慣らされた「お約束の文脈」に勝手に翻訳してしまっている人たちもけっこういるのではないかな、とは思いました。
(それを非難するつもりもありませんが)
もちろん、みんながみんなそういった読み方をしているなんて決めつけるつもりは全くありませんので、ひとつご容赦を。
つまり本作品に関しては、ここまでに取り上げたようなことはどちらかというとイレギュラーな例であって、作品の精神性の部分に強い魅力を感じている女性ファンがほとんどであろうことは、上述の平井先生のあとがき・エッセイ類からも知っているつもりです。
ただそういう方々はあまり表には出てこられることはないかと思いますので、話がややこしくなってしまったのかなと。(^^;)
なのでここまでのスレッドはどちらかというと、その「イレギュラー」なほうやらビジネスとしては出版側ならこうだろうな、ということを雑談としてだべっていたもんだと御理解してもらえると幸いです。
コメントいただいていろいろ勉強になりました。ありがとうございます。
今更な話ですが、田畑・余湖両先生の描かれていた真マジンガーZEROが昨年末に目出度く読者に好評の内に完結しました。
そして大きな連載が終わったから、ウルフガイの方も真の意味で完結させてくれないかな~ってのはどうしても思ってしまいました^^;
まぁ一応区切りは着きましたし、エタなったとかそういう訳ではないんですけどね、でもやっぱりあの終わり方は生殺し過ぎます・・・
狼の紋章の時点でかなり違いが大きいため、怨歌以降はそのブレがより拡大することになりそうなので続きが気になって仕方ないですなぁ。
あと余談ですがこんなの見つけました。
ttp://www49.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/31844.html
こういう記事みたいに、もっとヤンチャン版を広めてくれる人出ないかなぁ(クレクレ)
レス遅くなりました。ひさびさのコメントありがとうございます。
リンク先見せていただきましたがなかなか面白いですね。熱心でありつつもフェアに記述しようとしている感じがするというか。
確かにこういうのでもっと作品としての知名度が広まれば一番いい形でしょうが、おそらく真っ先に話題になるのはエ□の方向でしょうなあ・・・・・(^^;)
真マジンガー完結なんですね。
自分も気にはなっていてときどきwikiやらAmazonで出版状況とかおよそのあらすじのようなモノは目を通していたんですが、書いていただいているのを見るとけっこう投げっぱなしジャーマン的なラストだったんでしょうかw
田畑・余湖両先生組はこういうスピンアウトというかリメイクでどんどん実績を積み上げてらっしゃるので、ウルフのほうも続編是非やってほしいところですが、次から次へと別メジャー作品手掛けておられるようにもみえて、なかなか世間的な知名度の面で考えると厳しいでしょうね。
まあそのあたりのうっぷんはしばらくは石ノ森プロ版の幻魔で紛らわしておくしかないところでしょうか・・・あ、3巻目のレビューめんどくさいのでほったらかしのままだった!?(汗