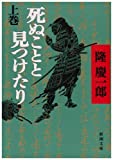作者の急逝による未完が悔やまれる傑作。
死ぬことと見つけたり (新潮文庫)


『影武者徳川家康』『一夢庵風流記』『捨て童子松平忠輝』等で知られる、隆慶一郎氏の晩年の一作。
武士道を語るとき、必ず名の挙がる一冊に佐賀・鍋島藩の『葉隠』があるが、その鍋島藩の草創から守勢に入ろうという寛永期を中心に、鍋島浪人・斉藤杢之助を中心とした群像劇。
実際の『葉隠』が執筆されたのは、この物語より後代の1700年代とのことだが、ひょっとするとこういった物語の末に『葉隠』のメンタリティは成立した、とでもいうべきラインを著者は用意していたのかもしれない。
表題の”死ぬことと見つけたり”は『葉隠』から取られた言葉であるが、おそらく他の隆作品と同じく、世間一般のイメージするそれと本作では、受ける印象は大きく異なっており、そんな窮屈なモノではなく、もっと闊達とした、ある種の清々しさを感じさせるものとして、描かれている。
これまでの氏の作品を愛読されてきた方々には、そこにあのなつかしい、風通しの良い立ち居振る舞いを愛する、”いくさ人”たちの姿を見るだろう。
(あの御免色里・吉原の惣名主・庄治甚右衛門も登場する)
本作がややこれまでの氏の作品と違う色合いを見せるのは、ぶっきらぼうともいえる杢之助に双子の子供がおり、”家族”というものについても語ろうとする面が見え隠れすることか。
これは、この『死ぬことと見つけたり』だけでなくやはり作者の死去で中断された『吉原御免状』シリーズでも、主人公・松永誠一郎に一人娘を設定するなど、晩年の氏の作品にはそういった”家族”或いは”親子”を描こうとした意図があったのかもしれない。
(そして双方とも父の剣客としての筋を娘が継いでいる、というのがなにやら可笑しい)
上下の二巻として刊行された作品であるが、物語はクライマックスである”殉死”の部分を除いて八割方語られていた、といってもいいと思う。
巻末に編集部より、氏の残したメモによる残る数話のあらすじの紹介、及び解題がなされているので、一応の物語の結末は知ることが出来る。
ただ、やはり他の作品同様、氏の筆による完結を見たかったという気持ちには変わりがない、ないものねだりというのは重々承知しているが。
しかし、未完とはいえ、十分読み応えのある作品で、末尾の知りきれトンボも、そうとわかって読めばなんとか納得できる。
それよりも読まないことによる、この爽快感を味わえないことのほうが、ある意味不幸だろう(笑)。
そうはいっても、未完は嫌われるというのはある種自然な流れで、おかげで自分も上下二巻200円という申し訳ないような値段で読ませていただいた。
食指の動かれた方は古本屋なり、amazonなどで探してみるのもよいのではないか。
少なくとも、その掛けた労力に数倍する恍惚感を、読んでいる間はまちがなく味わうことの出来る一作である。