昨今、お隣中国との関係がかまびすしいですがそんなときこそ彼の国の古典を。
誰かがうまいこと言ってましたが「中国文化が日本の親なら中共は親の仇」と(笑)。
事実中国文化から日本はたくさんのものをもらってますし、彼の国の方々そのものには恨みもへったくれもないわけで。
(むしろちゃんとした教育を受けれていない人たち相手にヒートアップするのは恥ですよ)
ということでお勉強の息抜きにぽちぽちと。
中国皇帝列伝 (創業篇) (徳間文庫)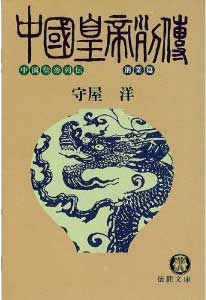
中国皇帝列伝 (守成篇) (徳間文庫)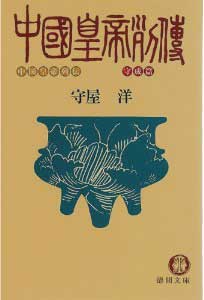
しかしいまこのタイミングで読むとけっこう昔読んだころの純真な視点と違って正直複雑な面もw
この守屋氏の著作は他に中国説客列伝、中国武将列伝、中国覇者列伝と高校~予備校のあたりでよくおせわになった。
たぶんこのあたりの中国古典への入り口だったのは、父親が持っていた陳瞬臣の全集かなんかで『小説十八史略』とか『秘本三国志』とか読んでからかなあ。前後どっちが先だったか忘れたが。
ほんで岩波の『史記・列伝』とかも買ったけど斜め読みでつまみ読みなかんじで(苦笑)。
で、あらためてこのあたりを読んでみると、いまの中国が「中華帝国」を指向する気分はわからんでもないが、やはりここに書かれている歴史の世界となった時代においても基本は彼らの言うところの「中原」が中華世界であって、それ以外の辺境というのはやはり中華世界とはいえないだろう。その中華世界の物語を構成する一登場人物であることには間違いないが。
で、彼らはやたらと過去の例を持ち出して「過去は我が国の領土だった!」と真贋もわからぬ過去の時代を持ち出すが、そうするとあんたらの国もモンゴルにそっくり返しなはれwということになるわけで(苦笑)。
そして彼らのいうところの南蛮、東夷、西戎、北狄―いわゆる四方を囲む化外の地に対してのアプローチも実は「属国化」ではなく「朝貢国化」が過去においては基本のように読める。
もちろん外征をおこしてたびたび攻めているけど、けっして恒久的な駐屯とかはやってない(というかできずに)、攻めつ、攻められつで中華世界の外周は決められていたように見える。
それからするとやはりいまの中国共産党帝国のそれがいくら歴史を根拠に拡大主義をはかっても、その根拠すらかなりあやふやではあるわな。
基本現状の国土の規模を維持する、という前提で行くなら確かに(道徳的な良し悪しは抜きにして)ああいう一党独裁の強権的な政治体制にならざるを得ないだろう。
逆に言うと、そういう「無理やり」な手段を使わなければ維持できない規模をいまの中国政府というのは保とうとしているとも言える。
手放してしまえば良いのに―。
中国の弱体化を願うのではなくて、周りの地域の平和と安定を願うならそれがベストだと思うんだけど。
その上で昔の「中華圏」でゆるい連邦制をとれば中国の面子も逆につぶれないと思うんだがなあ。
まあしかしそこが「中華」思想のむつかしいところで―なんせ「中華=世界の中心」なわけですからなあ(嘆)。
そんなこんなを思いながら昔なつかしい歴史上のキャラクターとしばしの再会を楽しみました。
けどさ―。
毎回思うんだけど、やっぱり日本軍が中国大陸でやったといわれている蛮行―虐殺やらなんやらというのは、こういう歴史書見ると「ちがうよなあw」と思う。
なぜなら基本的に殺し方の文化が違うのよ。
日本だと斬首した首に対して「首化粧」とかいうようにやはり「払い・清め」の文化があったりするけど、向こうさんがいうような四肢を割いて臓腑を撒き散らすみたいな死体損壊的な文化ってあまりメジャーじゃない。
むしろその死体損壊の文化は彼の国のほうの文化的なお家芸であって。
『復讐の念に燃える呂后は(中略)戚夫人の手足を断ち切り、眼球をくり抜き、耳を燻べてつんぼにし、いん薬を飲ませて唖にし、厠の中に投げ込ませて「人豚」と呼ばせたという』
(『漢の高祖(劉邦)』―章末より。「いん」→病だれに音、豚→常用漢字外、わからんw)
この呂后は漢の高祖の嫁=皇后。この手の話はたしか清朝末期の西太后にもあったような。
だからなのよ。自分の好きな後漢の光武帝が例外中の例外っちゅーのは。
彼は創業の功臣を誰一人として粛清しなかったし「妻を娶らば」と恋焦がれた陰皇后も賢夫人で、中華歴代王朝の腐敗の原因となる外戚(自分の親類縁者)を高い地位に登らせなかった。
まあそのあたりからも”普通”の―例外でないあたりまえのかのお国のものの考え方というのがわかりそうなモンではありますわな。
今回ぱらっと読み直してみてあらためてそのあたりを感じた。




