ネットでまどかの叛逆絡みの記事を読んでいると、時々目にすることがあったので読んでみた。
角川春樹事務所
売り上げランキング: 36,275
超強力なラップ現象=憑依現象を起こしている少女マリアへの”探索”を依頼された伊藤は彼女の精神世界へと入り込む。物理現象さえ発生させる彼女の思念世界、その奥にはシュワルツシルド特異点をこえた”あの闇”が広がっていた。表題作をはじめ、人間の”生”な描写と理論物理学的なアイディアをからめて壮大な彼岸の景色を描きだす4作品を収録。
量子物理学の描写やそれを使ったぶっ飛んだアイディア等、とても70年代末に書かれた作品とは思えない一冊。
なかなか読みごたえのある短編集だった―というかまだ十分読み切れていないかも。
それぐらいスケールが大きく科学的な知識をバックボーンにしたぶっとんだイマジネーションの作品だった。
繰り返しになるが、これを70年代に既に書いていたというのが凄いよなあ。
小松御大は博覧強記で故に文書が硬い、というイメージがあったんだけど、本作品集に関してはそんな印象はうけなかった。(これは少し自分の知識量も上がってたからだろうが)
全作品にどことなく「彼岸」のイメージがあって、かといって枯れているというわけではなく、躍動している生がそれでもなおさらに巨大な彼岸という闇に飲み込まれていくとでも言えばよいか。
そしてその闇も終焉としてだけの闇ではなく、どこかその先にある「誕生」を感じさせる―もうほんとこれは一冊全体を通して漠然とうけた感触でしかないのだが。
なかでもやはり突出して異色なのは表題作の『ゴルディアスの結び目』。
これは一部の人たちが小松作品のなかでもずっと愛読し続けている唯一の作品だ、というのもわかるような気がする、内容はとてもそんな上品なものではないのだが(苦笑)。
とにかくそのイマジネーションというか、当時最先端の科学的知識とデモーニッシュな少女の中の心象風景―それもファッションとしてのゴス的なものではなく、身体だけでなく深く魂までもが傷つけられた存在の心の奥底にある闇としてのそれ―が異空間からの膨大なエネルギーの流入口となる、というそのアイディア。そしてその描写は非常にビジュアル的なイマジネーションを呼び覚ます。
系統的にはまったく別のものではあるが、確かにこれはまどかにおける魔女の結界―特に叛逆の物語におけるそれ―と相通ずるものを感じる。
正直あと何回か読み直してみないと読み解けていない部分も多いかと思うが、それを抜きにしても非常に想像力をかきたてられる、読み応えのある一冊だった。



![e of s EP/SawanoHiroyuki[nZK]](https://www.thx-design.net/blog/wp-content/uploads/61xoPVN4IzL._SL160_-150x150.jpg)

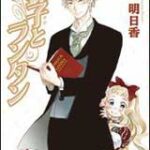
こんにちは。お初にお目にかかります小松左京先生は 他のSF作家と比べても、桁外れです。私も中学 高校 大学生の頃、文庫本を買いあさっていました。
1970年代にはTVドラマ 映画化されていましたが、「さよならジュピター」がこけた頃からあまり活躍しなくなり ました。
でも最近 随分 再評価されている様で、1ファンとしては嬉しい事です。
>まおゆうの虫さん
はじめまして、コメントありがとうございます。
小松先生の偉大さはこちらの接した時期の年齢のせいか、ご本人の作品直接からよりも周辺の作家さんたちの反応から間接的に認識していた感じでした、これまでは。
しかしこの作品をこの時期に読んでみると、ほんと凄い大作家ですよね。
時代が作中で駆使されている基礎知識にようやく追いついて来て、その真価がようやく評価されているということなのかもしれません。
自分もチャンスがあれば徐々に追っかけてみたいと思っています。
またオススメなどあれば教えて頂けると。
※HNからするとまおゆうもお好きなんでしょうか(笑)。
ご返事ありがとうございます。小松左京先生作品のお勧めは、「見知らぬ明日」「復活の日」「結晶星団」エッセイに近い「招かれざる訪問者」などありますが、あの方の作品に駄作はありません。初期の頃作品「日本アパッチ族」「明日泥棒」その続編の「ゴエモンの日本日記」は今の方には”古い”でしょう。
「 まおゆう」は大好きです。メイド長さんやメイド姉さんに「この虫」と罵倒され足蹴にされたい…違う、されないような人生を歩まねば自戒を込め「まおゆうの虫」と名乗っています。
すいません「招かれざる訪問者」でなく「おしゃべりな訪問者でした」
メイド長「この役立たずの虫が」
コメントありがとうございます。
まあまあそう卑下なさらず―いや、この場合はご褒美でしょうか(苦笑)
小松先生のオススメ作品ありがとうございます。
折をみてオススメのものからいければな、と思います。
昔からタイトルがぶっ飛び過ぎて気にはなってるんですよね、『日本アパッチ族』w
お久しぶりです。日本アパッチ族は 1960年代に小松左京先生がまだ貧乏だったころ、ラジオを質で流し代わりに奥さんの娯楽のため夜に書いて、朝 原稿を渡していた作品です。
内容は、日本が権威主義体制になっており、そこからはみ出た人々が、鉄を食べてエネルギーになる特異体質に「進化」して、「アパッチ族」と名乗り 人間の社会に挑戦する。というものです。荒唐無稽ですが。当時の世相らや作者の心情や政治についての考え方がよく出ています。
小松左京先生は、子供向けの作品もあります。青空市物語は 今では このころの人はこんなノーテンキな未来を信じていたのか という歴史資料でしょうね。子供向けは 「青い宇宙の冒険」がお勧めです。一味違います。
「エスパイ」も娯楽の小説ですが、最後に、ハードSFになります。
やはり 先生の考え方がよく出ています。
すいません、「鉄を食べてエネルギーになる」でなく 「エネルギーや栄養にする」 です。
メイド長 「 少しは進歩したと思っていたけど、抜けてるわね。虫さん。」
お久しぶりです。コメント&ガイドありがとうございます。
実はいろいろ教えていただいたので小松先生の作品はいくつか購入だけはしてあるんですよ、電子書籍でセールがあった時に。
ただなんか書かなければいけないブログのネタもほかにたまっておりまして+まだ未読なのでいつのことになるやら・・・。
また読み終えたら記事にはしようと思っておりますので、その際はぜひ感想お聞かせ頂けると!
(もちろんそれに限らずほかの記事でも琴線に触れるものがあればお気軽にどうぞ、もちろんそういうものがあればですがw)