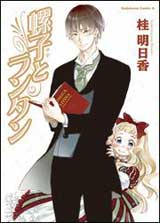新刊出たことは素直に評価。けどこのピッチで広げた風呂敷はたためんのかw
『ベルセルク 35 (ジェッツコミックス)』
スケリグ島・・・だったかな?(なんせここまでの分よそへ貸し出し中なので)へ向かう最中の船旅が継続中。
港で人攫いやってた髭海賊が髭骸骨になってお礼参り→退けるも被害。船の修理に立ち寄った島で・・・。
といった展開だが新キャラの女の子がかわいい(笑)。
あと島全体の雰囲気というか、辻に祭られている海神さまの描写のディティールはなんとなくクトゥルフ神話のそれを下敷きにしているようでいい感じ。
ただし激しく「続く次号!乞うご期待!」
な感じなので正直今巻だけではなんとも(苦笑)。
描写のディティールがぐっとあがってしまったのでいまの連載ペースは仕方がないともいえるが、(別作品とはいえ)真面目に内職やってる永野護と違って何か他のことしてるっていうのも見えてこないので、ちょっとさぼりすぎでないかなあ(笑)。
ぜひとも広げた風呂敷はたたんで終えていただきたいものではあるがこれいかにw
※2022/06 標題の表記を統一、リンク切れを修正