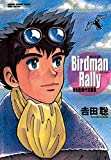それは「彼岸」にかかる橋か─
近藤ようこ先生最新刊。
『逢魔が橋』
青林工藝舎からの一連の時代物のシリーズで、今回も舞台的には中世と思しきところにとりつつも、作品の持つ雰囲気はどことなく今昔物語風に感じるのは自分だけか。
今回は表題になっている「逢魔が橋」の連作と数本の短編からなる。
「逢魔が橋は」作中の狂言廻しとなる美形の橋守りの青年がその橋を渡ろうとするさまざまな人々の物語に関わるスタイルの連作。
その掌中のもうひとつの「目」を持ち出すでもなく、ひとによって渡れる/渡れぬと変化するその橋自体が既に異界=「彼岸」なのかもしれない。
こういう境界に「橋」を設定し、そこに橋守を置くというというのは、これまであったようでなかったような。
「その橋は静かな山中に人知れずあった」というフレーズが物語の冒頭と最後に定型として入るのもよい。
そして近藤作品の魅力はそういう怪(あやかし)の世界と非常に柔らかな描線を持つ黒髪の女性キャラクターの清潔な色気の混合だなあと再認識。特に橋の向こうで年季明けに許婚との婚礼を夢見る娘を描いた第三話、仏道を禁欲的に極めようとする青年僧が彼を救った村娘に最終的に観音を見る第四話がすごくよかった。
美形の橋守りはなんとなく山岸涼子の描くところの厩戸王子を思い出させる。
この連作以外の三本も独特の雰囲気で、特に「海神の子」などは逆にいまの若いマンガ家では描けないだろう。
そして本書最後を飾る「夢見る指」が非常にぞっとして素晴らしかった。
あと本書は巻末の国文学者・田中貴子先生の解説が読ませる。
民俗学的なところがツボな人にはたまらんだろう。
総じて近藤作品の長編が持つ圧倒的なパワーのようなものは薄いのだが、その分この雰囲気をほろほろと味わうにはよい一冊かと思う。
贅沢を言うなら「逢魔が橋」の世界だけで丸まる一本読んでみたかったところ、そこだけがちと残念ではある。
※2022/06 標題の表記を統一、リンク切れを修正