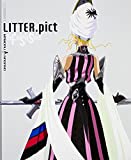FSSを8年近く休載してまでやろうとしていたこと―信者ならこの目で確かめずばなるまいw
移民星・カーマインプラネットには”詩女(うため)”と呼ばれる、民衆の心の支えとなる代々続く巫女がいた。新たな巫女は、就任に際し歴代の巫女の記憶を引き継ぎ、都までの道のりを行幸する。
新たに巫女となったベリンは、いままさにその都行きに出発しようとしていた。その時、巨大な戦艦が巫女たちの前に現れる。現れた少年はドナウ帝国第三皇子トリハロン。彼が言うには、この星の政情の混乱を狙って、新たな巫女を狙うテロが計画されているという。彼はその護衛ため惑星連合から派遣されてきたのだ、と。こうして詩女と皇子の不思議な旅は始まった・・・。
前々からいろいろ情報は出ていて、かなり少人数で作っており、そのアニメーションの大部分を監督・原作者である永野護自身が手がけている、ということでいろんな意味で注目されていた一作。
ここまで最大の懸念は、遅れに遅れ、おまけに小出しされる映像が、昨今のアニメのそれと比べると、あまりにも心元ないようにみえること。
正直完成しないのでは?と思っていたファンも多かったのではないか。
しかし完成した以上、25年以上ファンやってる身としては観にいかずばなるまい(苦笑)。
結論からいうと
「ああ、よかった」
そして
「意外と満足感あった」
この二つに尽きると思う。
「ああ、よかった」というのは、永野氏が”手製”にこだわるあまり、完成しなかったり、完成したとしても商業レベルに達していないモノになるのではないか、という不安。
これはなんとかクリアしていた。
というか、一部の描写では、これだけ時間をかけたからこそ見れる―昨今のアニメではなかなか見れないような部分―もあった。
特に一部の予告でもみられた、トリハロンが雨に打たれているシーンの雨の降り方なんぞは、素晴らしかったと思う。
しかし実はこのことが、この作品の全体の特徴を現しているんだが、止め絵的なシーンだとか、全体的な雰囲気、デッサンというのは素晴らしいんだ―。
だが、それと比して肝心要の人物の”表情”の描写がかなり厳しかった、というのは言わざるを得ない。
この部分(表情)が作劇の肝である。だから、こだわりたかったのはわかる。
が、ここは監督自身は一歩引いたチェックに回って、その道のプロに任せたほうが良かったのではないか。
(その余力でGTMの戦闘シーンの尺増やすとか)
正直それだけで、このフィルムの価値は数段階あがってたように思う。
個人的には、永野氏というのは間違いなくある種の天才だと思ってる。
ただ天才にありがちな弊害なんだが、天才ってチームワーク―他人に委ねること―ができないのよね。
(かのsteve vaiなんかも若いときそれでミスってもったいないことしてる)
そして、アニメーションというのは、そのチームワークの最たるものでしょう。
あの宮崎駿氏ですら、一人ではあれだけの作品群を産み出せないわけで。
もちろん安彦良和氏をして”冷静な分析力を持ったオタク”と評される氏のことなので、このあたりは自覚はしてらっしゃると思う。
あとは今後、自分の”映像作品”を残したいのか、それとも自分の”こだわり”のほうがより大事なのか。
(FSSをアニメ化したい、けど不可能に近い的なことは何度か発言されてると思うので)
そこを、シビアに秤にかけることになるだろうな。
ファンとしてはどちらにせよ氏の作品に”はっ”とする部分を感じる限りはついていくつもりですが。
そう、その”はっ”とする部分、ということで言えば、実は本作の主役であるはずの”ロボット”―特に敵役のそれには若干弱さを感じる。
これはFSSでも―特に魔導大戦以降のデザインに―顕著なんだが、なんか以前にあった、メカニックとしての理詰めの部分が、表のフォルムとしてのデザインの部分とリンクが切れているような感じなんだよな。一言でいうと―のっぺりしている、というか。
もちろん、のっぺりしていても素晴らしいデザインというのはあって―それの代表はかのハンブラビのそれだろう。
(少ない線であれだけコミカルかつデモーニッシュであるデザインというのはなかなかない)
あとあれだけ「音」にこだわっていたので、GTMの動作音にはかなり期待していたんだが、ガンダムよりはマシだが、これまで仰ってた発言から期待したものを感じるところまでには、至っていなかった。
けど主役のカイゼリン”起動音”にはかなりニヤっとさせられましたけどね(笑)。
そう、ここまでなんだかんだ書いたが、やはり主役のカイゼリン周りの挙動はかっこいいわけで。
あのガキ・ゴキ・ゴキと動く感じは、見ていて生理的に心地いい。
また、このカイゼンリンまで走るシーンとか、前半の崖に向かってソニックブレードとか、トリハロンの動きもカッチョ良かった―というか「おお!?マンガでかかれてたシーンはこういう動きなんだなあ」というか。
要はこのフィルムはFSS読者へのファンムービーの側面もあり、かつFSS映像化へのテストフィルムでもある、ということなんだろう。
前述のトリハロンの動きは騎士の、各GTMの動きはMHの、カイゼリンのトランスルーセントな装甲はどう考えてもインフェルノ・ナパームのための―。
そしてファンムービーということで言えば、出るわ出るわ、あんな方やこんな方やあんな人までw
というか、本編始まる前の角川のスタジオロゴからして思いっきり出落ちやがなw
個人的にはやっぱりグレイオンと、それに混じって出てくるバングが反則でしたね。
グレイオンなんぞは角川の『別冊エルガイム』リアルタイムで買った世代としては涙ちょちょぎれやし(フェイクファーまとったパイロットの人の系譜キャラも歴代の・・・のなかにいましたな)、バングに到っては「え?そうなん?またガレキの原型師さん死ぬん?」みたいな(爆)。
おまけにバングの設計者の人まで出てきてセリフまでしゃべってたしな。
(作者本人の手によって動いたはじめてのミラージュ騎士になるのか?)
あと当然ながら服飾のデザインはほんと最高だった。
(各マイト陣とか、例のフィルモアのバチカン風の制服とか)
最近のFSSも実を言うとMHとかよりも服のデザインのほうが見てて楽しい。
要は、本作はこれまでのCHARACTERSとかDESIGNSの映像版である、という捉え方が一番正確な気がする。
そういう意味では、今後もFSS本編や、関連書籍を読み続けるだろう、という方は是非見にいっておくべき映画かと。
また、ここまで細かなディティール部分についてのみ書いてきたが、実は上述のように「意外と見れた」と感じた大きな理由の一つは
「物語として破綻せず、演出としても、観客の集中力を切らさず最後まで見せるレベルになっていた」
からでもある。
なので、もし今後氏の映像作品があるのなら、委ねるとこは大胆に委ねて、是非そのこだわりをトータルで文字通り”監督”して見せてほしい。
いろいろ書いたが、ここまで四半世紀近くいろいろとお布施してきたんだから、これぐらいは書かせてもらっても罰(バチ)はあたらんだろう(苦笑)。
それ以前に”期待”や”信じて”なければ、こんなに長文書かんわ(笑)。
ぜひ動く3159を。
それがこれ以上のものであるなら、7分とかで3000円だったとしても観にいくぞw
※余談
・歌モノは主題歌含む3曲が本作では使われているが、主題歌よりも他の2曲のほうが良かった。
川村万梨阿氏の魅力がより出やすい曲調だったんだろう。
・おそらく自身の監督作品に「ベーシスト」としてエンドテロップに名前出た人は初めてではないかw
・毎回思うが、実は永野作品はファッション以外も「食事」描写が凄かったりする。
個人的に「食事シーン」と「ゴミ」の描写ができる作家は本物だと思っている。
・当日の客層の年齢が高いこと高いことwこの手の映画ではまずありえない客層(含む自分w)
(それでも女性が3割ぐらいいたというのは永野作品らしい)
・何気に富野監督と安彦氏の名前がテロップに入っている、というのは重要だと思う。
そういう位置づけの人物である、ということだろう。
地位がどうこうなのではないが、ご両人から名前を預かれるだけの作家である、とは言っていいのではないか。
※2022/06 標題の表記を統一、リンク切れを修正