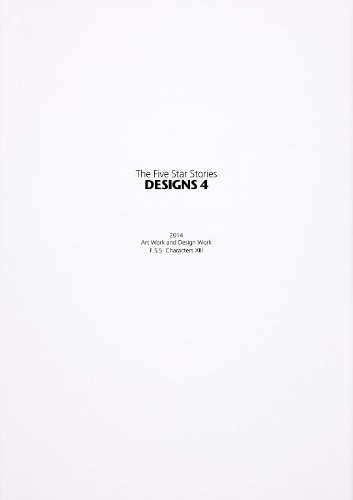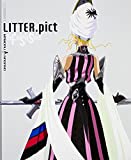先週までべらぼうに忙しかったのでまだ十分読めていないが、初見の印象
『F.S.S. DESIGNS 4』
これまでのDESIGNS1~3につづく最新作品集。これまで発表済みのデザインをまとめた既刊のものとは異なり、現在連載中の内容と並行する形でメカニック、服飾、キャラクターの最新デザインが収録されている。そのため版形も既刊のDESIGNSと異なり、これまでのKnightFlagsやSmokeWall,TwinTowerなどと同等の大型ムックとなる。
まず最初に言っておくと、本連載のほうを未読で単行本で本作品をフォローしているという人たちは、この作品集を買うのは少し待った方がよいと思う。基本的に次巻となる13巻の刊行を待たれてから手を出されるべきだろう一冊だ。
そのうえで、この作品集に収録されているデザインの大きな変遷を、自分は全く何の問題もなく肯定する。
こういった大激震をやってのけたのはやはり永野氏ならではと思うし、その大きな決断は評価する。
本作に収録されているデザインも、やはり十分見ごたえのあるもので、以前GTMのレビューの時のも書かせてもらったが”はっ”とする部分が十分にあり、やはり氏がある種の天才である、ということはいまだ揺るがない。
そういう意味で、基本的にここに掲載されているデザインに関して自分は”肯定”である
ただ、そのビジュアル的なデザイン以外の部分で、何点か述べておきたいこともある。せっかくなので、この機会に以下にそれをまとめておきたい。
基本的にこの大激震はこの人でなければやれなかったことだし、それは痛快であるので繰り返しになるが基本的には全肯定なのだ。
しかし”デザイン”そのものはともかく、固有名詞の大部分を変更してしまったのはどうだろうか・・・・・というのは正直思った。
なぜなら、これまでの物語のトーンというか根幹をなしていたものとして、やはりその文字情報の部分も大きかったと思うからだ。
(もちろんそれもあってのここまでの変更ということもあるのだろうが・・・)
そして一番肝心なのは、ここを大きく変えてしまったことで「なにか新しい・カッコいいものが見えてきたか?」というと、正直あまり見えてきていないということ。
ドイツ語読みや大胆に日本語的なネーミングを取り入れているところは面白いと思うのだが、その新要素がカッコよさや刺激につながる部分と、これまでの固有名詞が物語に与えていたダイナミズムのようなものを冷静に比較してみると、明らかに前者は後者を凌駕するだけのものを持ち得ていない。
もちろん一部には、すごく良い形での固有名詞の整理もあった。ドラゴン→セントリーなどはすごく良い変更だと思う。
個人的には、こういった一部の説得力のある部分だけの改編にとどめておいた方が、作品全体としての破壊力はより増していたのではないのか?というのが正直な印象だ。
ドイツ語読みカッケー!?というのもここまで連発されると一周回ってちょっと恥ずかしい感じすらする。これが一部にとどまっていればそうでもなかったんだと思うが、これだけ大量に使われると、ちょっと痛々しさすら感じる。
そしてもう一点。
これは本デザイン集以前からその傾向があり、それがどんどん悪化していたと思うのだが、いわゆる”超帝国”最強!的なヤツ。
超帝国に限らず”古いもののほうがスゲー!?”方針と言えばよいか。
これなんとかならんのかな?
これも、もちろん基本的には悪くはなかったんだ、出た当初は。
しかし正直ぜんぶ”昔のほうがスゲ―!””昔のほうが強えー!”だと正直萎える。
なぜ萎えるのかもちゃんと説明できる。なぜかというと、これをあまりにやってしまうと”世界が狭く”なってしまうのだ。
どういうことかというと、過去のルーツとなるモノのほうが凄い、というのは要するに枝葉でなく幹のほうが凄い、ということになるのだが、それって結局情報の多様性ということからいうと、ある一つの時代のものがすべてのルーツという話なわけで、他にそれに並ぶものがない、あるいはあっても霞んでしまっている状態。
せっかく5つも惑星がある世界の話なのに、すべて超帝国、あれも超帝国、これも超帝国、全てすごいものは超帝国では5つも星要らないわけで。
そう、多様性がない世界というのは、ものすごくつまらない。
この物語の始まった当初のワクワク感とういうのは、まず間違いなくその膨大に広がる世界への、その広さやいろんな景色への読者の期待や想像力が刺激されることにあったはずで。
しかし残念ながら今現時点での物語におけるそのベクトルは、多様性ではなく超帝国やフィルモアといった大帝国を縦に深く掘り下げる一方で、横への広がりが全く見えてこない。すごく”狭苦しく”感じるのだ、正直なところ。
これはいくら周辺王家がどうの、この家系がどうのと設定されていても、上述のように枝葉として広がるのではなく、幹のほうへ収束していってしまうからだ。
これはすごーくもったいない話のような気がする。というかそういう一つの井戸を深く掘ることしかできなくなっちゃったのか?(そうは思いたくないんだけれども)
ぜひこのあたりは超帝国がらみでも、ダスラントでもない、市井の広がりがゆえに発生する人のたくましさというかしぶとさを体現する物語も見せてほしいところだ。
正直”昔あったおっきな帝国が凄くてすごいのは全部それなんだぜ!”は飽きた。それが凄い・カッコいいとは全く感じないんだ。
たしかどこか”海外の反応”系の掲示板でだったかと思うんだが、海外の方が(本作ではなく日本のマンガ全般に対して)指摘していたのがあって
「日本のマンガって結局ぜんぶ血統主義なの?」
というのがあって、思わず深くうなずいたことがあったのを思い出す。
確かに血のつながりや血統の物語というのは面白い部分があって、自分もそれ自体を否定する気はさらさらない。
けれど、世界がすべてそれで決まっていて、それから逃れられないというのは、あまりにもデストピアな世界ではないか?この物語はそんな狭い価値観を肯定する物語だったんだろうか?
凄いものが凄い、そしてそれは血統に担保されてゆく―そういう側面もあるだろうし、そういった傾向が現実でもある程度強いことも否定はしない。
ただ、それってやはり繰り返しになるが、多様性の否定になっちゃうんだよな。
そして多様性を失った物語というのは、寿命は長くないんじゃないだろうか―種として多様性を失った生物の寿命が長くないように。
そういった多様性を新たに獲得するためのはずのデザイン面で行われた今回の一新が、物語側では機能していないのが、なんとも解せぬというか意外というか。
もちろん、こういったところも計算の上で、この先にもっと凄い展開が待っているのかもしれない。
自分のような凡人の予想をはるかにくつがえしてくれる物語が。
いまは心底そうであってほしいと願っている。
そうじゃないと、これだけぶっ飛んだことをやるクリエイターとしては、片手落ちだとすら思うんだわ。