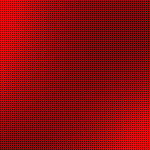才気ある人が、修羅場をくぐってもなお優しさと希望を捨てないと、こういう本になるのか。
なぜゴッホは貧乏で、ピカソは金持ちだったのか? [単行本(ソフトカバー)]
山口 揚平 (著)
いわゆる経済・金融系のHowto本ではなく、お金というものや、実体経済からおおきく乖離した金融資本主義経済が幅をきかすいまの世の中で、お金の本質―ひいてはその先にあるものがなんなのか?ということを考察した一冊。
著者の前著が素晴らしかったので読んでみたのだが、これも良い本だった。
各論のなかにあるものそれぞれを通して、より明確に著者の思想というか、ものの考え方を論じている一冊ともいえる。
本書はよくありがちなマーケティングやトレンドの流行り言葉としてのそれではなく、より信念と実体験に裏打ちされた言葉で評価主義経済への移行を論じており、静かな文章のなかに、ある種の熱を感じて好感が持てる。
タイトルや前半の内容からは「お金」の本質への考察、そしてそこから金融資本主義でのお金の実際も語り、それを踏まえた上で、本質から考え、お金とその先にあるものを模索している。
それは現在の金融資本主義的な社会から、「信用」の創造と、その信用によって回っていく経済のあり方がより存在感を増してゆくだろう、という論旨と自分は読んだ。
基本的に8割がた同意できる内容で、かつ、こうなってほしいと自分も考えるが、一点懸念を挙げるとすれば、国家のウエイトが下がっていくというくだりに関しては―そういう側面があるのを肯定した上で―すこし楽観的ではないかな、と自分には感じられた。
こういう話になったとき(自分もついやってしまいがちなのだが)、往々にして物理レイヤーの想像以上の強力さというのは、軽視されがちになる。
LCCなどの存在感が増し地球の距離は縮まった、物理的な距離の問題はもはやハードルではない、またappleなどの多国籍企業のほうが、世界最大のアメリカ政府より現預金を持っている―。
その通りなんだが、そういった劣勢になっている、と思われるオールドプレイヤーたちは、最終的にいちばん強い「暴力」を持ってるんだよな。
確かに、facebookやtwitterでひっくり返った政府や国もある。
そういった可能性とそれらがもたらす重み、というのは今後も間違いなく増えていくだろうが、それらソーシャルサービス的なものは、本質的に「細く」「遍く」なわけで、その力の源泉はその広範さというか”規模”に依存している。
その「規模」をひっくり返しうる一点突破の暴力的な力に対して、それらがどこまで力を持つのか?
webや発達した交通・通信技術を担保にひろがる、信用形成の世界は、そう簡単にその閾値を越えられないのではないか?
なによりその信用経済をささえる実体経済は物理的なやり取りに拘束されているわけで、その蛇口をいつでも閉められる存在としての国家とか政府がある、というのは軽視できないだろう。
もっとも、いま現在の金融資本主義というのも、実体経済と大きく乖離したある種の信用経済で、その媒介と源泉になっているのは本書でもテーマとなっている「お金」だ。
そのお金を介さずに、信用だけで社会を廻していける可能性はないのか?というのを探っているのが本書だと思うのだが、そういう意味では可能性はゼロではないと思う。
要は、そのオールドプレイヤーたちにいかに(言葉は悪いが)「利」を喰わせてやれるかどうか、或いは「これまでのやり方は割に合わない」と思わせられるかどうかが、そういった新たな社会へ移行するための鍵なのではないか。
つまりそういったいままさに「利」を喰らっている=既得権を手放したくないが故に「妨害者」となる者たちに、いかに社会的なムダにならない形で利を喰わせてやれるか、というのもその一つのやり方のようにも思う。
(台湾統治時代の阿片一掃政策みたいな)
こうは書いたが、著者はM&Aなどの外資が支配する金融資本主義の文字通り修羅場を潜り抜けてこられた方のようだ。
おそらく、ここに書いたような現実を承知の上で、さらにその先に見える「お金」の介在しない「信用」の世界を、実感として強く持ってらっしゃるということなのだろう。
それは頼もしいことだし、自分も出来ればそういったことに積極的な加担―までは出来ずとも、少なくとも邪魔をするような存在にはなりたくない。
ここに書いてあることが実現するか否かはわからないが、少なくともあるべき未来の、一つの大きな方向性を示していると思う。
※3/19:一部内容が別書のものと混同していた部分あったので該当箇所を訂正。