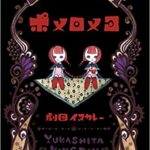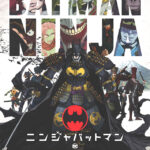日本のマンガ・アニメを中心とした膨大なソフトウェアというのは、なんだかんだ言われながらも、この国の大きな資産だと思う。
ただ昨今、そういう持ち上げ方は日本人の自己満足だ、クールジャパンなんて国外では誰も言っていない、アニメ・マンガが売れているのは一部のオタク層だけ―そういう言説もカウンターのようによく聞こえてくる。
事実そうだろうな、と思わないでもない。
ただそれでもやっぱり、これって潜在的に膨大なソフトウェア資産であって、その土壌というのはなかなか他の国が意識して真似られるものでもないと思う。
そんなことをこれを見てあらためて思った。
ニコニコ動画でたまたま見つけて、ただただ感心しながら見ていたんだけれども、一見オフィシャルに見えるこのトレーラ、第三者が本編を切った貼ったして勝手に作ったものらしい。
全然違和感がない・・・。
映画は実際に作られるらしいし、全話見たあとだからかもしれないけれども、非常に良くできてると思う。
例によって「野生の公式」だの「公式潰しw」など賞賛のコメントがついているが、これって実はある種膨大な”蓄積”の上でできあがってる。
本編は言うに及ばず、いわゆるこういう映画らしいトレーラを膨大な数を見て、その編集上のタイミングを身体で覚えている―そう、そういう身体性で反応できるレベルまでみてみて見まくってるっていうことだろう。
加えて、日本国内のアニメーションというのは、手塚治虫のころから予算に悩まされた結果、作画枚数を減らしたリミテッドアニメーションの表現が独自の進化を遂げているが、そういう”文法”―ある種のパターニングが、それに拍車をかけているところも大きい。
それはこの膨大なマンガ・アニメ文化の流通量に支えられて、ある種の表現作法として文化的に―意図せずに―継承されている、ということだろう。
(これはよく言われるように漢字文化圏―漢字もある種のパターニングである―であることももっと深いレベルでは横たわっている)
このMADにしても、ハイ・アマチュア或いは(僅かではあるが)実際のプロの可能性もあると思うが、いわゆる「素人」でもあり得るレベルだろうな、というふうに感じる人も多いだろう。
ただ、このレベルが”素人でも充分あり得るよね”といえるのは、やはり日本ならではないかなあ、と思うのは自分の贔屓目でしょうか?―こと二次元メディアに関しては。ちょっとそんな感じがするんだけど。
VOCALOID関連の動画を見ていても思うが、要するにこういうものがでてくる土壌というのは、視覚文化の圧倒的な流通量と、それを再現するための技術(それを駆使できるだけの基礎教育)、その技術力を支えられるだけの社会的な経済力―そういったものが必要となる。
そういったものを実現できる層が、これだけ多くいる国っていうのは、実はものすごく限られている。
特にこういったハイレベルの洗練度を伴うもの、といえばさらにその間口は狭くなるだろう。
こういったサブカルチャー的なものが、実体経済の中でどれぐらいのインパクトを持つものかは知らない。
ただ、こういった”物語”を伴うものはそういった経済や貨幣的価値でははかれない物を、それを見た一定の人たちのなかに間違いなく残していくと思うのだ。
そしてそれは、間違いなく貨幣的価値的なものよりも、深く・長く、そして静かに影響を与え続ける。
その価値って、金銭に換算できないからといって、決してバカにできるものでもないと思うんだけれども―。
そしてこと国内に関しては、これは間違いなくある種の文化資産である。
ある種のパターン化されたもの、その膨大な反復の中から生まれてくる、さらに洗練された新たなものたち。
その中から育まれたものは、視点を変えて、別の分野でも活きてくる。
トータルで見ていま日本のこういった文化は、間違いなくそういうレベルになってきている。
そう思わざるを得ない。
お・ま・け
ふ、ふ、腹筋ねじ切れるwww
本編ご覧になってない方は、見てからのほうが破壊力倍増なので、ぜひ本編後に。
若本氏がネタキャラになっているというのは伝え聞いていたけれど、ここまでとは・・・。
自分が一番アニメ見てた中高生のころからの大ベテランの方だと思うんだけど、い、イメージがw
ダンバインのアレンとかエルガイムのリョクレイとか渋いキャラばっかりだったはずなのにw