これも昨年見ていた分。ばたばたしていてレビューできていなかったので改めてここで。
フリーランス記者?のタレクは、新聞広告に載った”2週間の実験”の募集に興味を引かれ応募する。その実験は、被験者を囚人と看守に分けて、経過による心理的な変化を観察するというものだった。
高額な報酬に釣られた各々の被験者たちは、最初は気楽に構えていたが、些細なことから看守側に回った被験者たちの暴走が始まる。
最終的に、実験は研究者側をも巻き込み、思わぬ方向へと暴走していくのだった・・・。
最初にみて”ありゃ?”と思ったのは、言葉。
そう、これドイツ映画だったのね。
タイトルの「es」というのも、ドイツ語で「これ」とか「それ」という意味と、心理学用語での「無意識層の中心の機能」という意味もあるらしい。
(原題は別でそのものずばり”実験”というドイツ語がついとる模様)
ドイツ映画にしては、主人公の青年がぱっとみてわかるドイツ系ではなく、中東系っぽいのは、移民ということなんだろうか。(トルコ系?)
最初は記事のネタになる、ということで積極的に引っ掻き回そう、としていた節のある主人公・タレクだが、それが思わぬ方向へどんどん転がってゆく。
その暴走していく看守側の、主要人物がもろドイツ系っぽい顔のキャスト。
このあたりは意図的なのかもしれない。
内容はネタばれになるので、詳しくは書かないが、これはドイツならではの映画といっていいと思う。
(ただし原作的なものとして、1971年スタンフォード大で行われた実験を元にした小説『BlackBox』があるとのこと)
そう、ある種ナチスやアウシュビッツへの暴走もこういった些細なきっかけからエスカレートしていったのではないか?
そう考えさせられる内容だった。
その当たりがドイツ人らしいというか、なんというか、”普通の人”でもある我々自身にも、環境がそろえばこういう暴走をしてしまうかもしれない、ということを、まじめに考察した結果のシナリオとも読める。
それは上述の、先の世界大戦でのドイツという国のトラウマが、そういう傾向を無意識のうちに産んでいるから故の事なのかもしれないが。
先に取り上げた『ホテル・ルワンダ』でもそうだが、集団の中で発生した狂気の熱気のなかで、自分ただひとりで正気を保つということが、どれほどむづかしいことか。
またその空気は、ある一線を越えてしまったら、鎮火させることは並大抵ではない、ということを感じさせてくれる一本だった。
それほど、閉鎖集団の中の同調圧力というのは強いのだ。
いわんや”空気読めない”などという、同調圧力へのことばが、日常的に平気で使われるこの国においてはどうなることか―それが悪いほうに振れたときの事を考えると、正直ぞっとする。
まあ、そういうシリアスな映画ではあったが、被験者が当然むさくるしいオサーンばかりと思いきや、主人公と交通事故知り合うヒロイン役のお姉さんが、なかなか理知的な感じの顔つきの美人さんなのは良かった。
(役的にはちょっとぽわーんとした感じだったが)
ドイツの役者さんて、女性でもそれこそドイツ語みたいに、ガキガキゴキゴキごっつい、というか骨太なイメージがあったんだが、このひとはなんとなく良かったっすな。
同調圧力、空気―社会集団のなかのそういったものの作用に興味のある方は、見ごたえのある一本ではないかと思う。
あとコンプレックス持ってるヤツを不用意に刺激しちゃいかん、ちゅうこったな。
それが、どんなにくだらないように見えるものであっても。
それが、この映画のもう一つの教訓。


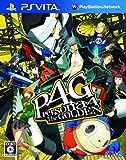
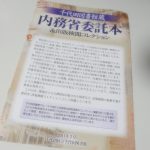
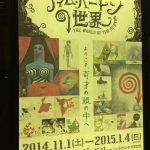
![澤野弘之 Live[nzk]003 2DAYS@zepp tokyo](https://www.thx-design.net/blog/wp-content/uploads/20150913_nzk003-150x150.jpg)