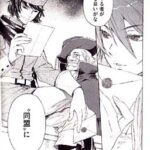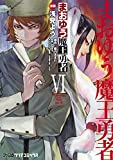いまさらながらはまったw
気持ちよく泣かせてもらいました(照)。
『まおゆう魔王勇者 1「この我のものとなれ、勇者よ」「断る!」』
wikiによると2009年9月から11月にかけて2ちゃんのスレッド上で発表されたweb小説らしい。
自分はこのまとめwikiでのまとめを、iPhoneのブラウザ(puffin)にて読んだ。
タイトルからもわかるように、ドラクエなどの日本型RPG的な設定・世界観を援用した作品であるが、その古典的なディティールから想像される物語とは、全く異なっている。
前述のようなRPGでなら最終局面に相当する、勇者と魔王の対決シーンから始まるのだが、それが表題にもなっている
「この我のものとなれ、勇者よ」「断る!」
の部分だ。
一見、そういったRPGにありがちなセリフで、通常ならここから最終決戦→魔王を倒して物語の終了、となるわけだが、この物語はちがう。
魔王と勇者、その二人が出会ったことから、物語が「始まる」のだ。
魔王の悪事を言い連ね、剣を構える勇者に、この戦いの裏で起きているであろう事実を数字を持って教え、その上で魔王は勇者に言う。
魔王「私は、まだ見たことがない物が見たいんだ」
勇者「……」
魔王「勇者になら、判るかも知れないと思ったんだよ」
勇者「何を、だよ」
(中略)
魔王「『あの丘の向こうに何があるんだろう?』って
思ったことはないかい? 『この船の向かう先には
何があるんだろう?』ってワクワクした覚えは?」
勇者「そりゃ……あるけど。わりと、沢山」
魔王「そうだろう? 勇者だものな!」
勇者「何でそんなに嬉しそうなんだよ」
魔王「だから、そう言う物が見たいんだ」
以降はぜひ実際に、まとめwikiを読んでみたり、web連載のコミックをみたりしてもらいたいが、ここでつかみは十分、そして思いもよらぬ、文字通りの”大河ドラマ”が繰り広げられていく。
(リンク貼っておいたファミ通のwebコミックなどは、最初に世界のイメージをつかむ意味で一話だけ読んでみるのもありだろう)
もう、つぎのドラクエこれでいいんじゃね?というぐらい(笑)。
ただこのweb小説がそれだけのものなら、これだけ大規模な書籍化やコミカライズ(都合3作品ぐらいコミックとして現在連載が立ち上げられている模様)がされるはずもなく。
なにが、違うのか―?
<「経済」リテラシーの入門編として>
珍しい、というか重要なのは、この魔王が「自分は契約至上主義者だ」と語るシーンからもわかるように、本作は、そのかなりの部分を経済とその仕組みに関する記述に字数を割いていることだ。
(最初はそれがやりたかったのではないか?と思うぐらいだ)
もちろん、創作、それも発表時点ではプロでもなんでもないアマチュアの手によるものだが、いまだにこういった社会とそれを動かす経済の仕組みが苦手な人の多い、日本人にとっては、基礎的なレクチャーとしては有用だと思う。
正確かどうかはいざ知らず、こういったニュアンスになじみを持つこと自体が、若い読者の経済リテラシーを高めることになるだろう。
本作は、この傾向が全編にわたって―最初から最後まで、ほぼ満遍なく貫かれている。
で、さらにすごいのが、だ―。
そういったものを軸におきながらも、この手のヒロイックファンタジー(英雄譚)、或いは戦史モノの小説としてもすこぶる面白いのだ。
なによりストーリー上、盛り上がるところで、これほどはないだろう、というぐらいに盛り上がるセリフをスパーンと入れてくる!
いやー、もう、これ盛り上がらざるをえんだろう(笑)。
そういう意味で一級のエンターテイメントなのだ、この著者の同様の作品が続けて商品化されたというのも良くわかる。
その上で、この方、かなり博学かつある種の哲学を持った方だとお見受けした。
<「教育と伝承」の物語>
それを強く感じたのは、本作は、魔王と勇者以外にも、たくさんの重要な登場人物が出てくる、ある種の群像劇なのだが、その関係性の多くがいわゆる「師弟関係」で結ばれていることだ。
主人公の魔王自体が「図書館族」という設定。
そしてその望んだ「丘の向こう」を見るために、その旅路の途中で、多くの彼女にとっての「弟子」となる存在を残してゆく。
そしてその「弟子」たちは、いつしか彼女の意を体現するものとなり、その蒔かれた種は次々と花を咲かせてゆく・・・・・。
そういう、教え・伝えること―「教育と伝承」の物語でもあるだ。
そして「”あの人”の弟子なんだから下手なことはできんのよ!」とでもいったある種の誇り。
そのポジティブな信頼と愛情が、それぞれの登場人物たちの間に、光の糸を紡いでゆく。
そういった、”善意と信頼”の結晶が、破滅に崩れ落ちかけている世界を救おうと、苦闘する物語―それが本作だ。
必要な戦いは戦うが、ほんとうにそれは”必要な戦い”なのか?
そういった問いを常に忘れない登場人物たちが共闘する姿というのは、いまのこの豊かな、けれどそれが崩れ始めている日本や欧米先進国の裕福な若者たちにとって、もの凄くリアリティのある物語となりうるのではないか?
文字通り、心優しき世代のための新たな”神話”になり得るだけのポテンシャルはあるのではないか?
個人的にはその可能性を、強く感じた―。
<「対」であること>
実は自分は、発表当初、この冒頭の部分をなにかのリンクでちらと読んだことはあったのだが、うっちゃっておいた。こんなド真面目な話ではなくギャグか何かだと思っていたからだw
オマケに魔王が巨乳の萌えキャラなんてぜんぜん知らんかったしw
で、ふつうなら「はん、またそういった”萌え”キャラ頼みのオナニー作品か」と上から目線で終わらせていた可能性も無きにしも非ずだったのだが、何故そうならなかったか。
これはたぶん、こういう”対”の存在でなければいけない物語だったからだろうと思う。
それは読んでいただくと、おそらく納得いただけると思う。
先ほど「師弟関係―教育と伝承の物語」だと書いたが、それと同じく「対」の物語でもあるのだ。
作者はなかなかそのあたりのこと、わかってらっしゃる方かとお見受けした。
(ただしエンディングは・・・これも自分は「2系統の発生」の意味で「対」であると理解したがw)
いや、こんな人がまだまだ野にごろごろいるんだねえ、
世界は広いわ―。
と、まあかなり気ままに紹介してみたが、肌が合うようなら、通勤通学時間の合間にでも、一読されてみることを強くオススメする。
それだけのなにかを見せてくれる、この恵まれた終末の世界ならではの良質の物語だ。
※2022/06 標題の表記を統一、リンク切れを修正