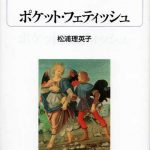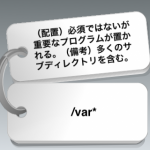松浦理英子の描こうとしてきたもののある種到達点のひとつだろう。
デビュー作以来、著者が一貫して求めてきたのは性器的なものを除外した、身体感覚を伴う愛情というのはあるのか?といっても良いかと思うんだが、そのテーマにおいて本作が一番純粋に成功しているといえるだろう。
本作ではタイトルどおり自らを「私の魂は半分犬でできている」とさえ思っていた主人公・房恵が、謎の人物・朱尾によって本当に小さな牡犬の姿に変えられてしまい、「あの人の犬になりたい」と思った陶芸家・梓のところへもらわれていく、といった舞台仕立て。
これらの言葉面だけを読むと下卑た想像をされる諸兄もいらっしゃるかと思うが、この本のすごいところはそんな比喩ではなく、それが本当に言葉通りの意味である、というとこだ。
(それを描写してしまう松浦理英子のストイックな筆致がすばらしい)
一見ファンタジーかSFかのような設定だが、そこが作者の筆力と、途中より登場してくる梓の兄・彬の存在が全体にいい意味での重さを与えている。
この彬の存在は、犬となる房恵とのある意味対比なのだが、これがなかなかえげつない。
恐らく読まれた方は皆そういった感想をもたれるかと思うが、作者にとってはおそらくいま世間一般に広く流布している人間の愛情なんて、突き詰めればこういうところへ行き着くんじゃないの?という皮肉に読めなくもない。
(そういう感覚は忘れずにおきたい)
これまでの松浦作品は冒頭にあげたテーマを表現するため、同性愛やら奇形に関するところまで書き綴ってきたが、それでも突破できない、読者の意識の中に頑強に組み込まれている「既成概念」を飛び越えるために”犬身”が必要だったのだろう。
(既成概念のまま表面だけ読む人たちには、これまでも、フェミニズムやらレズビアンだけの作家と読まれてきただろうから)
そしてそれはみごとに成功している。
更に本作がすごいのは、そういった文学的なテーマにブレないうえで、エンターテイメントとしても非常に読後感がよいのだ。こういったハッピーエンドなエンディングが松浦作品でみれるとは!
そういう意味も含めて、本作は松浦理英子、現時点での最高傑作といっても良いのではないか。
『親指Pの修行時代』も当時ベストセラーにはなったがそれは作品の設定に対する下卑た好奇心からだろう。
あの本は決してそんな好奇心だけで読みきれるほど軽いテーマを扱ってはいなかったと思うが、エンターテイメント性もあった作品なので売れたんだろうなあ。
そして本作は個人的にはかなりビジュアル化向きの作品ではないかとも思えた。
それぐらい(いい意味で)作品世界が明瞭なのだ。
勝手にキャストを想像してみる・・・
房恵は・・・上野樹里だとしゃべりすぎだな、宮崎あおいか。なんとなく犬っぽいし。
朱尾はミッチーかがGACKTか。面長ということなら前者なんだが、ミステリアスさということでGACKTだな。
梓は・・・うーん、眼鏡掛けてるイメージではあるんだよね。
ちょっとはずれるんだが、容易に心を覗かせない・植物的な印象、という意味では意表をついて仲間由紀恵あたりが面白いかも。(こんな汚れ役、できるかどうかは別として)
彬と母親は難しいな、てか自分日本人の役者知らなさ杉www
・・・という具合に、ひとりキャストを想像して楽しませてもらった(苦笑)。
そして案外これは日本だけでなく外国でもニーズがある物語のようにも思う。
むしろキリスト教圏にこそ必要ではないか。
ただ、その強固な男女の役割文化の前には、本作は、文字通り悪魔の所業に映るかもしれないが。
(逆にいうとだからこそ意味がある)
一見シンプルかつクリアーな物語だが、その下には毒がたっぷり含まれている。
ただその毒というのは、作者が盛ったのではなく、我々の作ってきた社会が澱のようにためてきた毒だが。
まあ毒に当たってものが見えるようになるということもあるし(苦笑)。
そういう怖いものみたさの人は是非どうぞ。
読むひとによっては、何も感じずに、単なるエンターテイメントで終わるかもしれないが。
ある意味リトマス紙的な作品とも言えるかもしれない。