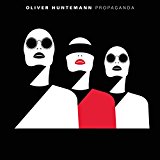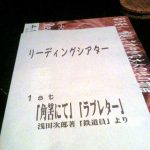今年の年初に久しぶりに「たまたまYoutubeでみて」というパターンで購入。
こういうどテクノというのもたまに聴くといいもんですな。
Senso Sounds (2017-10-20)
ネットで調べてみるとジャーマン・テクノの重鎮的な感じのアーティストっぽい。この手のジャンルのミュージシャンにありがちだがリミキサーとして有名どころとコラボしてるそう。
アルバムとしては昨年末リリースの最新作ということらしく、音は非常にミニマルで、シンプルに耳にひっかかってくる音色を厳選し、最小限でトラックを構成しているという印象。
この手のアーティストというのは、一昔前は音楽雑誌などで断片的に取り上げられるのをユーザー側が自分の経験値と”野生の勘”で探し当てる感じだったかと思うのだが、いまはもうそういう紙媒体が当てにならなさすぎ+瀕死の体(てい)なので、該当シーンに対してタイムリーにフォローしていくのは―こういったYoutube的な間口は広がっているにもかかわらず―逆にかなりむつかしくなっている気がするなあ、個人的には。こういったシーンそのもの追える人というのは現地の言語含めての理解が必要なはずで、それを考えるといまそういう追っかけ方ができるのはすごく限られてるんじゃないか、特に言語的ハンデの大きい日本人では。
で、個人的に丸ごと聴いてみたいと思うきっかけとなったのは以下のトラック。先行シングルだったみたいですな―このあたりちゃーんと制作者側のたれた釣り針に釣られてるわけでw
ブレイクからの低音がすごくカッコいい。こういうジャンルでかつミニマルな構成でのトラックというのは音色の選択が曲の魅力に占める割合がすごく大きいと思うんだけど、さすがうまいよなあ。
この手のテクノ的な曲というのは一見素人でも作れそうな気もするんだが、実際やってみようとするとすごくむつかしい。ある意味「引き算の魅力」というか、シンプルにそぎ落とせて、冷静に全体の幾何学的な構造を意識し、自分の感性が引っ張られないようにしつつ、過不足なく構築していかなければいけないので。
以前からある種のジャンルの音楽には、数学的な才能のある人のほうが向いているんじゃないかという気がしているんだけど、この手のジャンルはある種その典型という感じか。矛盾するいい方になるが「ロジカルさという”感性”」というか。
たまにこういう普段の自分が追いかけていないジャンルを博打で購入してみるというのも大事ですな。20代のころはよくそういう買い方をしていたんだけども、おっさんになるとつい億劫なのと、食指が動く頻度が少なくなってきて、このあたりは意識的に維持しておかないと落ちる能力なのかも。
なにはともあれ久々にこういう典型的なトラックばかりの一枚で聴いていてすごく楽しかったです。
Senso Sounds (2017-10-20)