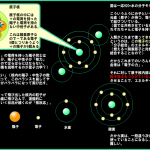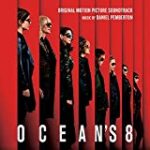たまたまもっていた角川の株主優待にて。
売り上げランキング: 4,336
光秀、愚息、新九郎という偶然出会った三人の奇妙な関係から描かれる”明智光秀”像。光秀そのひとではなく、愚息・新九郎という彼を傍観するキャラクターによって、これまでとやや違った視点からの明智光秀を描いている。
本作がこれまでの明智光秀を描いた多くの作品と異なるところは、二点ある。
まず第一はその「視点」だろう。
本作は光秀自身や歴史上にその記録のある人物などからではなく、”怪僧”愚息、”笹の葉流”新九郎というキャラクターを設定し、彼らのフラットな視点から、身分にとらわれない”友人”としての光秀を傍観するというスタイルをとる。
ここでのポイントは官位身分などにとらわれず、素っ裸な「一個人」同士の関係として、三人の友情が描写されているということ。
得てしてこういう描写は臭くなりがちだが、本作はそのぎりぎりのところでそれを免れている。それは登場人物の一人・愚息の一見偏屈にみえるその絶妙なキャラクター造形にあるだろう。凡人から見れば「めんどくさい」理屈を振り回す、だけど人物として魅力的、という彼のキャラクターがあったからこそ、世俗の掟に左右されない、独立した一個人同士の友情という描写に説得力があった。
二点目はタイトルにもなっている「定理」の部分。
作中で使われているものの一つは「モンティ・ホール問題」というヤツらしいが、要はよくある数学的なうんちくというか、そういった人間の一般の感覚ではひっかかりやすいが数学的に考えるとその裏にある正しい答えが見える、という類のものである。
この部分がある意味本作品の最大のウリの一つで、この部分をもって読者をうまく引き付けている。
愚息が提示するこの命題を通して光秀が出世の糸口をつかむ前後までが、ある意味本作のクライマックスとなっている。なので「光秀の」とついているが、明智光秀その人の半生をすべて描き切っているタイプの作品ではない。
面白い作品であったが、そういうところ少し羊頭狗肉感を感じなくもない。
加えて光秀のキャラクターがあまりにも現代風というかいまふうの「優しさ」で描かれている―要はへたれな感じで書かれている―のも、リアリティという面ではどうかなあ、という気もする。
ただこれはけっこうポピュラーな光秀像の一つでもあるので、好ましく感じる人も多いだろう。
(やや弱すぎるきらいはあるが、自分も決して嫌いなタイプの人物造形ではない)
また個人的には細川藤孝の描写は膝を打つ感じだった。本作での藤孝の描写は自分のこれまで想像していた藤孝像をピタッと言い当ててくれてその上を行く。
少ない描写ではあったが、ここは満足だった。
基本良い作品で楽しく読める。しかしこのようになんかひっかかったような一文を書かざるを得なかったのは―広告なのか、それが大勢の素直な反応なのか―本作の評を見た時に散見される「三人の友情に感動した!」的な反応のせいかもしれん。
確かに一見そうも読めるんだが、なんとなく俗世の垢にまみれる光秀を、残りの二人が(世間のしがらみという垢を背負っていないが故に)上から見ているようにも読めるのよなあ。
俗世から離れる、世捨て人である、というのは一見日本人的なメンタリティからするとある種の理想ではあるんだが、世塵にまみれない=立場的には同等ではないわけである。
この部分、少なくとも決してフェアではない。
だからこそ光秀はふたりに会いに来る時は、その世俗の立場を捨てて、あえて一人でやってくるわけだが、三人の友情、ということであればそこが描写の核にならざるを得ないはずで。
しかしそれに関する描写は―とくに光秀が仕官してからのそれは―成立しない、というか構造的に描写し得ない。なぜならその人生の大半を世俗に生きることを選択した男が、そういった”世俗を捨てた場所”で語れることはほとんどないだろうからだ。
だからこの三人の”友情”が顕著に示されるのは、結局世俗での切所働きをしようとしている光秀の窮地を残りの二人が救うという部分の描写にならざるを得ない。
かといって、それぞれ違う立場を選びとっているということと、これまで培ってきた友誼との間での葛藤がたっぷりと描写されているわけでもない。
(葛藤がないのはそれぞれが、それぞれの友情とそれぞれの立場に立っていることを、両方とも腹をくくって「自らのこと」として選択しているからだろう)
なので”友情”という一見きれいな言葉で語られるとなんかもにょっとなるのな。
ここは作品が悪いわけでも、作者が悪いわけでもないので御留意を。
もし本作のなかの友情を別の言葉で表すのなら、ある種の”哀愁”とでも言えば良いかなあ。
かつては同じ世俗から切り離された同類だったヤツ(光秀)が、その世塵の中に戻り、その世塵の中でもがき、それでも精一杯生きた―それを傍観していた二人の”哀愁”。
自分にはそのように読めた。
そして立場が違うが故に基本傍観という一線を引いた付き合いをしていた二人が、その彼が亡くなってから=彼がその立場の違いから開放されてから初めて、傍観者たることをやめようとしたのがラストの藤孝との対決シーンだろう。
ここは確かにまぎれもない友情である。
数学的な定理をうまく使っていたり、いわゆる”道々の者”的な身分に捉われない独立した個人的な描写には清涼感がある。
ただ、それが故にやや人間の感情の熱量、そのダイナミクス故の快感という点ではやや薄め。
そういった作品である。
個人的にはもう少し熱量がほしかったが、暑苦しくない分、こういった歴史モノのジャンルをふだん読まないタイプの方々にはちょうどいい読後感があるのではないかとも想像する。
一読してみて損のない一冊といえるだろう。