twitterでどなたかの発言で出ており、別件ついでにいってみた。
「検閲の基準 ―発禁になった本、ならなかった本―」
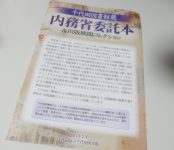
内容自体は、図書館の展示スペースの壁面を1面とガラス展示台からなるミニマムなもの。
おもに明治以後~戦後GHQに解体されるまでの内務省委託本(法律で献本が義務付けられている)をメインに、担当者がどう検閲を行っていたのか?というところをまとめている。
まず、千代田区立図書館自体が初めてだったんだが、九段会館のある交差点を南へ(神保町へ向かって右手)へすすみ、しばらくいくと千代田区区役所があり、その9、10階が図書館。
さすが日本の中心中の中心ともいえる千代田区だけあって、区役所自体綺麗な建物。1階のフロアなどではテーブルと椅子が窓際にあって本読んだりしている人で埋まってた。自習とかにも使えそう。
この建物には合同庁舎も一緒に入っていて、そちらには警備員さんが立ってたりする。
1階か2階からのエレベータを使って該当階まで。
エレベータを中心に、左右が図書館フロアで挟まれているような感じになっているが、そのエレベータの出口方向に当たる奥のほうのスペース壁面でこじんまりと展示されていた。
検閲、特に戦前のそれ―というとなにかこう暴力的な響きに感じてしまうが、そういった単純な、イデオロギー的な白黒のある展示ではなく、かつて内務省が行っていた検閲そのものをなるべく正確に振り返ってみようという感じの内容だった。
(監修されている中京大の浅岡教授の研究がその方向である、ということだろうか)
なので、その検閲に当たる試行錯誤―というか、非常にあいまいな文言ではあるけれども、法律としてその規制の元となる条文が存在するわけで、それに照らし合わせてどう判断するか?という葛藤があったんだろうなあ、というところが見てとれるのは面白い。
そして、いまの基準で見ると「なんでこれが?」というものがあったり、逆に「確かにいまの世の中だとやり放題だけど、本来はよろしくはないよなあ」と思うことも。
なかでも大笑いなのが、井原西鶴の作品など、一部露骨な描写の部分が当時では検閲に引っかかってるんだが、それでも出版すべく1ページまるまる伏字とか(笑)。
なんか余計想像してしまってわらえる。
また政治的なものに関しては、やはり共産党系のものが大きく引っかかっているようで、逆に言うとそこから当時の共産党の世間からの目、またある種の実態が反社会的組織に該当するような性格を帯びていたのかなあ、などとも想像したり。
ただ当然のごとく、こういうものごとの善悪の基準というのは、時代時代によって移り変わる。
いまは自由だとも言えるし、逆に言うと、風俗の紊乱これ極まれりともいえる。
(ネットで時間を潰していると、時々あまりにもひどいものにも不可抗力の交通事故のようにまれにぶちあたったりもする)
だからといって、それを「法律」という強力なツールで縛り、かつ、それが戦前のそれのように、解釈者次第でどうとでも取れるあいまいな文言で出来ていると、ほんと恐ろしいことになる可能性がある、というのは、この穏やかな展示で、逆に良くわかった。
そして、こんなネットの時代である以上、もうこういった縛りというのは、良くも悪くも実態として機能しない時代にはなってるように思う。
表現は自由であるべきだ。
ただそのためには、やはり表現者に、それなりの矜持というものが必要だよな―いつの時代でも。
そんなこんなを考えた。




