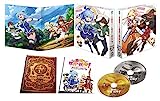なるほど、と思う箇所もあったが、後半は真面目に読む気失せて流し読みしちまいました。
昨年末帰省していたときに、関西ローカルの『たかじんのそこまで言って委員会』のパネラーとして筆者が出ていて、なかなか筋の通ったことをいうな、と思ったので、ご祝儀がてらに読んでみたわけですが・・・。
前半は確かに面白い指摘が多い。
特に、価値を創造しないところに消費はできない、政府は価値を創造できない、価値を創造できない政府からのお金(社会福祉など)は結局政府を介して隣人のお金を奪っているだけだ、というのはなかなか。
そして、GDP=国民が創造した価値であり、そのGDPの59%にあたる予算を組んでいる政府は(価値を政府自身は何一つ創造していない以上)59%の消費税を国民に課しているのと同じだ、というのが本書のメインの主張の一つ。
ただ、読んでいて若干違和感を覚えるのが、余剰資金を社会福祉などに回さず、企業の投資として注入し、経済を拡大していくのが”本来の資本主義”で、それを行えば景気は良くなる、という点。
資本投下=経済の拡大、といくほど今の社会って単純かね?という。
その他、いろいろロジックが書いてあるんだが、あんまりすとん、と”腑に落ちる”感覚で納得できるものはなかった。
(自分には珍しく、同じ箇所をなんどか読み返してみたんだが)
そして、経済コンサルタントとしての”純粋な提案”として出てくるのが、アメリカと日本の併合てwww
この箇所以降、事実上流し読み(笑)。
ある意味非常に正直、かつ誠実に書いてこの結論、というのはわからなくもないんだが、この方の根底に流れている”原理原則至上主義”的なところが、なんか思考の幅を逆に狭めている印象。
読んでてわかるが”小さい政府””自由主義経済”が経済至上というファンダメンタリズムから導き出されているような気がして仕方がない。
そういう意味ではある意味清々しくもあるのだが、世界はもっと複雑で抑揚があると思うのは自分の気のせいか。
ただ、個人的には”小さい政府”というか、官僚主義を打破していくためには、彼らが抱え込んでいる許認可的なものを一つ一つ剥いでいくしかないんだな、というのが感覚的にわかったのは収穫だった。
所管の事業をもぎ取らずに、制度だけいくら変えてもダメだわ。
ただそれをしようとすると、政治家の皆様の御利権が失われてしまうのでマズーなわけね。
だからでしょう。ここまで改革、改革と叫びながら遅々としてその言葉のさすものが一向に進まないのは。
手放さないといけないんだね、きっとほんとはいろいろと。
クレクレ!と叫ぶことから自身も切り離さないと、たぶん沈む。
持ちきれないものをいつまでも抱え込んでいても、いずれ溺れるだけだ。