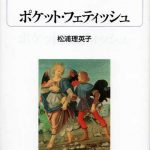真贋評価の錯綜している上杉氏、震災前2008年の著作。
近所の古本屋にて。
ジャーナリズム崩壊 (幻冬舎新書)
NHKでの短い勤務→鳩山邦夫氏秘書→NYタイムズリサーチャをへてフリーランス、というのが氏の経歴。
本書はそのNYタイムズ時代で知った欧米ジャーナリズムを基準に、日本のマスメディア、特にその記者クラブ制度の歪さを、各々事例をあげて指摘している。
上杉氏、という人物の評価の難しさに加え、人によっては「そんなに欧米のマスコミが正しいのか」という人もいるかもしれない。
ただ、欧米のジャーナリズムが日本のマスコミと徹底的に違うのは、記者の利便性ではなく、”真実の追究こそがジャーナリズムである”、という確固とした哲学が共通前提としてある、ということ。
(その上に個人的利益や待遇の追求というのは当然ある)
そして本書で繰り返し述べられている、この哲学―というか”掟”だよな―は少なくとも自分が大学で学んだジャーナリズム論と同じである。
(いちおうマスコミ関係の学科だったのですよ)
特に本書でかかれている、欧米紙には誤報検証欄が確固として存在している、というのは、何度見ても溜息が出る、うらやましくて。
こういう無謬性の否定がないと、組織や個人というのは自らの過ちを糊塗するために、どんどん誤った方向へと進んでいく。
(そんなことはない、ウチはやっている、という人もいるかもしれないが、ほとんどそれって”内部向け”だけなのよね)
いまの日本の官庁、大企業、その他大小さまざまの組織において、すべての失敗の原因はこれではないか、と思えるほど。
(しかしこれすらもある種「失敗に非寛容な日本社会」の裏返しであるともいえるが)
近年、インターネットの発達によって、ようやく残された最後の権力―マスコミに亀裂が走りつつあるが、この震災によってそれはさらに加速した面もあると思う。
それは無謬性にこだわってきたあまり、この錯綜する情報の中で真贋つかみきれず、みずからその無謬性の神話のずさんさを暴露する形で。
ただ、それでも日本人はまだまだ「お上」意識が強い。
そしてまだマスコミも「お上」であり続けている。
そこに亀裂をいれ、大きく広げて崩してしまうまでには、いま一歩及んでいない。
冒頭に書いたように氏は毀誉褒貶相半ばすることの多い、ある意味トリックスターのような人物だ、というのが自分の認識だが、それだけにまだまだ氏の役割は大きいのではないかと思う。
秩序感覚が大好きな方には、到底受け入れられない考え方だろうが、再生のための破壊には、”引っ掻き回す”人が不可欠―そういうこと。

![澤野弘之 BEST OF VOCAL WORKS[nZk]](https://www.thx-design.net/blog/wp-content/uploads/51rPCLZREuL._SL160_-150x150.jpg)