素晴らしい、そして壮絶な一本でした。
ただし日本ならではの映画かもしれない。
日本の「世間」ならではの異常な部分が、確実にバックボーンとして存在する。
ただその点を抜きにしても、作品としてのその複雑な構造が素晴らしい―すべてかリンケージしている。
(たぶんモノをつくろうとしたことのある人間にとっては、最高峰の表現レベルじゃないだろうか)
そしてそのリンケージの中で、同じひとつの行動が、ある視点からは正しく、ある視点からは邪悪にすら映る。
見ている最中「Downward Spiral」 という言葉が頭に浮かんだ。
(ご存知の通りNine Inch Nails ’94年の大傑作アルバムのタイトル)
物語のアウトラインとしては、我が子を殺された中学教師(松たか子)が辞職の
挨拶として、教室で淡々と独白の「告白」をしてゆく―そういう形で進む。
―そしてそこには我が子を殺した生徒もいた。
あまりにも凄かったので、たぶん二回分くらい分量書いてしまいました、サーセンw
ネタばれはないように書いている―というか抽象論になっているが、興味のある方は
作品を見られてから読まれることを強く強くお勧めします。
(ヘンな色眼鏡をつけてみるともったいないので)
【抽象論的に】
冒頭、その淡々とした語り口からすると若干突飛にもみえる仕掛けが出てくる
が、全編を見た後ではその配置のうまさが冴える。
(加えて中学一年~二年という年齢設定も実は抜群だ)
そしてその淡々とした「告白」とコントラストをなすような生徒たちの狂騒。
それが話が核心に進んでいくにつれて徐々に静かに一点へと収束していく。
静かな―だが、もの凄い圧力感。
極彩色を得意とする中島哲也だが、その能力で創るシックな画がそれを更にブーストする。
この冒頭の、松たか子の静かな語りと、対比するように描かれる教室の狂騒感をみて、
強く感じたのは、
誰もが”向かい合って”いるようでいて、向かいあっていない(=”コネクト”していない)
ということだ。
(※コネクト=「ちゃんと相手の目を見て話す」的なものと理解してください)
相手が目の前にいても、自分の気分でしか相手を見ていない=ほんとうには相手を”見て”いない。
自分の頭の中だけで、勝手に相手の「像」を組み立ててそれに向かって返事をしている。
なのに「空気を読め」という同調圧力が、それを問題とさせずに、コミュニケーションとして成立させてしまっている。
―そんな空疎な関係。
出てくる登場人物のほとんどがこれじゃないだろうか?
誰もほんとうに相手に向かってしゃべっていない―空気の読み合い。
(親子ですらそうだ)
仲良く、楽しそうにしているのは表面だけ。
みんな「そうでもしないと退屈だから」繋がっているフリをして現実をやり過ごす―。
(そしてそれが見えないバカ教師)
そう、相手を”真正面”にみて、ただしく関係を持つには、自己肯定感覚がいる。
―相手に侵食されない、相手に否定されても「自分」がある、という自信・肯定感。
それがないから、誰かを否定することで自分を肯定する。
自分を肯定するための生贄を探す。
だから、ほんとは誰かとつながりたいのに、つながれない―その不安。
この教室を埋め尽くす狂騒の根本はそこだ。
そして結果、発生するの「ミーイズム」の嵐。
「Me!(私!)」
「Me!(私!)」
「Me!(私!)」
ミーイズムの世界は、一見どんなにたくさん人間関係があっても、基本、世界には自分しかいない。
上に書いたように、人間関係は他人を”見て”いるのではなく、”見たつもり”を自分の中でで組み立てているだけだから。
だからいくらでも他人に残酷になれる。
そんな集団があつまると毎日が「ハレ」の日。
まるで生贄を探しながら踊り進むサバトのよう。
(*1)
しかし一見楽しそうにみえるこれも、誰も胸にあいた穴は埋められない。
真に望むもの―その欠落を埋めてくれるのは自分に正面から向かってくれる”他者”だから。
誰か一人でもいい、自分に”正面”を向いて語りかけてくれたなら―。
しかし実はそれができるのは、自身で自身の孤独を引き受けることのできる人だけ。
寂しさのために他者を必要としない、不安を誤魔化すために群れない―その強さがいる。
他者や群れに頼らずとも、ブレない・侵食されない自分がある―。
作中、唯一、孤独を引き受けていたかもしれない少女は、少年にとって一縷の望みになるかもしれなかった。
しかし彼女のその光も、真暗闇しか知らずに育った少年の目に映らなかった。
自己肯定感の源泉―それは対価を必要としない”無私の愛”=母の愛。
これがどれほど大きいものなのか―間違いなくそれがこの作品のひとつのテーマにある。
(※ただしこれは父がその役割を担えたはずでもある→そこに日本の男どもの幼稚さがある)
それぐらい”母”の存在は大きい
そして、それが決定的に欠落している少年。
その少年の見えない、静かな慟哭―それが物語を駆動する。
「自由」や「権利」という美辞麗句を浴びて育ったミーイズムを体現したような母。
アイテムとしての子供。
そんな母が、ようやくちゃんと正面を向いて子供を見たとき―子は母を失う。
子を失った母と、母を失った子と。
ここまでにいくつかの屍を重ねて、少年はようやく母以外の他者と正面を向かい合う・・・。
最終的には一本の対立軸に収束していくが、誰が悪いのでもない―そういいたくなるようなラスト。
そして特筆すべき松たか子の素晴らしさ。
とくにラストカットのあの表情を出せる人というのはいま数えるぐらいしかいないと思う。
素晴らしかった。
(*1)
「ハレの日」・・・民俗学的な用語。「ハレ」(祝祭日)「ケ」(通常の毎日)の意。
ハレの日は少々ハメをはずすことも許される。「晴れ着」の語源。
「サバト」・・・・・欧州のキリスト教文化で言う「悪魔集会」のこと。
この日には悪魔や魔女が寄り集う集会があるとされる。
【孵れなかった子供たち―各論的に】
・「孵れなかった雛」―少年B
少年Bは、なぜ助かっていたはずの少女を殺したか?
少年Bは、当初自分を肯定してくれた少年Aが裏切り、せっかく得たと思った「自己肯定感」を再喪失する。
母に溺愛されていたにもかかわらず、少年Bはなぜ自己肯定感をもてなかったのか?
それは、彼の母は母自身の(ミーイズム)の作り上げた少年Bを見ていたに過ぎず、ありのままの少年B
そのものを見ていたわけではなかった。
(彼を正面から・ありのまま見てくれる=”コネクト”の欠落)
ある意味母という存在の延長=子宮から逃れようとして少年は母を殺さざるを得なかった。
かれは巻きついた臍の緒に絞め殺される前に、それを断ち切って母の子宮から逃れようとした。
(自他との区別)
そんな少年Bにとって、少年Aに否定された自身の存在を取り戻すためには、否定した少年Aの描く物語を
拒否する必要があった。
ある意味彼は母の腕に抱きしめられ、絞め殺された故に孵れなかった雛のようなものだろう。
ある意味いちばん報われず、いちばん哀れな存在だったかもしれない。
・「母を失った子―堕胎された胎児」―少年A
少年A―彼はある意味堕胎させられた子のようなものだろう。
堕胎=母の都合に沿わない存在としての子の否定。
それでも母は母、子はあくまでも母を恋う。
なぜなら子にとっては母とは自分の存在の「根源」だから。
自分には意味があるといってほしい、意味のある存在だと認めてほしい。
プリミティブな、そして痛切な祈り、あるいは叫び。
彼はずっと泣いていた。涙は流さずとも母を恋うて泣いていた。
この点に関しては誰も彼を責めることはできない。
彼の悲劇は、その自分を捨てた母に、怒りをぶつけることすらできなかったこと。
それぐらい彼は母を恋うていた―。
彼の最後の慟哭は、母を見失って泣き続ける赤ん坊のようにも見える。
※少年A、B、そのどちらもいえるのは「母」の不在―。
そしておそろしいぐらいの「父」の存在感のなさ―間違いなくこれがひとつの日本の世の中の病根だと個人的に思っている。
・「いつでも死ねる、いつでも殺せる」―ギリギリのところで孤独を引き受けている少女
根無し草のようにみえて、なんとか一線を越えず踏みとどまっている少女。
彼女が作中一番まともに映るのは、彼女が不安から目をそらさず、一人孤独を引き受けているから。
「先生、この教室は変です」
くだらない矛盾だらけの世の中、たまるフラストレーション。
そんな世の中で「いつでも死ねる、いつでも殺せる」という状況を得ることで、理解者のいない、
理解できない孤独な世界の中で、彼女は一人踏みとどまっていた。
昔読んだ本の中にこう言うセリフがあった。
「人を殺すことと人を殺したいと思う気持ちは全然別物です
殺したい気持ちだけなら人の器におさまる
一緒に生きていけるもんじゃよ」
だからこそ彼女は少年Aへ手を差し伸べることができた。
そしてだからこそ、同じ孤独を理解できる(と思える)少年に彼女は惹かれた。
ただ惜しむらくは、彼女の年齢では少年の孤独の深さを測るには若すぎた。
おそらく作中、唯一まっとうな感覚を持っていた人物。
もし彼女が生き残っていたなら、かなり素晴らしい女性になっていたと思う。
佳人薄命。
・「まだ生まれてすらいない」―その他のクラスメート他
もちろん作中に描写されていないだけでそれぞれの物語はあるだろう。
しかし、群れに混じって踊っている段階で、彼らはまだ自分”自身”を生きてはいない。
ある意味「生まれてすらいない」といってもいい。
(それを極端にカリカチュアライズしたのがウェルテル教師か)
そして、この先自分の身にひきつけて考える「なにか」が起こらなければ、
彼ら・彼女らはたぶんずっとそのまま―。
大半が、このあとをなんとなく生きて、なんとなく子の親になっていく。
そしてある日、自分の子供が大事件を引き起こしてはじめて気づく。
自分はこれまで生きてすらいなかったことに。
いや、少年Bの母親を見ると、そうなってすらも気づかないのかもしれない。
ずっと「生まれない」まま卵の殻の中で自分だけの世界の夢を見続ける。
大半のひとはそれでいいのかもしれない。
えらそうにこうは書いているが、自分もこういったところから逃れられているとも思わない。
主要登場人物「以外」の軽躁さというのは、ある意味こういった自分たちへの痛烈な皮肉ともとれる。
・「子を失った母」―主人公
この人物も複雑である。
彼女も、なにもなければずっとなんとなく生きて、なんとなく教師を続けていただろう。
そんな彼女にとっての「自分の人生の目覚め」はおそらく夫との出会いだった?
きっと劇的な”運命の出会い”とかだったんだろう。
しかし”魅力あふれる男”というのは大抵なんらかのリスクとワンセット。
(それに惹かれることは人間を”動物”としてだけみるなら間違ってはいない)
結果、彼女の場合みごと特大の「大当たり」を引いてしまった。
(むしろのこの時点が「自分の人生の目覚め」?)
そういう意味では、この物語に単純な諸悪の根源を求めるなら「善意を振りまく熱血
カリスマ先生―実は単なるヤリチン」という彼女の夫に行き当たる、といえなくもない。
(これが皮相的な見方であることもお断りしておく)
で、彼女自身もそういう状況になって、初めて自分の人生と正面向かい合う。
恐らく必死だっただろう。ただし初めて”生きてる”ことを実感したかもしれない―望む望まぬには関わらず。
その象徴としての愛する我が子―娘。
しかしそれをあざ笑わうかのように、彼女は我が子を失う―母は子を失くすわけである。
「孵れなかった雛」と「堕胎された子」が、親の愛を受けすくすくと育つ子を呪い、殺そうとするのはある意味必然だったのか・・・。
「子を失くした母」「教師」そして「復讐者」―そのすべてが混在となって彼女は我が子を殺した生徒と向かい合う。
そこで問われるのは「命って・・・」とあの少女も問い続けた問いだ。
「大切にされた命」を失い、それを奪った「大切にされなかった命」たちと向き合う。
大切にされる・されない。
命は大切というが、そこに軽重はあるの?
それに対する答えを、結果的に彼女は彼女の行動で少年たちに示していく・・・・・。
・「子を無かったことにした母」
もうひとりの「敢えて言うなら」諸悪の根源。
実は子を失った母と鏡像になっている。
・子を失う⇔子を捨てた
・夫と離別⇔ちゃっかり再婚
・娘を殺した子と正面向かい合う⇔我が子をまともに見ようとしない
「ミー」「ミー」「ミー」徹底してミーイズム。
世界には「私」しかいない。
他者を―配偶者を、子を、友人を―直視しない、大多数の日本の大人たち。
実は彼女は極端に誇張された、そのカリカチュアなのかも知れない。
卵から孵らず、アカデミズムという子宮の中で夢さえ見ていれば良かったはずの存在が
なまじ一人前のように外の世界と関係性を持とうとしたことがそもそもの間違い。
(この「アカデミズム」を「会社」とか「仕事」に置き換えると世の大半の男どもにもあてはまる)
卵の中にいるくせに一人前に子を孕もうとした。
そのうえで子がいると卵が割れてしまうことに気づき我が子を追い出し、また自分の殻の中に引きこもった。
それがどういう経過か、卵の外に出(本当に出たのかは知らないが)、ようやく自分の人生に向かい
合ったのは、殻に守られぬ剥き出しの我が身に突きつけられた、我が子の刃、それが自分の命を
絶つその瞬間。
ただ、その彼女の命を絶つことになるものの存在を、わかって手元においていたのなら、彼女は
ようやくそこでまともに我が子と真正面から向かい合ったのかもしれない・・・。
こうは書いたが(繰り返しになるが)誰が悪いのでもない。
見終わった後の感想はそれだ。
あと、作品そのものの感想とは違うかもしれないが
どんなに愛に飢えていても
孤独は引き受けなければいけない
正しい寂しさや不安は引き受けなきゃいけない
ただし人間は孤独だけでもいけない
正しく孤独を引き受けた上で
相手を真正面から見て
孤独でない関係性を
「本当のコミュニケーション」を
創っていかなければいけない
そこを見ないで
孤独を引き受けないで
相手を見ない関係性は
字義通り「関係」ですらない
それは寂しくないという
「そんな気がする」だけ
それこそが真の「孤独」だ
そう、あの少年たちの母のように
そういうことはこの文を書いてて思いましたね・・・・・。
この「正しい孤独を引き受ける」ことができていたなら
少年は少女の差し伸べた手を頼りに本当の愛情をもらえたかもしれない。
そういう意味ではどこまでも救いのない映画。
しかしあの見終わったあとの、決して不快ではない、えもいわれぬ感覚というのはなんなんだろう・・・。
ああ、凄い映画だったのに自分ごときの言葉で書くとなんと陳腐な!!(号泣)
そして音楽・・・やはりあの締め付けるようなあれは、Radioheadだったんだねえ・・・。
なのでこんなもん読まなくていい!
現物を見ろ、現物を!
こんなぺらい感想を越えた、素晴らしい感動がそこにはある。
現物を見ろ、現物を!




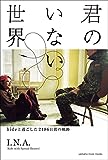
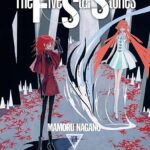
幸いなことに、観た後にこの記事を読ませていただきましたが、観る前にこの文章を読んでしまった方がいらっしゃったら、その方達が気の毒過ぎます。
感想(考察)が、作品よりも魅力的になってしまうのは程々にお願いしたいです。
最も、このブログの読者様達は、そんなこと解りきっているでしょうけれど。