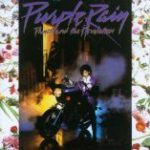司馬遼太郎の幕末以降のものは意識的に読まずにいたのだが、ちょっと考えるところもあって読んでみた。
まあほんで幕末といえばここからですわな、ということで新撰組関連のものを。
司馬遼太郎氏の作品は執筆にあたって膨大な資料をあたるせいか、ひとつのテーマに対してメインとなる作品のほかに外伝とか列伝的な作品も同時に存在することが多い。
この三冊では『血風録』が列伝、『燃えよ剣』が新撰組副長・土方歳三を主人公とした本編といえるだろう。
総じて言えるのは、時代がそうさせたとはいえこういった幕末の志士とか剣客というのはゴロツキやヤクザと紙一重だということ。それは剣客という武芸を糧に世を渡った連中だけでなく、攘夷論や尊王の思想を看板にした口説の徒も同じだ。(むしろこちらのほうが舌先三寸だけでこねくり回した理屈を振るうだけに余計に性質が悪いかもしれない)
しかしそういった普通の世の中では不要とされる底辺な連中の、暗い情熱が時代や社会の回天となる原動力になったのもまた事実だろう。
そういう意味からも、こういった”時代”が今まさに移り変わろうとしている時と場所というのは社会にとってもある種の青春時代であり、そこで流されたおびただしい血はそれ故の疾風怒濤の奔流―そういって良いのかもしれない。
で、そのなかである種の典型的な姿を世に見せつけてくれたのが、新撰組なわけである。
敵と見れば切り、士道不覚悟と見れば味方も切る―全てにおいてその命を白刃の上に置き、剣でのみしか語りえない連中。冷静に見ればただの殺人・暴力組織以外の何物でもない。正確な字義とは異なるが、ある種のアナーキスト・テロリストといってもいい。
『血風録』のほうから読み始めたのでよりそういった印象がつよく、正直最初は「うわー、やなやっちゃなー!?」そう感じた土方歳三。
彼はそういった時代の狂気を一身に集めた新撰組という組織の中心人物であり、ある意味彼=新撰組そのものといってもいい。そしてその彼を描いたのが『燃えよ剣』である。
しかしなー、これが泣かされたのよ!?
そしてそれは題にもある”剣”のそれではなく、雪という女性の存在である。
剣戟の道にしか自らを見いだせず、そこでしか生きていけないはずの男―自分でも人として何かかけているかもしれないという自覚すらある。そんな男がその”剣”以外の光を、わずかなひと時とはいえ持ち得たシーン。彼が唯一にて初めて人間としての”貌”をみせるそのシーン。そう、鳥羽伏見の敗戦のあと大阪での数日の逢瀬の前後のシーンですよ―ボロ泣きましたがな。
ひとはこういう暖かな思い出を一瞬でも持てれば、あとはそれだけで生きていけるのではないか―そう思った。例えその残された人生がどんなものであっても。
いや、しかし無骨な司馬遼太郎の小説で―それも一夜の逢瀬などというロマンチックなシーンで泣かされるとは思いませなんだわ。
ただ、それ故に函館での再会は蛇足とも思える。
司馬遼太郎は歴史の人物を題材に借りて、ある種の人間の典型を描こうとしてきた作家かと思うが、確かに本作の土方象というのはある種そういったところへ堕ちざるを得なかった、そういったところでしか生き得なかった男の典型と言える。(というか氏の作品の題材となる人物のほとんどがそうだな)
だからこそエピローグにあるように、函館政府の主要人物の中で唯一討ち死にしたのが彼だけである、というのも納得だ。
彼はある意味生きるべき時代に生きるべき場所を得てその生を全うした。その長短は関係ない。
ある意味本望な人生だったのではないだろうか。
久々にエンターテイメントとしても、司馬遼太郎に一本取られたような気分の作品だった。