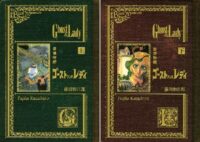掲載誌で連載時から読んでいたが、つどつど泣かされたのでこれは買おうと決めていた。
電書で購入予定だったが、所用で立ち寄った本屋で平積みになっていたのでおもわず前作のスプリンガルドの買い直しと合わせて三冊購入(苦笑)。
『黒博物館 ゴースト アンド レディ 上 (モーニング KC)』
『黒博物館 ゴースト アンド レディ 下 (モーニング KC)』
英国、ドルーリー・レーン王立劇場のアッパーサークルD列の端には、昼間公演(マチネ)の時にグレーの服を着た男が現れる。その”グレイマン”の噂を聞き、生きる希望を失っていた「彼女」は彼にとり殺してもらうべく劇場へとやってきた・・・。
スコットランドヤードの中にあるという秘密の博物館・黒博物館。そこに保管されている弾丸同士がぶつかったと言われる”かち合い弾”―そこに秘められた物語がいま語られる。
前作の『スプリンガルド』がより顕著だったかと思うが、この黒博物館シリーズはなんというか、昨今でいう伝奇ものという感じではなく、怪人二十面相やシャーロックホームズ―それらいわば小中学校の図書館にでも置いてそうな、ジュブナイルテイストあふれる意味での伝奇シリーズだ。
いろんな意味で「解像度」を求められる昨今のマンガやアニメ全盛のご時勢に、こういういい意味で理屈じゃないある種の「雰囲気」をもった作品を描くのは至難の業かと思うのだが、著者・藤田氏はそういったテイストを難なくやってのけている。氏の著作は他に邪眼は月輪に飛ぶしか読んだことがないのだが、同作にもそのテイストは感じたので、これは完全に氏の独壇場というか手慣れた作風ということかもしれない。
で、その藤田テイストによって今回語られるのはクリミア戦争のヒロイン「ランプの貴婦人」その人である。
しかし、当然ながらここで書かれている「彼女」のキャラクターはマンガとしてのキャラクターであって、実像とは異なる部分が多いとは思うのだが、そのキャラクター造形の底にドン、と横たわるその深い絶望の設定が実に見事で、これがある故に本作での「彼女」はとても身近で感情移入のできるキャラクターへと一気に昇華した。これはいまの日本社会の多くの若者たちも抱えているであろう「自己肯定感の欠落」をより過激にしてその根底に据えたことが最大の成功要因だろう。それによってこの19世紀クリミア戦争で活躍した「白衣の天使」とまで称された偉大な女性が、一気に身近で親しみのわく、悩み深き可愛らしい女性へと変わって、読者の目の前に現れる。
そして当初その彼女をとり殺すために付きまとっていた灰色の男(幽霊)・グレイがいつしか彼女を守る騎士(ナイト)となり、二人は奇妙なきずなで結ばれてゆく。
そして二人は戦争―そのあまたの戦場において、その根源である人々のエゴを体現する「生霊」と戦ってゆくのだ。
最近、自分も身近なことで「他人を支配し・コントロールしようとする人間―それもそれが肉親の場合が最悪だな」というのはけっこう実感していて、その意味でも非常にタイムリーな作品であった。
なにしろ本作での人間のもつエゴは、ジョジョのスタンドのようなかわいらしいものではなく、文字通り化け物のような姿の「生霊」としてその背後に立つのだ。
ヒロイン・フローは両親の社会的体裁を意識した猛烈なエゴの化け物「生霊」にその霊的な身体をズタズタにされ続けていた。そんな日々に絶望し、王立劇場の幽霊にとり殺してもらうべく彼・グレイと出会い、自身の「死」を覚悟した時から、彼女の中でなにかが変わり始める。
かたや舞台好きの幽霊・グレイはそんな彼女の変貌をみて、彼女がより深い絶望に至った時に彼女を殺すことで「最高の悲劇」とすべく逆に彼女を延々と守ってゆくこととなる。
最初は本気で彼女をとり殺すこと―それも深い深い絶望の淵で―それを望んでいたグレイだが、彼女の変貌に伴い、いつしか知らぬ間に彼自身も変わってゆく。そして「信じたものに裏切られ続ける」人生だった彼にフローの少年従者であるボブは知らずとこういうのだ「なあグレイ、あのお方は人を絶対に裏切らないんだよ」
そのアンビバレンツな関係性のまま、二人とその一行はある意味前線よりも悲惨な治療の現場を渡り歩き、最後の戦場・クリミア半島へ赴く。そう、彼らの最大の敵は最初からロシアなどではなく、味方の、それも前線での医療責任者であるジョン・ホール軍医長官だったのだ・・・。
本黒博物館シリーズは狂言回しとして博物館のキュレーターのおねえさんがシリーズ通して登場するが、別エピソードキャラクターや同作中人物が時間を経て作品の中で登場したりする。そういう意味では今回はおそらくそれに相当するのは決闘士の幽霊、シュヴァリエ・デボン=デオン・ド・ボーモンだろうか。ざっと見返してみた限り具体的な言及はないようだが、第一作目「スプリンガルド」のフランシス・ボーモンと同姓なので関連性があると思われる。
このあたりもそうなんだが、このシリーズの良いところはそういった関連性を含め、本編の登場人物がエピローグや後日譚といった形で必ず登場するという点。この演出が時の流れというか「歴史」を感じさせることとなり、本シリーズの魅力をさらに引きあげている。
そういったつながりを信じて「託して」いけるからこそ、このシリーズの主人子やヒロインたちの「善意」は受け継がれてゆく。そう感じられる。このあたり大人向けに作られたといいながら、ある意味下手なジュブナイルよりよほどジュブナイルらしかった『ガンダムUC』と通づる雰囲気というか空気感が感じ取れるのは、自分の気のせいだろうか。
とにかく本作はそのラストの演出がベタではありつつも素晴らしい。
ある意味舞台で始まり舞台で終わるという、素晴らしい一幕の「芝居」だった。
自己嫌悪に悩んだり、最近気分が落ち込んでるという人はぜひ読んでみてほしい。
こういう生きる力がわいてくるような作品というのが、ほんとうに「名作」なんだな、と自分はそう思うのです。