悪い本ではなかったが、自分的には若干浅く感じた。
日本の男を喰い尽くすタガメ女の正体 (講談社プラスアルファ新書)
深尾 葉子 (著)
最近、景気の不透明さのせいもあって、あるアンケートだと女性の専業主婦願望への回帰傾向が見られる、という報道を目にされることもあると思うが、本書はまさにそういった事情の背景にあるものを裏書している一冊だろう。
曰く、パートナーとなる男を数々の約束―箍(たが)で縛り、その男のサラリーや社会的なリソースを吸い尽くす。
箍で縛るが故に「箍女(タガメ)」、捕食されるが故に「カエル男」。
その歪さの根底にあるのはなにか?ということを問い掛けている一冊である。
タガメ女論についての更なる詳細は本書を読んで頂くとして―その例示や考察は的確であると思いつつも、自分的には若干浅く感じた。
一つは著者が、そういったタガメ女の生態そのものを研究するのが主眼ではなく、あくまでも最終章にある「魂の脱植民地化」という観点から、それを補強するための副産物として出てきた発想だからではないか?
なので、個人的に強烈に衝撃を受けた岩月謙司氏の『ダメ恋愛脱出講座』のような、女性のメンタリティの奥に潜む、底知れぬ暗闇のようなものを覗き込むような凄まじさは本書からは感じられない。
悪い意味でなく、持論を展開するために必要な、表層的なディティールを追っているだけのような気がする。
なので、実は考察としては面白い部分がたくさんあるのだが、正直あまり衝撃は受けなかった。
というか、本書の肝心の本題は最終章である「おわりに」の部分だろう。
他の部分がモノクロだとすると、ここだけはカラーページのような読後感だった。
その「おわりに」は首肯できるところが多々あるのだが、同時になにかそこにフェアネスさを越えた、個人的なイデオロギー的なものが透けて見えるような気がして、若干ひっかかる。
(これは本書の内容の考察にも加わっているという、安冨歩氏の言動などにも、時々それを感じるのだが)
もちろん、そういうイデオロギーを強固に持つ、ということそれ自体は歓迎すべきことだと思うのだが、そこに周りを(一応)はばかって、フェアネスの仮面をかけようとしているかのように感じるのが、なんとなく引っかかる理由かな―
それは、非常にうっすらとではあるのだが。
ただ、ご両人とも、部分部分では首肯できるところが多々あるし、なによりも、まだそんなにその著書に目を通せていない。
そんな段階で欲をいわせていただくなら、偏見に見られようが、気にせずもっと堂々と持論だけを吐き出したほうがわかりやすいんでね?とは思う。
(まあ、多くの人が手に取りやすい新書という体裁もあって、こういう文体を取ってらっしゃるんだろう)
そういう意味では、まだ絶対的な評価は下せない、保留、といったところか。
ただ、本書の段階だけでも、けっこう刺さる人には刺さる内容かと思うので、気になる方は手にとってみても損はないだろう。
多くの「箍」が今の日本にははめられている―。
そのことについては一も二もなく、同意するしかないので。





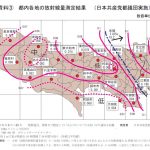
上げたり下げたりの評論ですが、結局、「浅いけれど結構面白い」ってことでしょうか。
好みとしては、深い感じがしてグサリと突き刺さる作品がお好きなのでしょう。
論理的説明を面白おかしく仕上げる作風というものにも、スイッチを用意されてはいかかでしょうか?
味わいというものは多岐にわたるので…。
はじめまして。コメントありがとうございます。
>好みとしては、深い感じがしてグサリと突き刺さる作品がお好きなのでしょう。
ご指摘のように、そういった傾向はあるかもしれません。
ただ、なぜ本項のようにふらついた一文になったかというと―本書の視点というのは、自分の持っていなかった発想なので、ああなるほどなあ、という感じで―感心して読ませては頂いたんです。
面白おかしく書いている、という点にもネガティブな印象は受けませんでしたし。
しかし「日本を喰い尽す」とタイトルにあるのなら、本書で主に書かれているもう一歩先のところまで言及がほしかったなあ、と。で、唯一それに相当する内容と感じた最終章が分量的に少なかったので、こういった書き方をさせて頂きました。
新書という体裁を考えると、分量的なところで仕方ない面はあると承知はしているのですが。
前菜がたくさん並べられて、メインディッシュがごく僅か―そういう印象を受けたので、こういった文章になった、そうご理解いただければ幸いです。