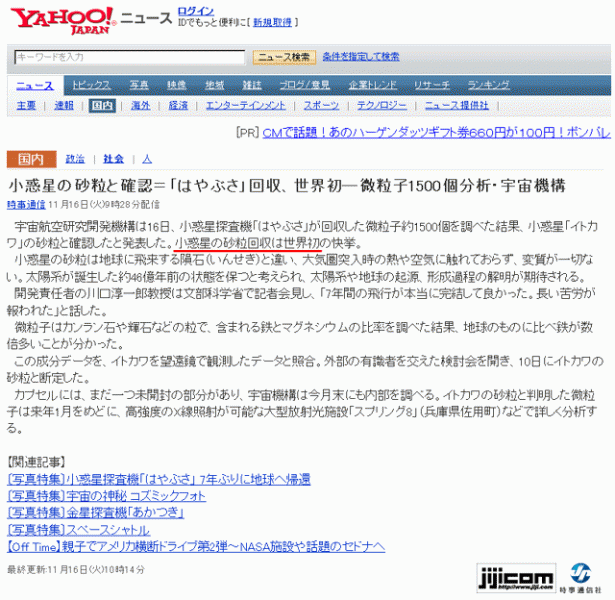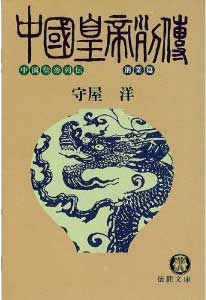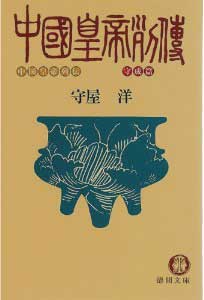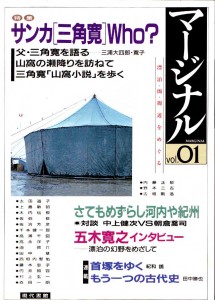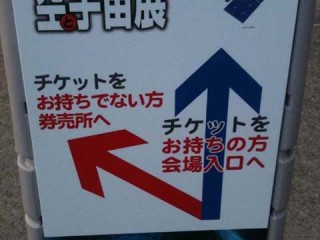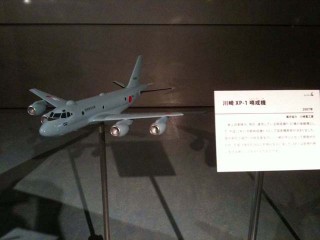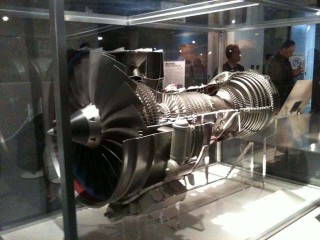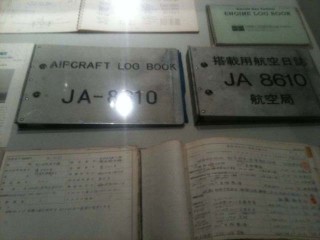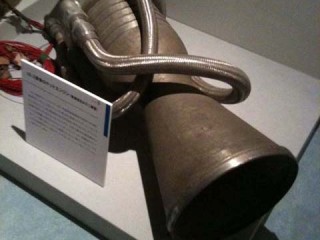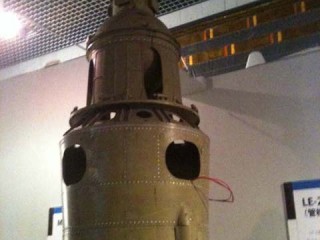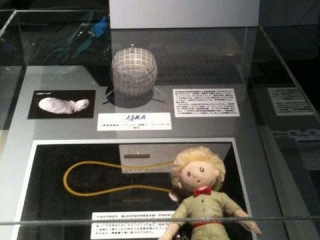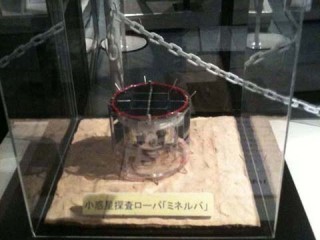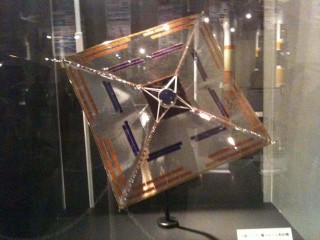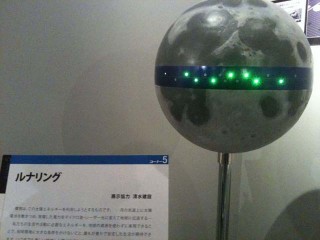渋谷の職場に通っていたころ、お昼休みの巡回コースでした。
大学生だったころにも行った記憶があるのでたぶんかなりの歴史のあったお店。
これも時の流れか。

(閉店を惜しむひとたちが閉店時刻の18:30頃には店の前でおもいおもいに集まっていた)
考えてみれば、道玄坂のこのヤマハに至るまでの店舗という店舗は、実は数年前からほとんどシャッターが閉まっていた。
一見華やかに見える渋谷の街でも少し視点をずらせば、今の世の中の縮図が見えるということか。
真向かいのケ○タッキーの窓越しに。
(ちょっと雪みたいに見えるがストロボの反射ですw)
席がないので3階の喫煙席へしかたなく座ったんだが、このケ○タッキーでも「3階は20:00以降ご利用できません」とあった。
客の入りと維持費のバランスがあわないんだろうか。
ひょっとするとこの日に限ったことだったのかもしれないが。
しかしひさびさに入ったファーストフードの単価を高く感じる自分がいる、貧乏はイヤじゃのう・・・。
前後するがハンズで椅子の修繕、というか改造できないかと探していた1/4インチ25mmのボルトネジとそれにあわせたプレートを購入。
(きょう合わせてみたが径はあってたが別の理由で使用不可、無念 orz)
その後、下北でオダニッチから声かけてもらっていたのでひさびさにSTEPをみる。
いやーここは毎回大人のクオリティ。安心して楽しめます。
DVカムも持っていってたんだが、狭いハコだったので廻せず。
CASIOのコンデジで一曲撮ってみるがメモリーカードの残量考えてなくてほどよく1曲だけ―それも途中ちょん切れな感じでw
まあおかげでひさしぶりにライブらしい感じで演奏自体を楽しませてもらいました。
終演後、ダニーとちょっと話して
「自分と自分の周りの人たちとなんとか楽しくやっていけるだけの稼ぎがあれば、いまの時代それはそれで幸せなことだよね」と。
ほんとそう思う。
世の中の一線の人たちをけなしたり、バカにしたりするつもりでいうのでもない。
お金の大切さや、いい意味での「欲」の大切さもわかっているつもり。
ただ、身体や心を壊してまで仕事にしがみつくのもやっぱりおかしいよね?
仕事も大切、稼ぐことも大切。
けど「仕事」だけが自己目的化したり、そこでしか人間関係がないとしたら―
それも貧しい話、ものすごく。
結局そういった場所でしか、多くの人が自分の居場所や関係性作れなくなっているんじゃなかろうか。
それってリスク分散の意味でも実はすごく危険なことなんだけどな。
かといって「職場」と「家庭」以外の自分の居場所をぱっと作れる人というのも、もの凄くすくないような気がする。ヘンに内輪指向の日本人、あぶないね。
(だから毎年3万人ほど自殺しとるんだろう―それを平気に思ってるのがもの凄く恐いが)
まあそんなこんなをつらつらと思いながら、このブログを書いていると、庭先で大家さんちから出発する火の用心の拍子木の音が聞こえる。
もう年の瀬・・・はやい、はやい。