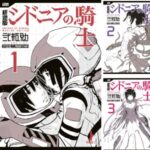昨今の日本経済の先行きは政治・経済のあまりのダメッぷりにお先真っ暗な感じだが、ダメダメ言っててもそこで我々は生きていかんとならないわけで。
で、なにかヒントはないものかと探してたときに見つけた一冊。
amazonでみつけて買うタイミング計ってたんだけど偶然近所のbookoffで発見し即げっと。
表紙とタイトルだけ見るとネトウヨ御用達の日本マンセー本のように間違えかねないがさにあらず。
内容としては日本で奇跡的に発達した「大都市鉄道網のエネルギー効率の良さが日本経済の大きなアドバンテージになる」という鉄道・交通を主題とした都市論の一冊。
かなりの力作でないようぎっしり。
数ヶ月前に買っていたんだけど読みきるのにここまでかかった。
ポイントとしては日本は資源がないといわれ、事実その面があるが、国家としてのエネルギー効率というのはそれだけでは語れない―資源がないのでエネルギー効率をギリギリまで突き詰めている。さらにそれをより効果的にしているのが東京・大阪に発達した便利で正確な鉄道を中心とした交通網―その既存インフラが、エネルギー効率がますます求められるこの先の世の中にあって、日本文明がますます発展していく重要な”資源”となる、という論。
この主張を浮き彫りにするため、著者は欧米の非・効率的な鉄道網の実態や、その車社会の実態を支えているのが効率ではなく固定化された階級社会からくる心理的な側面にある、という指摘を展開。
(確かにこの視点はなかった)
またこれまでのマスコミの論調からは絶対黙殺されるであろう「エネルギー効率の悪い地方に鉄道や道路を整備するのは財政的にムダ」「大都市圏に人を集中させることのほうが実はいろんな問題の解決に役立つ」という指摘。
そしてこれまでの地方活性化などの一見「公平・平等」にみえる社会の論調が実は田中角栄の『日本改造論』から始まり、それが自然な形での都市の発展を歪めてしまったとも述べている。
山手線での「痛勤」(通勤)の苦痛を身をもって体験した自分としては「山の手線内の従業員五千人以上の企業には重加算税を!」ぐらいに思ってるんだけど(笑)、確かに本書にある大都市への集中のメリットというのは真剣に考えてみる必要があるな、と本書を読んで考えが変わった。
特にこれからどんどん過疎化し、縮小していく地方都市に対して、果たしてどこまで資本を注入して「生命維持」させるべきなのか?
こう書くと「地方切捨てだ!」といわれるかもしれないが、傾向として「朽ちて」いく方向にあるものに―得にそれが一時的な刺激(カンフル剤)で下落傾向の変わらないそれに―無理やり資本注入して「生命維持」するほうが自然に反するのではないか?
もちろん故郷や緑の杜に愛着があるのもわかるし、住み慣れた土地を離れ人ごみだらけの都市の生活には耐えられそうもない、もっと余裕のある人間らしい暮らしをしたい―そう思う人も多いだろうと思う。
それがかなえられれば良いと思うのだが、たぶんそれはこの先人口の減っていくのが確実なこの国にあっては「とても贅沢なこと」になっていくと思うのだ。
これまでの「贅沢」とはま逆に見えるかもしれないが「贅沢」は「贅沢」だ―そう、「贅沢」をするには「金」が要る。
いやな話だけど。
問題はそういった「贅沢」になってしまった田舎暮らしを「公平・平等」の美名の下に政治的な資本の投下で維持していくのか・いけるのか。
どうも昨今の日本経済の落ち込みっぷりからするとそれはやりたくてもできなくなっていくだろうし、そこをムリに続けていくとまさに「国敗れて山河あり」になりかねなりだろう。
故郷を失い、未来を得る―両方得るのは残念ながらありえない。
希望を与えてくれた本ではあるが、ちょっとその点は複雑ではあった。
まあそういうセンシティブなところを抜きにして読めば非常に刺激的な本ではある。
ただ著者が非常にテンションを持って書かれた一冊のようなのでところどころ暴走気味なところもある(笑)。
ただしその暴走も根拠のないものではなく、勢いあまって筆が滑ったというような感じか。
(確信犯のような気もするが:苦笑)
その点頭に入れて読むなら、今後の日本の方向性を考える上で非常に重要な示唆をたくさん与えてくれる良書だと思う。
興味のある方は是非。