ようやく念願の5回分全部使い切りを達成(違

御嶽山の翌日、きっぷの有効が今日までということで強制出撃。
まず東京駅まで出る。
総武地下ホームを掲揚地下ホームと勘違いし、電車を一本逃す。
30分ほど待って成田行きに乗ることに。
総武線快速というのははじめてだったんだが、意外と順調に進む。
成田着。鹿島線に乗り換えのため30分待ち。

いったん外に出るが、余裕があるようでない待ち時間なので、駅ビル内のそば屋で昼食。

とくに心揺さぶられるものなかったので、天そば注文。
特筆するべき味ではなかったが(まずくもない)、量は多くて海老二本付き、わかりやすい満足感。
客層がめっちゃガテン系ばかりのお店だったので、そういうニーズの店なのかも(一瞬飯場に迷い込んだのかと思った:苦笑)

腹もふくれたし、時間も丁度よいころ合い。鹿島線に乗るべくホームへ。

(電車を待っている間に構内の電線に止まってたツバメさん)
この鹿島線沿線は、ここ数回のった山沿いの景色と違い、延々と平野部が続く。
乗客はまばらだが、どうも同じく18きっぱーらしい白髪のじい様がその道中で知り合いになられたおばさまときゃっきゃうふふされておるw青春じゃのう、まあ楽しんでください(棒)
そして今回めずらしくここで腹痛。小学校下校時のトイレがないという悪夢がよみがえるw
せっかくの利根川を越える陸橋からの景色も余裕がなく堪能できず。
幸い一駅で終点鹿島神宮だったので助かった。

駅を出るとゆるい坂道。
途中で塚原朴伝先生の像が

しかしその先になぜか楽器屋がwおいおい、ここはある意味”上り兵法下り音曲”の語源の地やろ!?こんなとこで楽器屋やってどうする(笑)

それを越えると上り坂は終わり、左に折れるとまっすぐな参道が見えてくる。
その道をまっすぐ行くと大鳥居が見えてくる。

白木の鳥居に赤い日の丸が風にはためいていて美しい。

残念ながら鳥居修復中のせいか正面からは通れず脇道から参道へと廻る。




木々が高く、潤沢な雨量と霞ヶ浦・坂東太郎沿岸という肥沃な土地がこれだけのものを育ててきたんだろうなどと推測。

その木々のおかげで空気が澄み、非常に良い感じの境内。
まずご本殿からお参り。

武甕槌命(タケミカヅチノミコト)をお祭りしているとのこと。雷と剣の神様なのね。
以前行ったことのある諏訪神社の神様とは因縁浅からぬお相手らしい。
このあたりの事情、お参りする時にどっちにどう義理立てすればいいのか(苦笑)。
参道に対して中央でなく側面に御宮があるというのがどことなくお伊勢さんと似ている。
参道を進むと途中に熱田神宮の摂社?のようなものがあったのでお参りしておく。
高い木々に囲まれた参道をさらに奥に進むと奥宮が。これは本殿よりさらに古い感じで素晴らしい。

慶長年間(1600年代)初頭の作らしい。そういうものがこれだけ残っているというのは素晴らしいなあ。

さらにこの奥宮の奥を曲がってしばらく進むと「要石」が祭られている。


これは地震を起こすなまずの頭を押さえていると言われている岩で、かつていくら掘っても掘り出せなかった巨岩の先端・・・ということらしい。

(芭蕉?の句碑)


昨今の大きな地震がこれ以上ひどくならないようにとお願いしておく。そういえば奥宮からここまでくる道の十字路のところになまず押さえている神様の像があった。

一通りお参りしたので本殿近くまで戻ってきて宝物殿で鹿島の大太刀ほかを見る。

(こちらは遷宮時の御仮屋、これも古くて立派だった)

ここも鶴岡八幡の時と同じようにさほどおおきな宝物殿ではないんだが、いろいろおもしろいものが展示されていて見て正解だった。
大太刀をはじめとする刀剣類―えらいもんで古刀のほうが迫力あるというのが素人目にもわかる(※)―や大鎧・鐙など、も面白かったが、個人的に一番おもしろかったのは展示の一番最初にあるなまず関連の伝承の資料。
地震が起きた時になまずが街中で町民たちにぼこぼこにされてたり(笑)、地震起こしたあとなまずが集団で鹿島の神様に詫びを入れにいってたりと、なんかすごいほのぼのした。
これみたときにあまりにも面白くてひとりにやにやしてたので、はたから見たらきっと頭のおかしいひとにみられていたと思うw
宝物殿を堪能し、ひととおり境内のめぼしいところは見たので撤収・・・とおもったらまだいろいろと脇宮がありましたよ。

須賀神社ほかいくつかの神様を祭っている場所があって、ここお参りしたのはいいけど、なんかどこまで入っていいのか分からん感じで混乱した。
あと正面の大鳥居修復中で脇を通るので見逃さずに済んだお稲荷様にもお参り。

(鳥居脇に生えている立派な感じの木)

ということで境内一通り拝見させて頂いたので神宮をあとにする、いい場所だった。

あ、そうそう、鳥居を出た後の参道の脇にも海神さまを祭ったお社あったのでお参りしておく。


(由来は不明だがなぜかキジが)

(構内にも鹿園あったがここでは彫刻も)
これでひととおりご挨拶したかと思うので、駅へ向って撤収。
下りの坂道から町を眺めてみると、この神宮はある程度の高さにあったので(津波とか含め)、神域として長く続いてきたのかなとか思ったり。
(事実ここまでの鹿島線の駅名には潮来(いたこ)という地名があったり、先の震災では途中の佐原という町はけっこう被害が出ていたようだ)
帰りは、ほんとはもっと早く到着できていたら臨海鹿島線というので水戸まで上がって常磐線で帰れればいいかなと思っていたけど、時間的にとても無理なので素直に来たルートをたどって戻ることに。
で、例によって成田から総武快速線に乗れたので早かった・・・とはいえやっぱりちょっと微妙に遠い距離ではあるのね。
まあ今回で勝手もわかったことだし、次からはもう少し乗り継ぎうまくやって水戸経由もやってみたいところ。
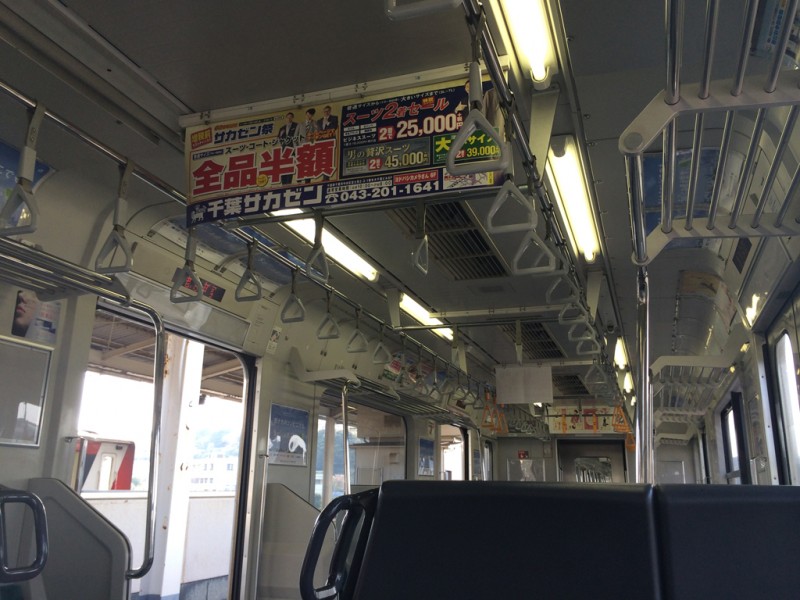
ということで、今回はなんとか18きっぷ全回分うまく使いきれたので、よかったよかった。
今後はもう少し泊まりとかを組み込んで行動の幅を広げていきたいな、と考え中。

(※)総じて古刀のほうが迫力あったのは事実だが新刀・・・というか現代刀?なのかなも立派なものがあった(確か展示右列の一番下のヤツなんかは骨太で迫力あった)
もちろん国宝の大太刀とそれに合わせたサイズで作成・寄贈されたという甲冑というのも中二病ごころをくすぐりまくりでしたな(笑)。
